小説一覧
-
異世界転移に巻き込まれたけど、気づかれずに数カ月。反動で選んだ能力は快適さ優先!
14,190クル
カテゴリー内順位1位 / 9,194件
ジャンル内順位1位 / 4,451件




 (98)
(98)
タイトルAI診断値65tai
- 舞台
- 異世界
- 主人公の性別
- 男
- 主人公の年齢
- 10代
- その他の要素
- 剣・魔法
- 転移・トリップ・召喚
- スローライフ
- グルメ
- 生産チート
- ご都合主義
- 出版化
- 書籍化作品(予定含む)
-
書籍化でタイトル変更しました。
MFブックスより一巻発売中!
ニコニコ漫画でコミカライズ展開中!
ぱっとしない人生から異世界転生したのにやっぱりぱっとしない人生。
かと思っていたら使えないスキルだと思っていた『ゲーム』が実はすごいことに気付き……。
くたびれたおっさんのいまさらなチート異世界ライフ開幕。
13,495クル
カテゴリー内順位2位 / 9,194件
ジャンル内順位2位 / 4,451件




 (11)
(11)
タイトルAI診断値54tai
-
「僕は両親に売られ、君の家に金で買われた。だが心まで自由にできると思うなよ。決して君に屈したりしない。愛するなんてもってのほかだ」
婚約者カインツとの仲が冷え切っていたセリア。
ひょんなことから前世の記憶を思い出した彼女は、自分が悪役令嬢もののマンガのヒロインに転生したと知る。
「あのマンガ、クソ長いうえにストレスフルなのよね」
マンガ通りに動けば、約束された幸せな未来が待っている。
だがそれまでの道筋が面倒くさすぎる。
茶番を演じたくないセリアは、別の方法で幸せをつかみ取ることにした。10,644クル
カテゴリー内順位3位 / 9,194件
ジャンル内順位1位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値66tai
-
結婚して五年目。
そろそろ子供が欲しいと言っても素気無くされる夫の秘密を偶然知ってしまった。
冒険者ギルドにサポーターとして登録している私――シーラの夫リオンは、結婚したらあまり行かなくていいはずの遠征に月の半分以上行っていた。
ある日、サポーター要員としてクエストに行った私は、偶然夫の姿を見てしまう。
彼は一人ではなかった。
彼のそばには優しい眼差しで見ている母子がいた。
リオンの事を「パパ」と呼ぶ女の子。リオンが腰に手を回す女性。
それは紛れもなく家族と呼べる光景だった。
【ご注意】
※作中に「私生児」「婚外子」と表現があります。
婚姻中の不貞で生まれた子は「私生児」、何らかの要因でシングルで生まれた子は「婚外子」とし、明確に差別化をしています。この異世界この国独自の文化となりますので実際とは異なります。
また、作者の他作品とも関係ありませんのでこの作品のみの解釈と認識していただきますようお願いします。
※作者の脳内異世界のお話です。
※執筆集中の為感想欄は閉じています。
9,198クル
カテゴリー内順位4位 / 9,194件
ジャンル内順位2位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値83tai
-
竜王の治める国ソフームには、運命の番という存在がある。
運命の番――前世で深く愛しあい、来世も恋人になろうと誓い合った相手のことをさす。特に竜王にとっての「運命の番」は特別で、国に繁栄を与える存在でもある。
「ロイゼ、君は私の運命の番じゃない。だから、選べない」
ずっと慕っていた竜王にそう告げられた、ロイゼ・イーデン。しかし、ロイゼは、知っていた。
ロイゼこそが、竜王の『運命の番』だと。
「エルマ、私の愛しい番」
けれどそれを知らない竜王は、今日もロイゼの親友に愛を囁く。
いつの間にか、ロイゼの呼び名は、ロイゼから番の親友、そして最後は嘘つきに変わっていた。
名前を失くしたロイゼは、消えることにした。
6,258クル
カテゴリー内順位5位 / 9,194件
ジャンル内順位3位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値0tai
-
KADOKAWA・電撃の新文芸様より 2022/9/16 発売!
書籍化に伴い、タイトル変更しました。
旧題:Iris Revolution Online 〜俺のぼっちをあの娘が実況中継しています〜
VRMMOひとりぼっちの無人島生活(実況あり)
『Iris Revolution Online』――フルダイブVR技術を確立した六条グループが、巨額の資金を投じて作らせたと言われるVRMMO。
伊勢翔太(ショウ)は限定オープンに当選したユーザーの一人としてその世界――アイリスフィアへとダイブする。
しかし、彼が降り立ったのは誰もいない無人島。
長期出張中の両親の代わりに妹の面倒をみたり、元来サポート気質のショウはIROというゲームの中に『誰もいない一人の世界』を持とうとしたのだった。
順調に無人島スタートしたショウだが、不用意に配信していたのをミオンというリスナーに見つかってしまう。
実はそのミオンはクラスメイトの出雲澪。
同じ電脳部に入ったことでお互いに気づいた二人は、部活動の一環として二人三脚での無人島ライブを始めることに。
怪我しているのを助けて懐いた狼(?)のルピとともに、のんびり無人島ライフを目指すショウだが、その行動はライブを通してゲーム世界全体に影響を及ぼしていくのであった……
【登場人物】
伊勢翔太:ショウ … 高1。過度の気遣い性からソロ希望。
出雲 澪:ミオン … 高1。内気すぎる性格だが、実際は……
香取鈴音:ベル … 高2。電脳部部長。和風美人なのに残念度高め。
熊野やえ:ヤタ … 担任&電脳部顧問。おっとり切れ味抜群。
伊勢美姫:セス … 翔太の妹。中3。天才となんとかを地で行くタイプ。
柏原直斗:ナット … ショウの幼馴染&親友で天然陽キャ。
鹿島恭子:ポリー … クラス委員長。ショウとナットのお目付け役。
伊勢真白:マリー … 翔太の姉。大1。感性だけで生きてる系。6,142クル
カテゴリー内順位6位 / 9,194件
ジャンル内順位1位 / 567件




 (7)
(7)
タイトルAI診断値25tai
-
ベルニ公爵家の令嬢として生まれたエルシーリア。
エルシーリアには病弱な双子の妹がおり、家族はいつも妹ばかり優先していた。エルシーリアは八歳のとき、妹の代わりのように聖女として神殿に送られる。
それでも頑張っていればいつか愛してもらえると、聖女の仕事を頑張っていたエルシーリア。
十二歳になると、エルシーリアと第一王子ジルベルトの婚約が決まる。ジルベルトは家族から蔑ろにされていたエルシーリアにも優しく、エルシーリアはすっかり彼に依存するように。
しかし、それから五年が経ち、エルシーリアが十七歳になったある日、エルシーリアは王子と双子の妹が密会しているのを見てしまう。さらに、王家はエルシーリアを利用するために王子の婚約者にしたということまで知ってしまう。
何もかもがどうでもよくなったエルシーリアは、家も神殿も王子も捨てて家出することを決意。しかし、エルシーリアより妹の方がいいと言っていたはずの王子がなぜか追ってきて……。5,779クル
カテゴリー内順位7位 / 9,194件
ジャンル内順位4位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値86tai
-
天涯孤独で生きてきた極道の男は、騎士爵家の三男・リューとして異世界へ転生。今まで縁がなかった家族の愛を一身に受けてスクスクと成長し、やがて気づいた。優しすぎる彼らは先祖代々、ケンカは強いが稼業は弱い超貧乏家系だということに!
これは自分が一肌脱ぐしかないと、未知のスキル《ゴクドー》と前世の裏稼業知識を活かして作ったコーヒーやチョコ、リヤカーを売りさばき、畑の改善で原料の収穫量はさらに増加、祭りで出店した屋台は大繁盛と、次々に新たなシノギを軌道に乗せていく。しかし、着実にシマを増やす中でゴロツキ貴族から逆恨みされた一家には危険が迫っていて……?
心優しき元極道少年の義理と人情の領地経営ファンタジー!
※カクヨム・なろうでも掲載中5,221クル
カテゴリー内順位8位 / 9,194件
ジャンル内順位3位 / 4,451件




 (9)
(9)
タイトルAI診断値44tai
-
幼い頃の鑑定によって、覚醒とユニークスキルが約束された少年——王道光(おうどうひかる)。
彼はその日から探索者――シーカーを目指した。
そして遂に訪れた覚醒の日。
「ユニークスキル【幸運】?聞いた事のないスキルだな?どんな効果だ?」
スキル効果を確認すると、それは幸運ステータスの効果を強化する物だと判明する。
「幸運の強化って……」
幸運ステータスは、シーカーにとって最も微妙と呼ばれているステータスである。
そのため、進んで幸運にステータスポイントを割く者はいなかった。
そんな効果を強化したからと、王道光はあからさまにがっかりする。
だが彼は知らない。
ユニークスキル【幸運】の効果が想像以上である事を。
しかもスキルレベルを上げる事で、更に効果が追加されることを。
これはハズレと思われたユニークスキル【幸運】で、王道光がシーカー界の頂点へと駆け上がる物語。5,176クル
カテゴリー内順位9位 / 9,194件
ジャンル内順位4位 / 4,451件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値44tai
-
「俺が責任を取る」
そう言ってくれたあなたを、信じたのに。
戦場で負った傷で騎士を辞めた私に、あなたは結婚を申し出た。
それが“愛”だと、信じたかった――
けれど、あなたは他所で「家族ごっこ」をしていた。
私のいない場所で、自分の居場所をつくっていた。
……もういい。私は私の人生を取り戻す。
これは、全てを失った元女騎士が
夫に突きつける、最後の答え。
そして、その後に見つける、大きな幸せ。
3,444クル
カテゴリー内順位10位 / 9,194件
ジャンル内順位5位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値67tai
-
猫を助けるためにトラックにはねられた「俺」は、実は重要だった猫を助けた見返りに他の世界へと転移することになった。
そこで「俺」が選んだ仕事は鍛冶屋。家族が増えたり事件に巻き込まれたり、バタバタするけど、「俺」は果たして最後は静かにクリエイティブな暮らしを満喫できるのか。3,225クル
カテゴリー内順位11位 / 9,194件
ジャンル内順位5位 / 4,451件




 (19)
(19)
タイトルAI診断値30tai
ファンタジーai値
587ai
-
自然破壊が進む地球に対して女神は人々に試練を与えるために世界のあらゆる場所に『ダンジョン』を出現させ、『期間内に探索ランキングで一定数値を残さなければ人間は滅びるでしょう』と言い残した。
残された人々はダンジョンを攻略する『探索者』を募り、世界は探索者優遇の時代に入る。
そんな中、永遠のレベル0と蔑まれた鈴木日向は、クラスメイトのイジメによって不思議なダンジョンに落ちる。
レベルが0から上昇しない日向だったが、実はレベル上昇しない代わりにスキルを無限に獲得できる力を持っていたのだ。
日向は帰りを待っている妹のために、あらゆるスキルを獲得して謎のダンジョンを攻略して最強探索者となる。
「あれ? 探索ランキングの1位の人、名前が表記されてない?」
謎のランキング1位の登場により、世界は大きく変わっていく。もちろん――――――日向の生活も。
2,719クル
カテゴリー内順位12位 / 9,194件
ジャンル内順位6位 / 4,451件




 (2)
(2)
タイトルAI診断値65tai
-
私にはもう何もない。何もかもなくなってしまった。
地位や名誉……権力でさえ。
否、最初からそんなものを欲していたわけではないのに……。
望んだものは、ただ一つ。
――あの人からの愛。
ただ、それだけだったというのに……。
「ラウラ! お前を廃妃とする!」
国王陛下であるホセに、いきなり告げられた言葉。
隣には妹のパウラ。
お腹には子どもが居ると言う。
何一つ持たず王城から追い出された私は……
静かな海へと身を沈める。
唯一愛したパウラを王妃の座に座らせたホセは……
そしてパウラは……
最期に笑うのは……?
それとも……救いは誰の手にもないのか2,681クル
カテゴリー内順位13位 / 9,194件
ジャンル内順位6位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値59tai
-
書籍化作品。
子供の頃から異世界ものに憧れ、青春を捧げた青年が自力で異世界に行く。
そして、その世界ではポンコツと思われていた文字化けスキルの能力を少しずつ開花させながら、主人公が頭脳と努力で立ち回り成長していく、そんなに甘くない生い立ちから始まる異世界でのサクセスストーリー。
※カクヨムにて最高総合年間ランキング2位。
総合累計ランキング15位。2,640クル
カテゴリー内順位14位 / 9,194件
ジャンル内順位7位 / 4,451件




 (11)
(11)
タイトルAI診断値52tai
ファンタジーai値
608ai
-
結婚目前と思ってた彼氏に振られて、ソロキャンを始めてみたら、そこそこ楽しくなってしまった私。
望月五月。27才。
何の因果か、山を買うことに。それがまさかの異世界だったなんて。
ただいま、ログハウスでモフモフたちと山暮らし。
恋愛よりもスローライフな五月の異世界暮らし、満喫中。
※『山、買いました ~異世界暮らしも悪くない~』の続編2,414クル
カテゴリー内順位15位 / 9,194件
ジャンル内順位8位 / 4,451件




 (3)
(3)
タイトルAI診断値30tai
-
会社からの帰り道、主人公は大きな犬を轢いてしまう。
その瞬間、彼の頭の中に声が響いた。
≪モンスターを討伐しました。経験値を獲得しました≫
「え?」
突如として世界は変わったのだ。
モンスターが現れ、レベルやスキル、ステータスが存在するゲームの様な世界に。
これは、そんな現代ファンタジーと化した世界で、頑張って生き延びる主人公の冒険譚である。2,291クル
カテゴリー内順位16位 / 9,194件
ジャンル内順位9位 / 4,451件




 (47)
(47)
タイトルAI診断値50tai
-
私は昔から空気を読むのがうまかった。だから、悲劇のヒロインになりたい異母妹マリンの望み通り、悪役を演じている。そうしないと、マリンを溺愛している父に食事を抜かれてしまうから。
今日のマリンのお目当ては、バルゴア辺境伯の令息リオだ。
はいはい、私が頭からワインをぶっかけてあげるから、あなたたちはさっさとくっついてイチャイチャしなさいよ……と思っていたら、バルゴア令息に捕まれた私の手首がゴギッと鈍い音を出す。
悲鳴をあげるバルゴア令息。
「叔父さん、叔母さん! や、やばい!」
「えっ何やらかしたのよ、リオ!?」
そんな会話を聞いたのを最後に、あまりの痛みに私は気を失ってしまった。2,263クル
カテゴリー内順位17位 / 9,194件
ジャンル内順位7位 / 1,714件




 (2)
(2)
タイトルAI診断値79tai
恋愛ai値
471ai
-

長年やっていたゲーム世界に転移し喜んだのも束の間。豚と見紛うほど太った悪役キャラ、成海颯太に転移してしまった。
美男美女だらけの学校で恋愛も楽しめるゲーム世界だというのに『ブタオ』と呼ばれ、クラスメイト達に蔑まれる学校生活。このままストーリー通りに進めば婚約者である幼馴染に捨てられ、最後は退学に追い込まれてしまう未来が待っている。
そんな悲惨な状況でも諦めない屈しない! いずれはハーレムを築き、トップ冒険者になってやる!
これは恋愛もダンジョンも無双する、とある男の物語。2,224クル
カテゴリー内順位18位 / 9,194件
ジャンル内順位2位 / 567件




 (5)
(5)
タイトルAI診断値15tai
ファンタジーai値
565ai
恋愛ai値
563ai
-

第七回ネット小説大賞受賞しました!書籍化されます…!
魂の修復のために「よそ」の世界に行くことになった「ゆうた」。
異世界で再スタートしてがんばります。色々な人(?)と出会い、幼いユータは素直に教えられたことを吸収する・・あれ、それって人間ができることだっけ?のほほんと色んなチートを身につけ、駆け上がれ!最強への道??
いえいえ!目指すはもふもふ達と過ごす、穏やかで厳しい田舎ライフです!
※序盤はモフ成分少なめ
お疲れ気味の現実の中で、深く考えずにサラッと読めるような、ユータと一緒に童心にかえって楽しめるようなお話にしたいと思っています。
残酷な描写は多分ないけれど、流血くらいはありますので念のため…。
2,221クル
カテゴリー内順位19位 / 9,194件
ジャンル内順位10位 / 4,451件




 (70)
(70)
タイトルAI診断値52tai
ファンタジーai値
631ai
-
イリス王国の王女リーディは、停戦の条件として敵国に嫁ぐことになった。
結婚式は、1年後。
それまで敵国で、人質のような生活を送ることになる。
そんな生活の中、婚約者の敵国の王が、ある女性に夢中になっているという噂を聞いた。それは、異世界から迷い込んできた女性らしい。
リーディは噂の真相を探ろうと、王城の侍女に扮して、調査を開始する。2,091クル
カテゴリー内順位20位 / 9,194件
ジャンル内順位8位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値91tai
-

戦争で活躍し孤児から救国の英雄となった主人公ディアスはその報酬として国の外れの外れ、最果てといっても過言ではない土地を領地として王から拝領する。
いざその領地へと向かったディアスだったが、そこは人っ子一人居ないだだっぴろいだけの草原で、領民が居ないどころかディアスが住む家も無く、食料も無く、ディアスは呆然と草原に立ち尽くすことになる。
果たしてディアスは領主としてやっていけるのか、それ以前に何もない草原でどうやって生活するのか、生きていくことは出来るのか。
前途多難な新米領主の日々を綴る剣と魔法の世界の物語。2,055クル
カテゴリー内順位21位 / 9,194件
ジャンル内順位11位 / 4,451件




 (15)
(15)
タイトルAI診断値38tai
ファンタジーai値
634ai
- 主人公の性別
- 男
- 主人公の年齢
- 30代
- その他の要素
- 剣・魔法
- モフモフ
- 出版化
- 書籍化作品(予定含む)
-

ラヴィレンス高等学園の奨学生メグミは、生活費と将来のために、イジメられながらも学園へ通っていた。
そんなある日、なぜか学年一の美少女であるサーシャ・バークレーが彼をかばい、イジメの主犯格である皇太子の怒りを買ってしまう。
皇太子が彼女を攻撃し、もうダメだと思ったとき……教室全体がまばゆい光に包まれ……気がつくとクラスメイト共々、ダンジョンマスターである魔王に転生していた。
ダンジョンポイントの初期値が、転生前の貯金額と連動していたせいで、最初のうちこそ苦労するメグミだが、地道に力を蓄え成り上がっていく。
負ければ殺される魔王として生き、サーシャ嬢と関わる中で、彼の価値観にも少しずつ変化があらわれ……2,010クル
カテゴリー内順位22位 / 9,194件
ジャンル内順位12位 / 4,451件




 (7)
(7)
タイトルAI診断値55tai
-
異世界に転生した元サラリーマンの記憶を持つ少年、クレイ。
平和な村に温かい家庭。
順風満帆な生活を送っていたはずが、五歳の誕生日に最弱スキルを授かってしまった事で、両親の期待を裏切ってしまう。
一年後、クレイは両親に一服盛られた末に、王都に捨てられてしまった。見知らぬ土地で周囲の助けも期待できない。このままでは飢えて死んでしまう。
何とかしたいけど、お金も無い。頼れるのは己の知識と最弱スキルだけ。
クレイはこの世界で、平穏な暮らしを手に入れる事が出来るのか。1,908クル
カテゴリー内順位23位 / 9,194件
ジャンル内順位13位 / 4,451件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値46tai
-
戦闘狂でF級探索者の俺が、ダンジョン配信者を助けて世間から注目を浴びてるらしいが気にせずマイペースに行くとしよう 〜だから実力を疑われても俺は知らん。で、なぜ幼馴染と助けた配信者は俺に寄ってくるんだ〜
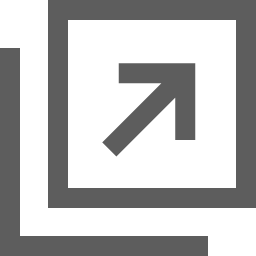
あるダンジョンに通い詰めるF級探索者、天城滅也(てんじょう めつや)は生粋の戦闘狂だった。
毎日ダンジョンへ潜っては膨大な魔物を狩っているバトルジャンキーである。
ただ毎回ダンジョンの深層で戦っていた為、その実力が世間に知られることはなかった。
そんなある日、なぜかダンジョンの深層で窮地に陥っていた女性ダンジョン配信者を助けることになり、滅也はネットで注目の的となる。
F級探索者の異常な実力に世間は様々な反応を示すが、滅也は気にせずマイペースに行動する。
ただ幼馴染や配信者、S級探索者達はそれを放ってはおかなくて――1,831クル
カテゴリー内順位24位 / 9,194件
ジャンル内順位14位 / 4,451件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値70tai
-
動物に好かれ過ぎて毎日苦労していた工藤優人(くどうゆうと)は、熊犬に勢いのまま吹き飛ばされ、トラックに轢かれてしまい、転生を果たした。
転生を果たした優人はクラウドと名付けられ、地方貴族ベルン家の長男として新しい人生を送る事になるが、異世界の動物(魔物)から好かれ過ぎてしまい、気が付けば周りに多くの魔物が集まってきて、しまいには異種族まで集まり始める。
家族、従魔、仲間と一緒に面白おかしく、楽しい毎日を生きていく。1,642クル
カテゴリー内順位25位 / 9,194件
ジャンル内順位15位 / 4,451件




 (2)
(2)
タイトルAI診断値50tai
-
10歳で政略結婚させられたレオニーは、2歳年上の夫であるカシアスを愛していた。
しかし、結婚して7年後のある日、カシアスがレオニーの元に自身の子どもを妊娠しているという令嬢を連れてきたことによって、彼への愛情と恋心は木っ端みじんに砕け散る。
皮肉にも、それは結婚時に決められた初夜の前日。
レオニーはすぐに離婚を決心し、父から離婚承認を得るため実家に戻った。
だが、父親は離婚に反対して離婚承認のサインをしてくれない。すると、日が経つにつれ最初は味方だった母や兄まで反対派に。
いよいよ困ったと追い詰められるレオニー。
そんな時、彼女の元にある1通の手紙が届く。
その手紙の主は、なんとカシアスの不倫相手の婚約者。氷の公爵の通り名を持つ、シャルリー・クローディアだった。
果たして、彼がレオニーに手紙を送った目的とは……?1,620クル
カテゴリー内順位26位 / 9,194件
ジャンル内順位9位 / 1,714件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値65tai
-
ある時、世界中にモンスターとダンジョンが出現した地球の日本で、佐藤普人は高校デビューする為に探索者登録した。しかし、適性検査によって分かったのは、レベルもスキルも能力値もないという無残な結果。
絶望しかけた普人だったが、ステータスに熟練度という項目だけが表示されているのを思い出して極めることに。
レベルもスキルも能力値もなく、探索者だとは恥ずかしくて誰にも言えない普人は、緊張して高校デビューに失敗してしまう。にもかかわらず、高校生活が進むにつれ、美少女達が彼の周りに集まっていく。その本当の理由を本人は知らない。1,527クル
カテゴリー内順位27位 / 9,194件
ジャンル内順位16位 / 4,451件




 (4)
(4)
タイトルAI診断値64tai
-

【ブレイヴ・ヒストリア】
それは、ある世界で一世を風靡した、ファンタジーRPGだった。
物語の主人公ローランは、ククル村という田舎の村で穏やかな日々を、幼馴染の少女アリシアと共に過ごしていた。
慎ましくも穏やかな、幸せな毎日。
しかし――ある日突然。
そんなローランの平穏な日常は脆くも崩れ去る事になる。
平和なククル村にある日、突然――レクス・サセックスと名乗る貴族の少年が現れる。
聞けば彼は、エルロード王国における、有数の貴族、サセックス家の嫡男であり、アリシアの体質に目をつけサセックス家に側室として迎え入れる為に、連れに来たという。
最愛の少女を奪われるという現実。
そんな現実を受け入れられないローランはレクス・サセックスに決闘を挑んでしまう。
これは、そんな【ブレイヴ・ヒストリア】の世界の悪役貴族に転生してしまった男の物語。1,502クル
カテゴリー内順位28位 / 9,194件
ジャンル内順位17位 / 4,451件




 (2)
(2)
タイトルAI診断値81tai
-

「エルヴィラ・ヴォダ・ルストロ。お前を聖女と認めるわけにはいかない! お前が育てていた『乙女の百合』は偽物だった! この偽聖女め!」
アレキサンデル様が、わたくしをそう罵ります。
皆が驚きの声をあげました。
「エルヴィラ様が聖女でなかった?」
「何かの間違いでは?」
それもそのはず。
本来なら、わたくしが、正統な聖女だと認定されるはずの儀式です。
それが、一転して、「偽聖女」呼ばわり。
さらにアレキサンデル様は、宣言します。
「聖女ではない女とは結婚できない! お前との婚約は白紙に戻す」
そこで、初めてわたくしは、口を開きました。
「ーー承知しました」
※カクヨム様でも連載してます。
1,481クル
カテゴリー内順位29位 / 9,194件
ジャンル内順位10位 / 1,714件




 (4)
(4)
タイトルAI診断値80tai
ファンタジーai値
494ai
恋愛ai値
456ai
-
現代で病死した俺は、RPGの世界に“破滅確定の悪役貴族”として転生してしまった。
家族には見限られ、勇者には蹂躙され、最終的には追放される未来が確定している……。
さらに俺のユニークスキルは、どこでも最高の睡眠環境を作り出せる『絶対快眠(スリープキング)』
戦闘や魔法には役に立たないとされる“ハズレスキル”だ。
しかし、よく考えたらこれは魔力や疲労を即座に回復できる最強スキルなのでは?
魔法訓練を繰り返せば、無限に鍛えられる!
かつてのレオンは勇者への劣等感から破滅へ突き進んでいったが、俺は違う。
このスキルを活かし、悪役の運命をぶち壊してやる!
絶対に破滅しないため、俺は“睡眠チート”で強くなる!
だが、周囲の認識も次第に変わっていき――
「……あれ? もしかして俺、悪役じゃなくて“英雄”ポジションになってない?」1,469クル
カテゴリー内順位30位 / 9,194件
ジャンル内順位18位 / 4,451件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値69tai
-
「今すぐ出ていけ」と言われたらその通りにするべきだろう。
イヴェッタ・シェイク・スピア伯爵令嬢はこれまで言葉の裏を読む茶番に付き合って生きて来た。卒業式の後のパーティで婚約者であるウィリアム王子から突然婚約破棄を突き付けられ、自分の代わりに愛らしい男爵令嬢が殿下の結婚相手となるらしい。
先代国王から命じられているはずの神殿へのお役目はどうするのだろうか、あぁ、なるほど、王族の婚約者の立場だけ奪われて、神殿に一生奉公し続けろということか。
「よし、言われた通りに、出て行こう」
イヴェッタはその日のうちに荷物をまとめて国境を越えた。
遺跡で300年前に施されたエルフの封印を解いてしまい、目覚めた超絶美形のエルフはイヴェッタを「妻にします」と離さない!1,449クル
カテゴリー内順位31位 / 9,194件
ジャンル内順位11位 / 1,714件




 (2)
(2)
タイトルAI診断値75tai
-
「また転生してしまった」
とある赤ん坊レクスは、英雄と賢者という二つの前世を持つ転生者だった。
「今度の人生では陰謀や騒動に巻き込まれないように気をつけよう」
前世の記憶から目立つ事の危険を学んでいたレクスは地味に生きる事を誓う。
「そして前世からの憧れの職業、自由の象徴である冒険者になるんだ!」
念願叶って冒険者となったレクスは、目立たない様地味な依頼で日銭を稼ぐ毎日を満喫する。
「すみませーん、薬草採取してたらドラゴンに襲われたんでついでに狩ってきましたー」
レクスは気づいていなかった。
自分の地味が滅茶苦茶派手だという事実に。
「それにしても冒険者ランクって簡単にあがるんだなぁ」
それに気づかない少年は今日も平然と周囲の人間の度肝を抜く。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この度書籍化が決定致しました!
マンガUP様にてコミカライズがスタートいたしました!
皆様応援ありがとうございます!1,398クル
カテゴリー内順位32位 / 9,194件
ジャンル内順位19位 / 4,451件




 (18)
(18)
タイトルAI診断値71tai
-
グラス森討伐隊で働く聖女シーナは、婚約者に侯爵令嬢を害した罪で婚約破棄と追放を言い渡された瞬間、前世の記憶を思い出した。自分が搾取されていた事に気付いたシーナは、喜んで婚約破棄を受け入れ、可愛い侍女キリのみを供に、魔物が蔓延るグラス森に一歩踏み出した。
これは、虐げられていた追放聖女がその気もないのに何となく勝ち上がっていく、多分サクセスストーリーである。
※長編となっています。ゆっくり進める予定です。
※残酷な描写があります。
※恋愛要素もあります。1,384クル
カテゴリー内順位33位 / 9,194件
ジャンル内順位20位 / 4,451件




 (7)
(7)
タイトルAI診断値36tai
-
気がついたら異世界で八歳の子供となっていた。最初は異世界に興奮してたけど、平民に転生したから、お風呂はないし、水洗トイレじゃないし、料理は素材の味だし、日本の方が全然いい!
日本に帰りたいけど無理そうだから、この世界で快適な生活を目指すことにした。けど自分で作るのなんて無理だし……
え? 貴族は魔法具で水洗トイレ? お風呂もあるの? じゃあ俺、貴族を目指す!
そう決めた主人公が異世界で快適な生活のために奔走していたら、いつの間にか世界の救世主になっていた物語。1,362クル
カテゴリー内順位34位 / 9,194件
ジャンル内順位21位 / 4,451件




 (3)
(3)
タイトルAI診断値62tai
-
「……吸血種族。俺、ベジタリアンなんだけど」
フルダイブVR技術が、日常の物として広く普及した近未来。
VRMMORPG『Destiny Unchain Online』――レベル制を排した完全スキル制、 プレイヤースキル重視、PvP上等……そんな新作VRゲームのリリース当日。
満月紅はその開発者である父親の頼みにより、新しいヒューマンインターフェースデバイスのテスターとして、その世界へと降り立つ。
ところが気付いたら、その姿は吸血種族の少女になっていて……
加えてログアウト不可、さらには不具合により最初の街ではなく、辺境の森の中と波乱の幕開けとなるのだが……父の「命の危険は無い」という言葉を信じて、ひとまずゲームを満喫しようと歩み出す。
己を鍛え、ギルドの仲間を集め、なんの因果か「のじゃロリ」のロールプレイをする事となり、配信機能により視聴者からの人気を獲得し……やがて紅は『赤の魔王』クリム=ルアシェイアとして、名を馳せていくのだった。
そしてその影響は、現実世界の紅の体にも――……
1,345クル
カテゴリー内順位35位 / 9,194件
ジャンル内順位3位 / 567件




 (6)
(6)
タイトルAI診断値23tai
-
婚約者は、傍らに美しい恋人を抱きながら、婚約を破棄すると告げた。
そのショックで前世の記憶を思い出したクロエは、すべてを捨てて自由に生きようと思い立つ。
1,324クル
カテゴリー内順位36位 / 9,194件
ジャンル内順位12位 / 1,714件




 (3)
(3)
タイトルAI診断値67tai
-
かつて、異世界へと転生して英雄となった主人公。
そんな彼の人生は転生前は社畜、転生後はこれまた英雄として社畜の日々を送る正に地獄のような毎日だった。
「神様……休みを下さい……」
涙ながらに二度目の転生前に女神に頼んだ彼の二度目の人生はとある王国の第3王子だった。
優秀な兄2人のどちらかが王位を継ぐことは間違いなく、気楽な第3王子となった彼は、これまで習得した魔法や知識を活かしつつ、好きなように生きるように決意するが……?
これは、二度目の転生にてスローライフを求める主人公がのんびりしたり、遊んだり、料理を作ったり、押しに負けて婚約者を増やしたりする物語。
1,283クル
カテゴリー内順位37位 / 9,194件
ジャンル内順位22位 / 4,451件




 (3)
(3)
タイトルAI診断値52tai
-
明るく、いつも何かに一生懸命な蒼月 矜一は、小学6年生までは人気者だったが、なぜか国民全員が取得するステータスでレベルがいっさい上がらずにいた。
今まで矜一に嫉妬の目を向けていた者たちはこれ幸いとそれを理由にしてイジリ、苛烈なイジメをするようになっていく。
何もしていないのに悪役認定されるし悪口を言われる。ストレスを抱え、日に日に引きこもりがちになり暴飲暴食をして太ってしまった。
近所に住む幼馴染からは小学四年生の時に一方的に婚約契約指輪なる物を持たされたのに、落ちぶれた俺への対応はどんどん悪くなるばかり。
そろそろ指輪の返還を求められるかなと思っていた時に、彼女が国でトップの高校を受験すると言う。離ればなれにはなりたくないので彼女を追って俺もそこを受験すると、なんと受かってしまった。
しかしその学校でも最下位と馬鹿にされて嫌われる。ダンジョンに潜って強くなろうと足掻いてみたが、レベルが1のためにゴブリンにも殺されそうになる始末。
そんな時にたまたま通りかかった冒険者に命を救われ、鍛えられた俺は、レベルの壁を超え、スキルや魔法を習得して、妹と一緒に成り上がります。
―――――――
序盤は努力に関係なく、レベルが上がらないためにストレスがあるかもしれません。特にラノベのタブーで一般社会では普通の出来事「負ける」が序盤にはあります。主人公が負ける所が嫌な方もそこから抜け出すまでは読んでもらえたらと思います。
ハッピーエンドを目指しますので宜しくお願いします。1,242クル
カテゴリー内順位38位 / 9,194件
ジャンル内順位23位 / 4,451件




 (5)
(5)
タイトルAI診断値72tai
-
神猫ミーちゃん、船が好き ハードンブラコー♪ドンブラコー♪。川で流れる箱に飛び乗り良い気分 ハードンブラコー♪ドンブラコー♪。うたた寝してたら大きな川のど真ん中 ハーモットモダー♪モットモダー♪。たすけて~よ~とみ~み~鳴くけど届かない……アーラエライヤッチャエライヤッチャヨイヨイヨイヨイ!
浪人生の根路連太(ねじれんた)、通称ネロはそんな子猫を見つけちゃう。男気みせ、川にダイブし見事子猫を救出! でもこの人、猫アレルギー。
ずぶ濡れになりながらも子猫を連れて帰る事に、ここで猫アレルギー発動! 階段から落ちてあの世行き、さあ大変。
ミーちゃんの飼い主、神様です。ミーちゃんを助けてくれたので特別に、別の世界に転生できる事に。異世界に着くと、何故かミーちゃんバッグの中からこんにちわ。でも当分の間、神様の元に帰れなくなちゃった。神様慌ててネロに猫用品召喚のスキルを付けちゃいました。(本人承諾なし)
そんな神猫ミーちゃんと猫用品召喚師ネロのお話。スローライフを目指すも、そんな生易しい世界じゃない!? 頑張れネロ、ミーちゃんとのスローライフを目指すのだ!
神様が飼ってる猫→神猫
ツギクル様でも読めるようにする予定。1,186クル
カテゴリー内順位39位 / 9,194件
ジャンル内順位24位 / 4,451件




 (12)
(12)
タイトルAI診断値44tai
- 舞台
- 異世界
- 主人公の性別
- 男
- それ以外(人間以外を含む)
- 主人公の年齢
- 10代
- その他の要素
- 剣・魔法
- ほのぼの
- 現代知識
- ハッピーエンド
- 出版化
- 書籍化作品(予定含む)
-

何故、天使は怪物の姿をしているのか?
カーマン・ラインすら遥か突き抜けた巨塔──『天獄』と名付けられたダンジョンが存在する現代。
悪魔のチカラを宿す剣、すなわち『魔剣』を手にすることで、己の腕っぷし頼みに身を立てられるようになった時代。
若者の多くが『魔剣士』に憧れる中、特に興味も抱かず、胡散臭い雇い主の元で日々アルバイトに励んでいた胡蝶ジンヤ。
けれど皮肉にも、そんな彼はある日偶然魔剣を手に入れ、魔剣士の一人となる。
天獄の怪物たちを倒し、そのチカラを奪い取り、魔剣と自分自身を高めて行くジンヤ。
そうするうち、彼は少しずつ知って行くことになる。
自分の魔剣の異質さと──怪物たちが、天使の名を冠する理由を。
1,168クル
カテゴリー内順位40位 / 9,194件
ジャンル内順位25位 / 4,451件




 (1)
(1)
タイトルAI診断値36tai


