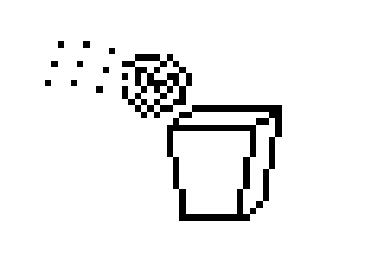1−4: トム・ガードナー
数十分後、交代要員のテリー・ジェラルドがやって来た。イルヴィンやトムより、いくらか若く見えた。
テリーはイルヴィンが座っている席に近付き、紙袋を捧げ持った。
「差し入れだけど」
そう言い、紙袋からトールのカップを持ち上げて見せた。
「コーヒー。ラテですけど」
「ありがとう」
そう応え、イルヴィンは受け取った。
「それで、ここでやることは……」
そこまで言うと、テリーが言葉を遮った。
「20万ユニットの状態の監視」
テリーは入口からは奥にある、10枚の大型ディスプレイを指差した。
「それと、ユニット交換の指示」
今度は二つのテーブルに置かれているディスプレイを指差した。
「それがわかっていればいいか」
イルヴィンは紙袋からカップを出し、一口飲んだ。
「ところでテリー、君はトム・ガードナーと親戚かなにかか?」
「あぁ、倒れたっていう人ですね。いえ、何もありませんよ?」
「いや、気にしないでくれ。それより仕事を始めよう」
イルヴィンが、トムが使っていた席を指差すとテリーはそこに腰を下ろし、早速手前のディスプレイと大型ディスプレイに交互に目をやった。
20万ユニットの状態表示は、ブルー、グリーン、イエローの間を行き来している。まれにオレンジになることもあるが、およそすぐにイエロー以下の状態に戻った。
* * * *
退勤時間になり、イルヴィンとテリーは部屋から出て、ロビーへと向かった。そこで次の班の二人とすれ違い、簡単な挨拶をした。
イルヴィンはロビーにあるカウンターの前で立ち止まり、内線を手に取った。
「サービスセンター・アシスタントです。ご用件をどうぞ」
「監視員イルヴィン・フェイガン。トム・ガードナーが運ばれた病院を知りたい」
「トム・ガードナーは、一旦市立病院に搬送されましたが、そこからすぐにHUMANLY INTELLIGENCE本社運営の病院へと移送されました」
「本社運営の? それは隣の州なんじゃないのか?」
「はい」
その答えはイルヴィンにとって予想外のものだった。トムは近くの病院で休んでいるのだろうと思っていた。
「トムの容態は?」
「現在、依然として昏睡とのデータがあります」
トムが倒れた理由には、トムから聞いている限りにおいて、イルヴィンに思いあたるものはなかった。それなのに、移送され、昏睡が続いているというのはどういうことなのだろうかと思った。
「トムの健康状態について、つまりトムは何か既往症があったり、それとも今も何か病気があったのか?」
数秒の沈黙があった。
「そのような記録はありません」
「つまり、原因不明で、依然意識不明なのか?」
「はい」
どういうことなのかとイルヴィンは思った。
「ありがとう」
イルヴィンは内線を切った。
「トムのことが気になるのか?」
横からテリーの声が聞こえた。
「目の前で倒れられればな。君も気になって、ここに残っていたんだろ?」
「まぁ、ね」
そこでテリーは左右に目をやった。
「聞いたことはあるかな」
「何を?」
イルヴィンもつられて左右に目をやった。だが、交代の人員は既に通り過ぎており、ロビーには他には誰もいなかった。
「つまりさ、サロゲートの話…… あと、知能サービスの話……」
イルヴィンはテリーの目を凝視めた。
「本気でそんなことを考えているのか?」
「本気ってほどじゃぁないけどな。ユニット交換中にトムは倒れた。そして、原因不明の昏睡だ」
テリーは肩をすくめて答えた。
「だからって、そんな都市伝説を持ち出さなくてもいいだろう?」
「それならもう一つ」
テリーは右手の人差し指を立てた。
「トムはどうして本社運営の病院に連れて行かれたんだ? 州を超えてまで。 原因不明の昏睡ってのは問題だろうけど。市立病院じゃまずいのか?」
イルヴィンは、テリーの右手に手を当て、脇にまで押し下げた。
「そういう陰謀論めいた話には、あまり興味はないな」
イルヴィンは左手を腰に当て、右手を顎に当てた。
「テリー、君が都市伝説や陰謀論を好きだろうと、それはかまわない。だがな、トムが入院したなんてことを、その根拠のように言い触らすんじゃないぞ」
「あぁ、いいかなイルヴィン」
テリーはまた右手の人差し指を立てた。
「君は、自分自身の感覚や、知能サービスの実現に疑問を持つことはないのかな」
「ないね」
イルヴィンは横に首を振った。
「じゃぁ、ここにある ”R&D” ってのは?」
「知らないな。俺たちの仕事には関係ないことだ」
「関係ない? 本当にそう思っているのか?」
あらためてそう言われると、イルヴィンは言葉に詰まった。
「ユニットはどこから来ているんだ? ユニットの中身は何だ? 俺たちはボタンを押すだけだ。何を知っているって言うんだ?」
やはりイルヴィンにははっきりとしたことは答えられなかった。
「知る必要はないだろう。俺たちの管轄外の話だ。気にしてどうする? あまりそっちを気にするようなら、監視員として不適切だとレポートを上げるぞ」
「好きにすればいいさ。だけどな、俺は動画を持っているんだ。廃棄ユニットを分解する時のな」
イルヴィンは玄関に体を向け、歩き始めた。
「そういうのは知ってるよ。ネットで拾ったんだろ? その手のは趣味にしておくんだな」
右手を挙げ、振り、イルヴィンは玄関から出て行った。