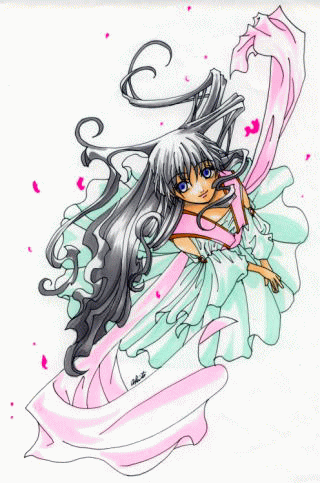第86話 ゆったりと時間ばかり流れ
誠達が捜査と言う名の散歩をはじめてから一週間の時間が流れた。いつの間にか世間は師走の時期に入り、地球と同じ周期で遼州太陽の周りを回っている遼州北半球の東和も寒さが厳しい季節に入った。
ランが指定した建物の調査と言う名目で訪問した現場は100を超えたが、誠もカウラも法術研究などをしているような施設にめぐり合うことは無かった。
そもそも調査した建物の半分が廃墟と言ったほうが正確な建物だった。5年前の東都中央大地震の影響で危険度が高まり放置された廃墟の内部構造の様子と生活臭がありそうなごみの山を端末で画像に収めながら歩き回るのが仕事だった。
その日もいつものように液状化で傾いたため放棄された病院の跡地の調査を終えて、車に戻った誠にカウラがマックスコーヒーを投げた。熱いコーヒーを手袋をした手で握りその温度を手に感じた。
「ありがとうございます」
そう言うと誠はマックスコーヒーのプルタブを開けた。
「やはりここも外れだな。予想通りと言うべきか」
寒さにも関わらず冷たいメロンソーダを飲んでいるカウラのエメラルドグリーンのポニーテールを眺めていた誠に自然と笑みが浮かんだ。
「何か良いことでもあったのか?それとも私の顔に何かついているのか?」
ぶっきらぼうに答えるカウラの視線につい恥ずかしくなって誠は視線を缶に向けた。
「それにしても島田先輩達は何をしているんでしょうね。あの人達は役所周りでしょ?この寒い中廃ビルばかりを回ってる僕達に比べて暖房の聞いたお役所の建物の中で調査なんて、不公平ですよ。まあ、茜さんは相変わらず厚生局と交渉中で一切その交渉も進展していないみたいで……所詮僕達にできることなんてこれくらいなんですね」
ランとかなめが志村三郎を追っていることは知っていた。三郎はあの日以来父の経営するうどん屋にも自分の事務所にも立ち寄らず姿を消していた。一方、茜が仕切る別働部隊は茜がひたすら捜査への協力を拒む厚生局への協力依頼の交渉を続ける傍ら、アメリアを中心としたチームが厚生局が白だった場合に備えて主に研究機関の支援をしている可能性のある政府機関を当たっているが、どちらも芳しい結果は得られていないということしか誠は知らなかった。
「言うな。アメリアにつれられての官庁めぐりにもそれなりの苦労と言うものが有るに違いないんだ。むしろ下手な小役人のご機嫌を取ったり、袖の下を要求されたりしない分だけ楽と考えることもできる……まあアメリアの方も収穫は何も無いようだが」
実際官庁めぐりを続けるアメリア達の他に、本部にはネットの海の狩を得意とする技術部の士官達もあちこちのサーバーを片っ端からチェックして大きな動きが無いかをチェックしているのも知っていた。だが、誠があの法術実験の失敗作とされて廃棄された不死人を斬ったその日から、ネット上にも法術の違法研究を示すような情報は見つからないらしかった。
「誰が最初に当たりを引くかですね。研究は確実に行われていて、その施設はこの東和に確実に存在している。いきなり消え去ったりすることは無いですから。いつか行き当たりますよ。特に厚生局。ここまで協力を拒むには相当深い理由があるんですよ。いくら東和が憎いからって遼北が国ごと敵に回るなんてことは無いと思いますよ。あそこも一応は同盟加盟国ですし、同盟崩壊なんて自体はあの国も避けたいでしょうから」
何気なく言った誠の一言にカウラが頷いた。海からの強い風が車の冷えたボディーに寄りかかっていた二人をあおった。
「やはり、少し寒いな。中で飲もう」
そう言うとカウラは運転席のドアを開けた。誠も助手席に座って半分以上残っている暖かいコーヒーを味わうことにした。
「でもどこが研究してたとしてもこんな研究の成果を誰が買うんでしょうね……今のところ不完全な法術師しか作れないんでしょ?かなめさんならどこかの軍と言うでしょうけど、軍と取引できるとなると役所でも限られてきますよ……ってここでも厚生局が怪しいってことになる。本国に技術を持ちかえればそれなりの評価をしてくれるでしょうからね。本当にあそこが?でもどこで研究を?研究所のしっぽぐらいは見せてくれてもいいのに」
その言葉に冷めた表情で同じ事を言うなと言っているように誠を見つめるカウラがいた。
「これまで見つかったのはすべて失敗作だと考えるべきだな。神前程度の覚醒をしているのであれば我々がそいつを見逃すわけが無い。自爆テロ以上のことができるならどこの軍でも欲しがるさ。もし、その技術が完成に近づいていて売り手を探し始めれば、当然売り手を求めている連中の動きが技術部の士官や安城少佐の公安のネットワークに引っかかるはずだ。それに人工的に法術師を作れないとしても既存の法術師を覚醒させる技術を所持していると言うことを内外に示せればそれなりの技術力の誇示はできるだろ?数百年前の核ミサイルと同じことだ」
カウラの言葉にも誠は納得できなかった。法術の発動が脳に与える負荷については司法局実働部隊の法術関連システムの管理を担当している看護師の神前ひよこ軍曹から多くのことを聞かされていた。
『急激な法術の展開を繰り返せば理性が吹き飛んでしまいます。そうなればもう誰もとめることができないんです』
法術の専門家である医療班の神前ひよこ軍曹の受け売りの言葉を誠はつぶやいていた。だが彼の前には感情を殺した表情のカウラの姿があった。
「その時はこれまでどおり自爆要員として使う。それにいったんノウハウを把握できれば再生産が可能なのは私達『ラスト・バタリオン』の製造で分かっていることだ。東和はラスト・バタリオンの製造プラントを引き取った国だ。そのノウハウはおそらく今後の人造法術師の量産に生かすつもりだろう」
そう言うとカウラはメロンソーダを飲み干してその缶を握りつぶした。そこには自らの運命に対する呪いと、その技術が別の悲劇的な運命を作り出すことに対する怒りを見ることが出来た。