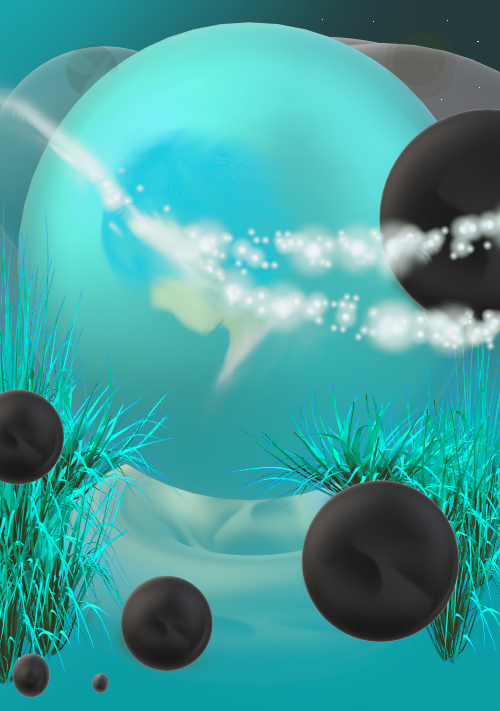魂呼び子.8
ザザッと。
閉ざしたまぶたの内側を占めた闇——それが瞬時に走りさったような感覚があった。
次に水が満たされているような空間に、ぼやけた影が見えてくる。
ふさふさして流れるようなもの……
髪…?
…いや。もっと、ひろい範囲……
身体から生えた毛? 体毛のようだった。
観察するなかに、それが
白と茶、そして赤茶……背筋にそって密集する長い……髪を思わせる毛皮?
(…なんだ? 獣? …——)
色のない地表をとらえている腕の先端。
皮が厚そうな手の甲…つけねのあたりから……内にあるものを庇うように二枚。
あるいは三枚、四枚……
鋭いかぎ状のものがはえていた。
骨のような材質にも見えるが、装甲過剰な籠手のごとく手首の甲側から段階的に突きだし、鋭くも肉厚で先細りの
それは奇形の骨……いや、骨というよりは、やはり
その内側。
茶色の被毛で
その部分部分には、赤黒い生きものの液体がふちゃくして、じっとりと。したたり落ちないばかりに
右手と両足を地面について
白くて繊細そうなつま先と……かかと。
下肢にまとわりついている水色のナイトガウンには大量の血痕。
噛まれたのか、裂かれたのか。
血液が、ひとすじ、ふたすじ……くだりおりている繊細なあごの輪郭。その喉もとを横切り、見えなくなっている黒い頭髪の束。
(…どこかと似て否なる
いっぽうの体毛豊かな獣は――彼、セレグレーシュが、いま、初めて出会ったもの。
あきらかに初対面だったが…。
その
(…もしかして彼女が、メル…——?)
ぴくっと、
実際に動いたわけでもないのに動いたような錯覚……彼女の黒い睫毛が震え、
(だめだ。これは……いま呼んだら…——)
セレグレーシュの注意が、その子の右肘をくわえている獣に向けられた。
毛むくじゃらの生きもの。
筋骨たくましい人に長いのや短い毛を密集させたらそんな容貌になりそうなもの。
ただ骨格に獣と人間が混ざりあったような不自然な曲がり、拡がりがあり、
尾かも毛の束かも判らなくなる量のたてがみが、過剰に伸びた毛髪のごとくおりて地面に横たわり、うねっている。
部分部分にみとめられる鋭利な
熊でも、大狼でも、大猿でもなく――。
二本の足で自立して、外見は霊長目。ヒト科のようであるのだが、不活性ながら異常なまでに混濁した魔性――人には読み解けぬよどみを帯びている。
この地において、自然に成りたった生きものの系譜とは思えないおどろおどろしさを連れている。
毛深い頬と口元を汚している赤い汚れ――血痕。
少女の上腕に食いこんでいる獣の証明のようにも思える
眼球に白い部分のない無垢な瞳をした、孤独な存在……。
泣いている…――涙を流せぬままに……。
それにも名前がある。
(…呼び…づらい…——)
🌐🌐🌐
早朝の冴え冴えとした陽光のもと。
さながら地面や空間を割って
白と茶色と赤茶の、ゆたかな毛なみ。
そのすきまから、ぎらついて見えた奥の深い緑色の双眸が、周囲にいた人間を映し――
威嚇とも
〝その獣人《彼》〟の……わずかに
閉じられた時――
その生きものは、ひたりと。彫像のように硬直して動かなくなった。
五歩もないところに見たもの。
瞬間的に不動の境地に
「どうして、こいつがっ…?」
その声の下方――。
どさっと地面に落とされたセレグレーシュが、その衝撃に、うっすらと
草地に頬をあずけ、つかの間、うつろな表情も見せた彼だが、そうして開いた瞳の焦点が定まるとともに、
さして遠くないところに毛むくじゃらの生物が立っている。
そう認識したことで、失態を自覚したのだ。
手応えはあやふやでも、その存在の名を呼んだ記憶があった。
呼ぶつもりなど、なかった。なのに……。
どうして呼んでしまったのか――一時的にわからなくなる。
いずれにせよ…。
いま彼は、法印の中にあるその種も
自分がそれをどこからひっぱり出したのか。取りあげたのか…。
やたら生々しい確信、自己認識があって、
知らぬ存ぜぬで、済ませられる精神状態でも、状況でもなかった。