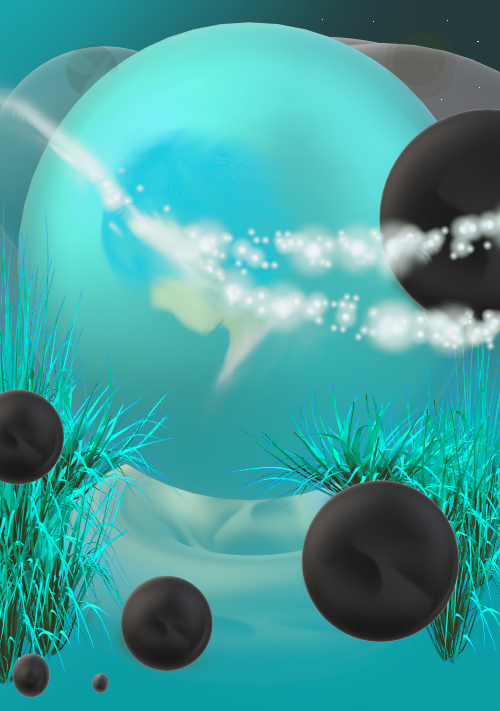魂呼び子.1
約束の二十日。起床時刻。
昇りかけの太陽が
その誘いは、《
《
アントイーヴが手ぶらに見える
人工的な隆起が大地になじみとけ合う平地の
放牧場において《
はるか遠方に確認できる森がはじまるまでは、きまぐれにちらばる《
いま彼がいる、どこまでが敷地と認識されているのかも不明なそのあたりに、始まりが唐突なら、終わるのも突然な
支えつきのその格子杭…――ただ地面に
あたりを見まわせば遠くや近くで中途半端な装備――鞍は外されているが、いくつか装飾的な法具を着けたまま――の馬をはじめ、
「…。ひとりかい?」
「うん」
確認の声をかけたアントイーヴの視線があたりを泳ぐ。
「彼は?」
「彼って?」
「このっくらいの背丈の癖っ毛の
「…。今日は見てないよ」
「頼まなかったのかい?」
問われたセレグレーシュの口もとに、胸のうちの不平が
「協力しろって? 君が頼んだんじゃないの? オレは知らないよ」
「そう…。じゃぁ、協力を依頼して喧嘩になったわけでもないんだね」
「ケンカ?」
「噂になってるよ。君と彼が喧嘩してるみたいだって。違うのかい?」
「まともに会話も成立しないのに。喧嘩になんか、ならないだろ。
最近は、あまり
「そうなのかい? でもそれは、喧嘩しているからじゃ――…」
「違うよ」
セレグレーシュは、アントイーヴがしゃべり終えるまえにその指摘を否定し、心理的にも拒絶した。
「そうだとしたら、あっちが勝手に怒ってるんだ。もともと親しかったわけじゃない。考査の時、口きいたのが……初めなんだ。
オレ…。あいつのことは、よくわからないよ」
アントイーヴは「そうか…」と応じて、そっと息をはいた。
「じゃぁ行こうか。あまり遅くなると恐いしね」
なにが恐いのだろうと不審に思いながらも、セレグレーシュは、それを追求しなかった。違う疑問を口にする。
「あの闇…――
「プルーなら先に行ってると思うよ。確かめたわけじゃないけど、たぶん現場にいる。
実は今朝
危うく、ぼくの部屋が暖炉になるところだったんだ。
自在に消せるから上掛けに火を
かなり尋常ではないことを耳にしたセレグレーシュは、とっさには認識が追いつかなくて目をぱちくりした。
なにも、相手の発言を疑ったわけではないのだが…――。
彼が生まれた土地で、闇人・妖威といえば、人間にとって、勝手気ままな支配者や神出鬼没な隣人、または天敵のような存在だった。
やたらに出遭うものでもなかったが、それは遭遇してしまったら逆らえなどしない〝触らぬ神に……〟的に語られる部類なのだ。
そういったものが友人として生活空間に入ってくれば、いま耳にしたようなことも起こるのかもしれない。
その人が体験した事を想像するのは、さして難しくなかったが、そんな状況に自分を置きかえてみると、そら恐ろしい気もした。
それを呼びこむ
それはそれとして。
セレグレーシュには、そのへんもわからない。
問いただせば交流がないというようなことを口にされるが、このあたりの闇人と一般の人間のあいだには、不可侵めいた距離がある。
その種との
一度なりとも、闇人が人に力を貸したという事実は重い。
アントイーヴから依頼することに不都合があるのかもしれない…――そんなふうに、やぶ睨みすることもできるが、ここぞというところで橋渡しを提起されるので、自分が動かなければならないような気にもなってくる。
訳あって名前に重きをおくその種に、省略形であれ、
そうおうに、その闇人の関心を得ている自覚はあるのだ。
現実を見れば、未熟な自分がついて行ってもたいした助けにはならない。せいぜいが荷物持ち・会話相手ていどだ。
にもかかわらず協力を求められている。
アントイーヴの意図・狙いは明らかだ。
はじめから仲介するよう、彼に働きかけてきたのだから。
だが、セレグレーシュとしては、とうぶんのあいだ、例の少年と距離を置きたいのだ。
考えるほどに迷いも疑問も、それに抵抗も深くなる――こんな、うやむやな状況で姿を消してしまわれても困るが、あまりかまわれたくないし、ちょっかいを出したくもない。
名前を聞いてさえ、ふっきれない。
そのものに思えてしまう声ばかりではなく…。ヴェルダが人間だったら、ありえない外見の若さ……年格好だというのに、闇人だった可能性が
その声を耳にするまでは、そんなことなど
やはり自分は、その彼をヴェルダだと思いたいのかもしれない。
特別だった友人が、そばにいないから…――その
不本意にも混乱してしまうのだ。