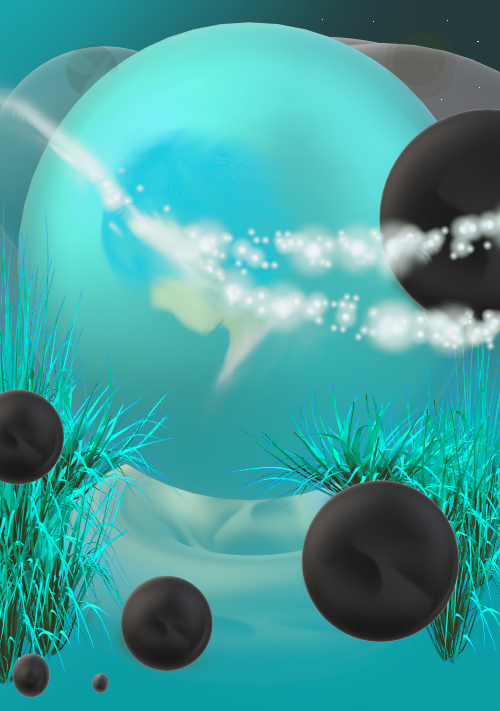魔神招来.3
…その時――…
大地を震わせたのは…――
〔…ぅ…ぁぁあー…——〕
咆哮…悲鳴……高笑い——どれともいい
〔…ぁあぁぁあああぁぁ……はぁっはははあぁ……ぁあああ——…〕
声とも
右耳を手のひらでおおい、かばいながら顔をあげる。
彼が本能的に避けようとしたそのあたりに、おおいかぶさってくるような錯覚をもたらす
人影のようだったが……。
「……あ?」
木々をなぎ倒しかねない大音響。
〔——ぉううう……〕
出どころは、すぐそばで仁王立ちしているそいつのようだった。
(やば……、なんか出た…!)
安全が約束されているような暮らしの中でいくらか鈍ったのだとしても、近づく存在の気配には、ほどほど過敏な彼である。
深い眠りに落ちていたとしても、こんなに騒々しいものが、そばにいたのに気づかないなどということは考えにくい。
他に気をとられて、うっかりしていることがないとはいわないが、あまりにもいきなりすぎた。
そんな中に。それと受けとめながら順序だてて考えたわけではなかったが、直感めいた思いつきもあった。
(——いや…。オレが……呼んだ?)
ゾッとするような予感にすっかり目がさめてしまったセレグレーシュは、しばしばして、しっくりこない目元をこすりながら、それがいる側と逆の方――左へと腰を浮かした。
(いや……違う! 呼んでない…。そうだ。……
人影を視界の端においたまま、そばに落ちていたクリップボードを手に後ずさりする。
そこにいるのは贅肉をすべて削りおとしたような痩躯の男だ。
汚れ、のびほうだいにひろがって空を泳ぎ、ふわりと肩におりたりもする灰色っぽい髪。
夜半。
月のない星闇のもとにあって、影になった眼窩には眼球があるのかないのかさえうかがえない。
だが、そこにたたずむ存在の印象・気配には、ついさっきまで夢うつつに見ていた眠れる人と共通するものがあった。
白銀の光があふれるところにいたもの。
闇人を招いた時、ときおり記憶にのこっている濃密な闇からではなかったけれども、やはり、どこかから、ひっぱりだしたのかも知れないのだった。
そうだとしても、いつもとはかなり勝手が違っていたが……。
性質がどうあれ。ひきだした闇人は、たいてい状況を把握できずに茫然としたり、とまどったりする。
即座に現実を受けいれ、理解して行動をおこすものがないわけではないが……これは、さながら……破壊能動性の強い妖威にでも、でくわしたかのような…——
「お…、オレ……(魔神…妖威なんて……。ひっぱりだしたことなんて…)——」
あわてて探した荷物が、シートのあるあたりに放置されている。
駆けだしざまに、かさばるリュックをひろいあげた彼は、そうして近くに見た大木の陰に、こそっとまわりこもうとしたのだが……。直感的にひるんだ。
すーっと。流れてきた風圧の先ぶれ。微風が掠めたような違和感に、先に進むことをためらいをおぼえ、一歩、大きく後ろへ
ともなく、
そのあたりの木々が、ぎしりっ、めきめき…っと、いっせいに軋みだし、おなじ方向へたわんで
いっときは頼ろうとした目前の大木が、根をムチのように震わせながら横転し、根元からはじかれた土が、ばらばらと、つぶてとなって彼をみまう。
濃厚な香をはなつ湿った土くれが、べしべしと。強風にあおられながら、ぶつかってきて、避けたくても避けられるようなものではなかった。
瞬間的な圧力か? それとも突風か? 定かではなかったが……。
うかがい見れば、その方面の木々がかなりのところまで、一方向へ向かって折れたり横倒しになったりしていた。
旺盛な緑を左右に残したまま、生じた暗い溝。
地が削られたわけではなくても、その方向にあった植物があらかた倒れ伏したので、はたからは、その部分が、するどく
セレグレーシュがいるのは、そのはじまりのあたりだ。
直前の一歩か二歩が、生死をわけた気もするこの状況。
危機一髪だったが……。
多いか少ないか不明な中にも、妖威が気まぐれに徘徊するといわれる地に育ち、放浪した経験もある彼は、その程度のことで行動を見失うほどやわな精神の持ち主ではなかった。
土が入ってしまった左目を抑えながら、リュックを片手、わき目もふらず走り出している。
さいわい、これと目をつけられていないようでもあり…――標的とされていたら、おそらく…、今頃、命はなかったのだと。
そう、思えた。
なおかつ、自分はまだ生きている。
だいじょうぶでケガもしていない……
考えるまでもなく彼の身体は知っていた。
木が倒れた方面を避けて、自然そのままに生え競う木立の隙間をさぐりながら駆けぬけてゆく。
すべてをなぎ倒すような怪異にまき込まれるかどうかは、このさいは賭けだった。
そこに妖威とおぼしき人影がある以上、隠れられるところもない苔の原っぱが安全とはいえない。
だから彼は、とにかく影響力が及ばないところまで離れようと。
目をつけられてしまう前に、その場から遠ざかろうとしたのだ。