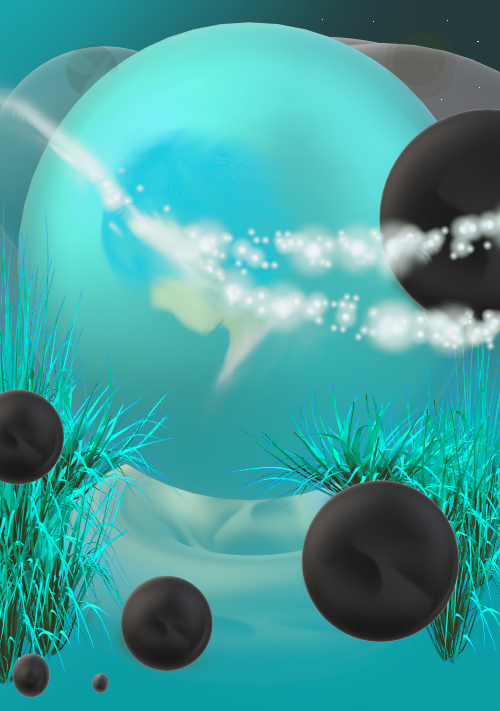稜威祇の少年.3
——…。
木々がわずかな空間を
簡素に固めただけの小さなもり土。
かき集められた土に混ざりこんでいる青葉は、みずみずしさをいくらか残しており、まだ雑草が芽ぶくけはいもない。
そんな小山のてっぺんには、微妙にゆがみをおびた取っ手つきの銀色の円盤がのっていた。
大陸を分断する内海からこちら側。いまいる場所からみれば、南かげんの東。
ルス・カの里には、墓を掘るさいに使った道具を故人にたむける習慣があった。
使用した道具を忌むいっぽうで、埋められた場所が気にいらないときは、埋められた者自身が新たな
死者が動くはずはないのに、そこに
墓造りに利用した道具を墓標としてその場に残して行くという、その里独特の風習。それに関わった者の
「ぁあ、鍋のフタだね…」
追いついてきて、彼のとなりに並んだアントイーヴが足を止めるともなく告げた。
「珍しいものではないね。最近、家で生徒に配布しているものと同じようだけど――彼のなのかい?」
「なにか
「…。先を急ぐぞ」
くるりと身体の向きを変えて、道へとひき返してゆく。
(さびた金属……いや違うな。これは血臭…――?)
アントイーヴは、なにが埋まっているとも知れない痕跡を前に頭をひねっていたが、早々に見切りをつけ、
「鉄さび……血、みたいな匂いがしたね。確認しなかったけど、あれが彼の墓標ということはな…――」
「それはない」
即答した後で、ふと眉を寄せた少年
「それは、あの女があれの命を狙っているということか?」
こころなしかその口調が威嚇的だったが、アントイーヴは、さして緊張することもなく応じた。
「そこまでじゃないと思うよ。いろいろと言い分が……。話したいことが、あるんだろうとは思うけどね」
そこで
(……。…たしかに、あの女のようすには
🌐🌐🌐
ふたたび馬上の人となったふたりは、踏み固められた土の道を進みはじめる。
アントイーヴの後ろにいる少年の身体の向きが左に変わったことをのぞけば、道草をくったこともなかったように。
「野宿したのかな。……まぁ、さほど郊外でもないし、
そこでいったん言葉を切ったアントイーヴは、背後にいる少年の反応を意識しながら告げた。
「彼らを見つけても、ぼくは声をかけないけど、いいかな? 気づかれないように行動を見守るつもりなんだ」
「われはしばらく動かない。好きにするといい」
「……回復の構成、築こうか?」
「不要」
機嫌でも悪いのか、そくざに返された言葉には攻撃的な響きがあった。
そこでアントイーヴは、そっと
協力してもらえそうな
その少年は、弱っている事実を認める気がないらしい。
「マゾの
「
「無口というわけでもなさそうだね。セレシュ君が、そんなに信頼に足る人間だというなら、ぼくも友人の列にくわえてもらおうかな。彼の噂なら、いろいろと聴いている。どんなやつなんだろうと思っていた」
おなじ組織に属する、人間と人間——おなじ種。
セレグレーシュは、彼が笑いかけると奇怪なものを見たような顔をして無視する。
その少年らしい反応で、そうなることを予測して、あえてそうゆう対応を選択し続けている彼だが、否定的なその態度になにも感じていないわけではないのだ。
――…オレ、闇人なんか嫌いだ……
それはかつて、彼が耳にしたその少年。セレグレーシュの言葉。
誰よりも、そう呼ばれる種を……その者達を理解していた気がする人物は、もうこの世にはなく……
その存在そのもののようにも思える少年は、闇人と呼ばれる
その子が育った環境を思えば、人間嫌いになる方がまだしも自然な気がするのに……。
(…――われと
――闇人。
複数の色彩を瞳に秘めたその少年は、おのれ自身と、その少年の内に認められる数ある矛盾を…――盲点の少なくない互いの事情が織りなす不透明な実情を把握しきれぬまま……。
さして意味もないありがちな事実、現象として、シニカルに受けとめていた。