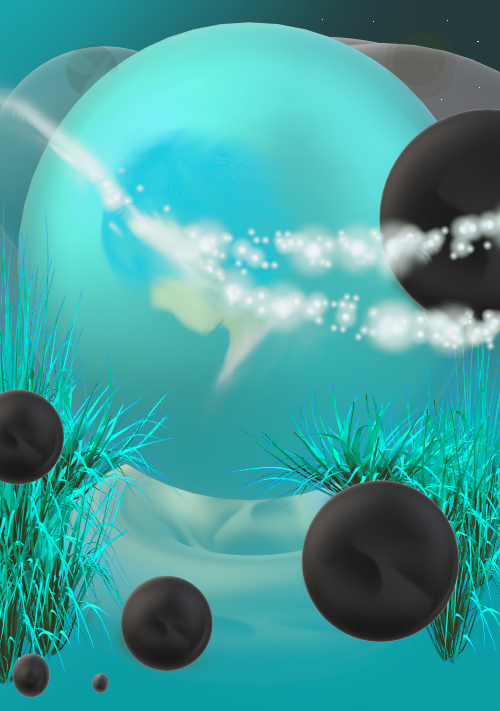法の家.0
ちゃんとした衣類など持っていなくて……。
いつ身につけたのかも覚えていない大きめのシャツは、
冷たい草地に転がって、うとうとしていた少年をびくつかせたのは、なにか生きものが近づいてくる気配。
そこに現れたのは、ほどなく十を数えようとしている彼より頭ひとつ半あまりも
成人にはまだ遠い中途半端な体つきのその子は、暗がりの中、いささかの迷いも見せることなく彼のもとに歩みよると、湯気がたちのぼる
心もとなげに手を伸ばした彼が、おずおずと器を受けとる。
するとその人物は自身が身につけていた
「大丈夫。悪いものは入ってない」
知らなかったのに、ほんとは知っているような……。
いつかどこかで見かけたことがあるような気もする
そう。
覚えていた。
それは彼を助けてくれた少年だ。
炎がせまりくる熱気の中、彼を
目が
きっと、こわい人ではない。
彼より背が高くて、おとなに見えるから、二つ三つ年上……いや、とても
あたたかいスープと
このあたりの人間にとって衣類や食物は命をささえる貴重な富・価値ある物資だ。
助けてくれたし、食べ物をくれた。
ほわほわの
いま自分の目の前に
おなかが
夢中になって、
そして、がぶりと。自分の口より大きな
「西の
闇の中。届いた声に顔をあげると、目をだす状態で顔の下半分ほどを布地でおおっている相手の白い横顔があった。
その視線はあらぬ前方に向けられていて、彼を映してはいない。
「力だけじゃなく、法がものをいう土地がある」
「ほうがものいう?」
「一部の人間と闇人が協定を結び——
目をまんまるにした彼が、よくわからないような顔をしていると、その少年は少しばかり思案するようなしぐさをみせた。
ちらと彼の方を見て、言葉を
「人と闇人が土地を分けあって暮らしている」
「……わけて、いっしょに?」
「トラブルがまったくないわけではないが、闇人が無闇に人を威圧……支配…。
「ほんとうか?」
「西に行ってみないか?」
「それ。おれが行こうとしてたのと
「…――気をつけなければならないことが、幾つかある…」
ここは、そう
ちょっとした異常にも過敏な防衛反応をみせるようになる。
彼は、そんな人間の里からはじかれた子供だった。
いまは頭も眉も、つるつるにそっていて、そんなに目立たない――けれども純粋な人間にはありえない色彩を持っていたので……。
父を亡くし母に捨てられた彼は、ほかに頼れるものもなく野をさまようしかなかった。
「西には
「それって、どっち? なぁ、ここからは、どっち? おれ、(夜だし、いま自分が)どこにいるのかわからないんだ。どうやったらそこに行ける?」
興奮した彼に発言を
「セレグ。《法の家》に行かないか?」
「ほうの家?」
「うん。壁が淡い紅色……
「……。おまえは、そこに行くのか?」
「う……ん? ぼくは……」
覆面の少年は彼を映していた瞳を、すっと水平にそらした。
その裏を感じさせるしぐさにどんな意味があったのか…――あたりは暗い闇に沈んでいて……。
「おれ、
「町というわけじゃ…――いや、みたいなものか」
覆面の少年は語尾を
「おおまかには太陽が沈む方角を目指せば、どうにかなる」
「太陽がおちるほうか。じゃぁやっぱ、朝にならないと(わからないな)……。そっちって道あるの? (森は獣もあやかしも出る。でこぼこで、ぼうぼうで……迷いそうだ。食べ物もない……)。おれ、行けるかなぁ…?」
「セレグ。《法の家》も西にあるんだ」
「それって、町とか人の里とちがうの? だれかの家? ……とおい(の)?」
「規模はそれなりだから集落ともいえるかもしれない。君が知ってる人里より、はるかに大きい。広いが……。親がいない子供も受けいれ、住ませてくれる。生きる
「おまえも、ひとりなのか?」
「ぁあ、…うん。そうだな……」
「……。いっしょに行くか?」
相手に対する気後れ、ためらいもあったが、そこに芽生えた期待を秘めきれずに誘ってみる。
すると、少しのあいだ、まっすぐなまなざしを注がれたので、彼も見つめかえした。
先に視線を外したのは、布を顔に巻いている少年の方だった。
「いや。止めておくよ」
「つまんねぇの…」
「君を見失わないくらい…――そばには、いるから。じゃぁ、また…。……」
あわただしく立ちあがった少年の
月の光が通りぬける小さな穴がたくさんあったから、
身につける種類の装飾品としては大きすぎて、邪魔になりそうな金属……または陶器のようでもある腹太の楕円形。
穴だらけなので液体を入れておくものではないのだろう。
その
目につく細工を腰の横につるした少年は、もうふり返ることもなく行ってしまったので……、
彼はまた、ひとりになった。
いちど足を立ててから、もとのように座り直した彼は、たった一人の味方がのこしていった外套をぎゅっと身体にまきつけた。
「…きっと、父さんがいるんだな……。…」
ぽつりと思ったことが言葉になった。
頼れるのは父親で、母親は何をするかわからない――そんな固定観念が、いまの彼にはあった。
自分は髪の色が変だし、変わった
それでも、あの少年は『また』と言った。
『そばにいる』と。
だから、あの少年なら信じていい――そんなふうに思えた。
(西のほうにも町があるのか……。東のほうにあるのと、あの里だけだと思ってた。知らなかった。人と闇人がなかよくできるのは、すごくいいな…。……)
幸福な気分であれこれ思案していた彼は、
それは彼が
彼が育った土地では、死がひどく身近にあって……。暗闇のなかで、ひとりになることよりも恐いこと、危険と思うようなことがいくつも存在した。
なにがひそむかも知れない闇だが、その
彼を襲うものを隠していないかぎり、それは、なによりも心強い味方だったのだ。