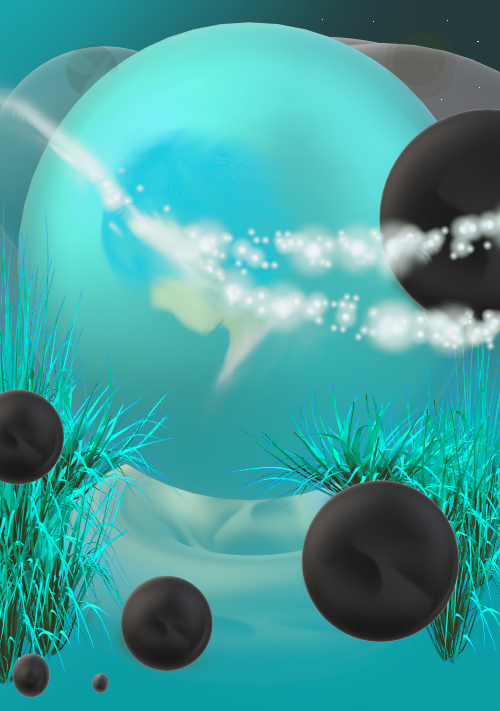第二十三話
「もう、もう、もうこれしかありませんわ!コチョコチョ。チョコチョコ。」
大悟は左右の手で、ふたりをくすぐりする。
「「や、やめて~バタン!」」
ふたりは白眼を剥いて、前のめりに倒れてそのまま動きを停止した。
「やっと終わりましたわ。くすぐりの腕がまた上がりましたわ。マッサージ師の家元の伝統の力なのかしら?わかりませんわ。」
翌日の日中はいつものようにフードを被っていた衣好花。それを見て、図らずもホッとする大悟であった。
そして放課後。神頼みエントリーが終わっているので、大悟と楡浬は社の外で待っている。
「今日も待たせるわね。神様を軽んじるにも程があるわ。やってきたらとことん、御幣に血潮を吸わせてやるわよ。ひひひ。」
「とても神様のお言葉とは思えないですわ。もっと女神らしく穏やかに行きましょう。ほら、こんな風に。」
大悟は軽やかにターンして、制服のスカートを翻す。どこから見ても清楚な女子高生に見える。」
「馬嫁下女はどこの誰よりも女の子してるわね。」
「そんなことないですわよ。オレはどこまでも男子中の男子ですわ。ほら、この自慢の胸を見てほしいですわ。」
大悟は堂々たる胸部をこれみよがしに強調した。楡浬はそれを一瞥して、眉間に皺を寄せて視線をそらした。
「どうしたのかしらこの回避不能な敗北感。根っこからの女子化が心まで浸食しているようにみえるけど。」
「う・・・。オレは、いったい誰なんですの~?」
「ひどく悔しいけど、ただの馬嫁下女よ。」
巨乳という同一事象を異なる観点で意気消沈したふたりに、追い打ちをかけるように、雨が降り出した。
遠目に誰かがやってくる。雨の日にわざわざこの小神社にやってくる人は限られている。
大悟が目を凝らしている。
「あれは衣好花ですわ。ワンピース、それも黄色の水玉模様の女の子らしい華やかなものに見えますわ。ちゃんと昨日申し上げたことを守ってくれているようですわ。」
「今更だけど、その喋り方、嫌なヤツを思い出して、キモイわ。」
「キモイなんて、俗語を使うのは、よろしくありませんことよ。」
そうこうしているうちに、衣好花がやってきた。
「あれ?衣好花さん。遠目で見て、実に女の子らしい黄色の水玉模様のワンピかと思ったら、オレの指示と全然違うじゃありませんの。」
「拙者は忍者の家系ゆえ、貴殿の所望された、か、か、かわいい服を所有してござらん。無念の字。」
衣好花は、はらはらと落涙した。衣好花が着ているのは黄色水玉模様に汚れた作業用つなぎであった。フードで表情は見えないものの、美少女が泣く姿には心打たれるものがある。
「あらあら、かわいい顔をぐしゃぐしゃにして。乙女がそんな顔をしちゃ、台無しですわ。ほら、顔をお上げなさい。」
大悟は衣好花のフードを取り上げた。途端に衣好花の表情が一変し、口元が猥雑につり上がった。