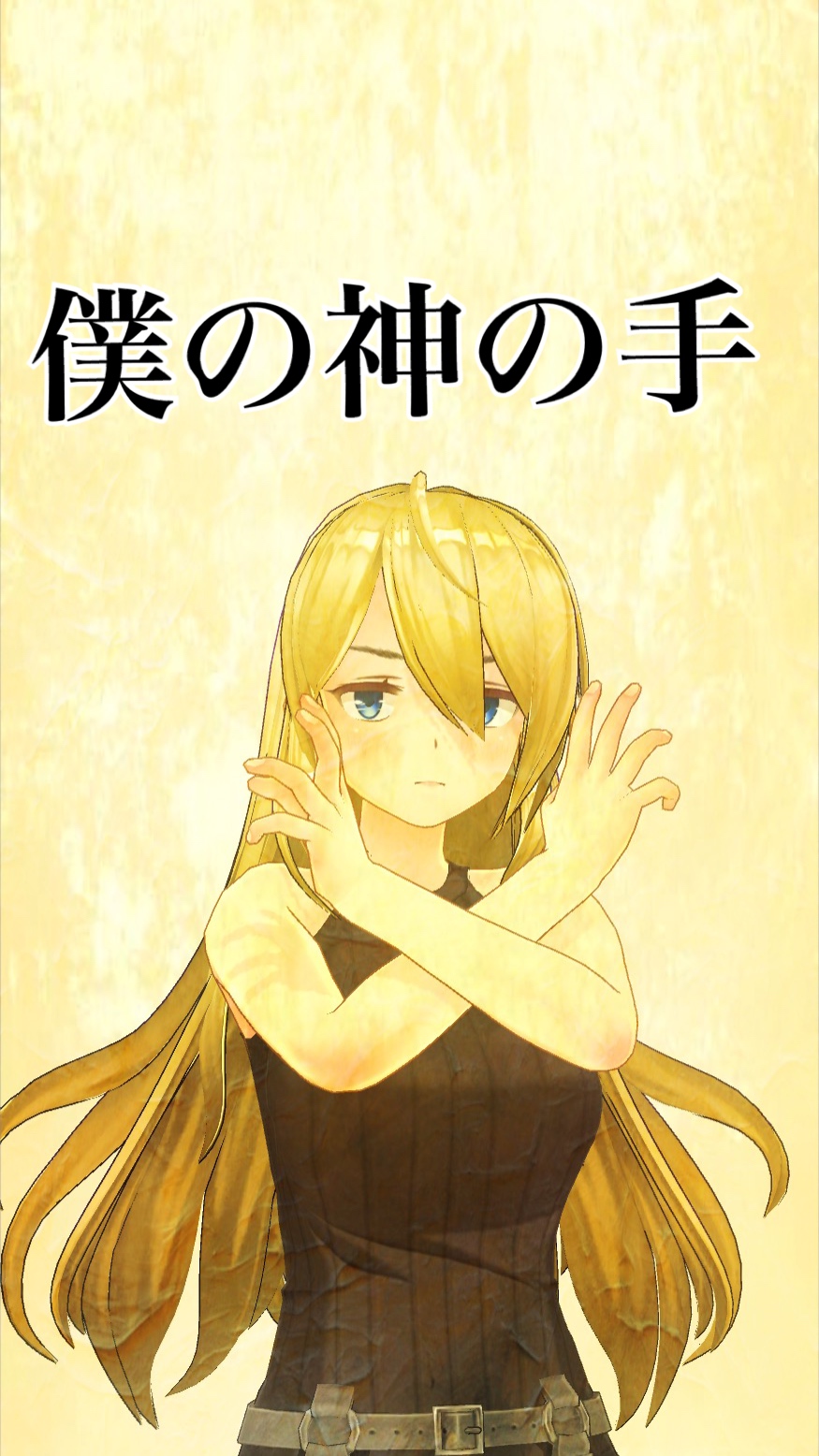21
「話変わるけど、あの量、よく持って来れたわね」
「え?なにがですか?」
「冷蔵庫開けた時、あたし大家族だったかしらって錯覚したわ」
「ああ・・・なんか、何買っていいかわからなくて。あれでもだいぶ戻したほうです」
「しばらくは何も買わずに済みそうだわ」
「いや、食べれない物は無理せず捨ててくださいね」
「あなたが買ってくれた物を捨てるわけないでしょ。ふふ、毎日雪音ちゃんを思い浮かべながら食べるわ」
「・・・早坂さん」
「ん?」
「って、変わってますよね」
「ええ!?何よ急に」
「いや・・・わたしたち、会ってそんなに時間が経ってるわけでもないのに・・・そこまで、その、大事に思ってくれてるから」
「あら、それは伝わってるのね。よかったわ。そうねぇ・・・年月で言うなら、そんなに経ってないわね。だからこそ、怖い部分もあるわ」
「と、ゆーと?」
「今でこうなのよ?この先あなたと時間を共有すればするほど、恐怖心も募っていくんだろうなって」
「恐怖心、とは?」
「うーん、そうねぇ・・・考えられる事全部、かな」
「それが聞きたいんですが」
「アハ、あたしもうまく説明できないわ」
「・・・わたしが、死んだら・・・とか?」
早坂さんは黙った。表情は見えないが、空気が張り詰める。何が、この人をこんなに不安にさせるんだろう。
「死にませんよ、わたしは」
早坂さんがこっちを向いたのがわかった。
「この先、時間を共有して、命の危険を感じる事があったら・・・その時は、早坂さんを盾にしてわたしは生き延びます」わたしも早坂さんを見た。「それでいいですか?」
「・・・クックックッ」ベッドが小刻みに揺れ始めた。早坂さんが暗闇の中でわたしの手を捕まえる。「そうね。気が楽になったわ。ありがとう雪音ちゃん」
「盾にするって言われて礼を言うのも、おかしな話ですけどね」
「雪音ちゃん」
「はい」
「さっきの、無かったことにしていい?」
「さっきの?」
「抱きしめていい?」
──"何もしないから"
「・・・そーゆーこと、わざわざ聞かれると・・・」
「いい?」
無言は、肯定の証。
早坂さんはわたしの頭を持ち上げると、自分の腕を差し込み、そのままわたしを胸に抱き寄せた。髪にあたたかい息がかかる。
「う─、落ち着く」
わたしも、今回は緊張より安堵が勝ったらしい。説明しようのない幸福感に包まれる。
「わたしも、この部屋、落ち着きます」
「え?何もないのに?」
「早坂さんの匂いでいっぱいだから」