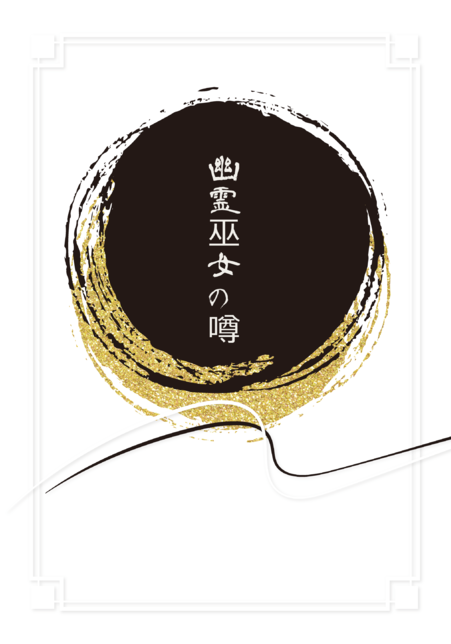第七話
澱んだ空間の中を涼佑と彼の肩に乗っている小蛇は進む。望の心を覗いた時と比べると、相手は大人なせいか、なかなかそれらしい光景には辿り着かない。水の中ではないのに、この黒い靄のせいか、足が取られるような感覚が消えなかった。
「それにしても、どこに行けばいいんだ? ずっとこんな景色が続くのは御免だぞ……」
独り言のつもりだったが、涼佑の一言に意外にも小蛇が反応した。ぴょん、と彼の肩から飛び降りた小蛇は真っ黒な地面ーー地面と言っていいのかは不明だがーーを這い回っていたかと思うと、ある一点で動きを止めた。
「そこに何かあるのか?」
涼佑も小蛇の傍に駆け寄ると、小蛇はまた彼の手を伝い、肩まで登ってくる。慣れない感触にぶるりと僅かに震えつつも、それに耐えた涼佑は小蛇が指し示していた場所を手探ってみる。すると、そこには一枚の扉が靄に隠されていた。点検口のように鉄で出来ている扉には丸い取手があり、それに指を掛けて上に引っ張ってみる。見た目から重そうな印象は受けていたが、予想通り、否、それ以上に随分と重い。
「う……くぅっ……!」
思い切り力を込めて、涼佑はその鉄扉を開けた。気を抜くと、落として閉まってしまいそうな扉を、何とか彼自身が通れる程まで開けてから涼佑は扉の向こうへ視線を落とした。
赤い。毒々しい煮詰めたような赤い世界がそこには広がっていた。まるで、地獄のようだ、と月並みに思ってしまう。宙に漂っている靄も赤い。しかし、この下に降りなければ、解呪の手掛かりすら掴めない。降りようかどうしようか逡巡して、腰に巻いている注連縄が切れないか心配だったが、元より涼佑に選ぶ権利なんて無いも同然なのだ。戻れるかどうか不安だが、そっと慎重に足から扉の中に入れ、思い切って飛び込んだ。
幸い、扉が閉まって注連縄が切られるようなことは無く、着地できたが、降り立った瞬間、空間全体に響いてきた怒号に涼佑は思わず耳を塞ぎ、小蛇はびくっと身を縮こまらせて涼佑の懐の中に隠れた。
「なんでこいつはこんなこともできないんだよっ!!!! これじゃ、いくらオレが金稼いできても、意味無ぇじゃねぇかよぉっ!!」
いきなりのことに涼佑はそのまま辺りの様子を見ていたが、真っ赤な空間が続いているだけで、特に危険なものがある訳ではない。しかし、そんな不気味な景色の中、男の声だけがしきりに誰かを怒鳴っていた。
「望の奴もおんなじだよっ!! 勝手に死んで親に迷惑掛けやがって!! あいつにどれだけ金を注ぎ込んだと思ってるっ!! それがくだらない失恋ごときで全部パァだ!!」
「折角、厳しく躾けてきてやったのにっ!! あんなに可愛がってやっていたのにっ!!」と喚き散らす声を聴いて、涼佑は自分の耳を疑った。
「躾けた? 可愛がった? ――何を言ってるんだ、こいつは。樺倉に……望にあんなことしておいて……っ!」
「バカで使えないお前に似たから望もこうなったんだよ! 全部、全部、全部お前のせいだっ!! お前が家を壊してるんだよ!! 出てけ!! この家から出てけよ、クズがっ!!」
パリィンッと遠くの方で何か陶器のような物が割れる音がする。その音にも小蛇は大きく反応し、涼佑の懐の中でぶるぶると震えていた。しかし、涼佑は怒りを覚える傍ら、頭の隅の方では冷静に、この空間を観察していた。望の心を覗いた時とは違って、記憶の中の景色というものは一切現れてこない。ただ、不快な他責思考の言い分が空間全体に反響しているだけだ。聞いているだけでも頭にくるのに、望と彼女の母はこれに暴力が加わってくるのだ。女性の力では抵抗するにも難しいだろう。家を不幸にしているのはお前だ、と涼佑は思った。
彼の父親はどんなに仕事で疲れていても、仕事と家庭は別と考えている人で、仕事のストレスを家に持ち込んだことは殆ど無かった。元々穏やかな人柄だったこともあるが、それでも、涼佑は密かに尊敬していたのだ。そんな父親のことを知っているから、尚更、この子供じみた主張をする男に怒っていた。父親を名乗る資格すら無いと思った。
おそらく、望と彼女の母は毎日のようにこんなことを言われ、暴力を振るわれてきたのだろう。だからこそ、望はこいつから逃れたくて、涼佑に縋り、呪いとなった。ならば――。
「こいつへ復讐すれば、少しは望の心も晴れるんじゃないか……?」
その結論に至ってしまうのは、自然だろう。元はと言えば、この父親が自分の役割を全うしていれば、自分に呪いが降りかかることなんて無かったのだ。ぎり、と憎しみと怒りで奥歯を噛み締め、それらを抑える為に涼佑は拳を握る。
しかし、とそこで涼佑は思い留まる。それは倫理的にどうなのだろう、と。いくらこの父親が憎いとは思っても、涼佑自身には復讐に至るまでの力は無い。結果的には巫女に押し付ける形になってしまう。もし、ここでこの父親の心に巣食う幽霊や妖怪を見つけることができれば、また話は違ってくるのだろうが。そんなことを考えつつ歩いていると、涼佑の肩からまた小蛇が飛び降りようとした。咄嗟に両手で受け止めた涼佑は、変な掴み方をしてしまったので、ちょっと心配そうに両手を開いてみた。
小蛇は彼の手の中でちょろちょろと尻尾を振って逃れようとしていたが、彼が手を開くと、途端に大人しくなった。じっとこちらを見つめる小蛇の目は、どこかギラギラした光を宿しており、何か言いたげだが、言葉を話す訳でもない小蛇の言葉を解することは涼佑にはできなかった。その代わりに急激に涼佑の意識は薄れ始め、ついにはその場に倒れてしまった。
注連縄が何度か引っ張られ、合図が来たと思った巫女は縄を引っ張る。厭に重いとは思いつつもやがて、窓を通じてずるり、と現れた涼佑の体を縄から手を離した彼女はその脇に腕を回し、引き抜いた。と、彼の服の端に何か付いている。よく見ると、それは黒い小蛇だった。その正体を一瞬で看破した巫女は咄嗟に腰の刀に手を掛けようか迷ったが、すぐに大した力は持っていないと分かり、手が掛かることは無かった。代わりに小蛇を手に乗せてまじまじと観察する。
「――ふむ……。呪いから魂だけが抽出されたのか」
「なんやそれ」
不信そのものという目つきで小蛇を見る柳に、巫女は簡単に説明する。
「まぁ、あれだ。こいつは樺倉望の魂と善意の塊みたいなもんだな」
「ほう。……で、こっちの坊の方は? また気絶しちゅうが?」
「さぁ。何か手掛かりは掴めたのか、起こしてみないことには何も分からん。おーい、涼佑~。起きろー」
つんつんと涼佑の頬を指でつつき始めた巫女の袖を、小蛇が咥えて引っ張る。それに彼女が応じ、「なんだ?」と自分の方へ意識が向くと、小蛇はその小さな両目で『あること』を訴えた。
「――ほう? そうすれば、お前は協力してくれるのか?」
こくり、と小さな黒い頭が頷く。暫し何事か考えていた巫女だが、やがて「但し」と人差し指を立ててたった一つの条件を口にした。
「決して命を奪うな。お前の好きにして良いとは言ったが、殺しは駄目だ。それだけは守ってくれ」
「殺してしまったら、お前の魂が穢れてしまうからな」という巫女の忠告に、小蛇は「分かった」と言うようにこくんこくんと頷いて、和室を出て行こうと廊下へ這い、消えていった。
小蛇が消えると、漸く涼佑が目を覚ました。「お、起きたか」と巫女に声を掛けられて、まだあまり覚醒していない頭を振った。頭を振ると少しは覚醒が早まり、やがて小蛇のことを思い出した。
「あっ、そうだ! 巫女さん、その……小っちゃい蛇、見なかった!?」
「ああ、見たぞ」
「そいつ、樺倉望なんだ。何か、オレにもよく分からないけど、あの窓に入ったら何か急に吐き気がきて……」
涼佑から小蛇が現れた経緯を聞くと、巫女は「やはり、そうか」と自分の予想が当たっていたことに納得したように頷く。それからも巫女は望の父親の心に何か手掛かりが無かったかと訊いてきたが、涼佑は「全然」と素直に答えた。彼女の父親の心には、霊や妖怪のようなものは何一ついなかったと報告すると、巫女は「ふむふむ……」と何やら考えつつも、聞いているようだった。あまりにも巫女が落ち着いていて、自分の周りに小蛇らしきものがいないと分かると、涼佑は焦った様子で「樺倉はっ!? どうしたんだよ?」と巫女に迫った。
「まぁ、落ち着け。あいつなら、そのうち帰って来る」
「……帰って来る、って?」
彼女の話がよく分からない涼佑の言葉に、巫女は当たり前のように言った。その言葉に、涼佑は掛ける言葉が見付からなかった。
「ああ、自分で復讐したら、ここに帰って来るって言ってたぞ」
仕事を終えた男は、真っ直ぐ家路を急いでいた。我ながら、浮気もしないでよくここまで我慢できたものだと思いながら、途中で寄ったコンビニで缶ビールを買い、歩きながらそれに口を付けた。飲まなきゃ、あんな陰気な家でなんてやっていられない。自分で自分を健気な奴だなぁ、などと思いながらまた一口飲んだ。酒が入ると、気持ちが大きくなるせいか、段々不満と苛立ちが腹の底から込み上げてくる。ちっ、あんな不出来な娘なんぞ作るんじゃなかったと。
もう自分も妻も若くはない。妻はあの大型台風の日に行方不明となり、遺体で見付かった娘を見て半狂乱になり、すっかり憔悴しきっている。全く役立たずになった。一時期は自殺しようとするまでに至ったが、世間体もあるし、これ以上、近所から奇異の目を向けられることには耐えられなかったので、いつものように殴りつけて止めさせた。妻の奇行に誠心誠意付き合ってやってる自分は、なんて偉い奴なんだろうと思う。
そうして自画自賛しているうちに家に着いてしまった。ああ、嫌だなぁと思う。家に帰ってもいるのは根暗な顔をした妻一人だけ。こうなったら、どこかで可愛い彼女の一人や二人作ってみたいもんだが、生憎と男には風俗で遊ぶという趣味は無かった。確かに風俗店なら若くて可愛い女の子はたくさんいるだろうが、その場合、自分は完全に客として相手をされるだけだ。本気になってくれないのは面白くない。
重い溜息を吐き、相も変わらず電気すら点いていない家の玄関ドアの把手へ手を掛ける。いつも通りにがちゃり、と開けてリビングへ足を踏み入れると、男は有り得ないものを見た。
夕食の準備をしてテーブルに突っ伏して眠っている妻の背後に、何かいる。カーテンが閉じられていない掃き出し窓から月光が差し込んでいる中、『それ』ははっきりと男の目に映っていた。
「な、んだ、お前……っ!?」
無感情に妻を見つめている、少女の形をした真っ黒い影。人間と同じように目に当たる部分だけが白く浮かび、じっと俯きがちに見つめていた。『目だけがはっきり見える影』としか言えない様相の相手は男の存在に気が付くと音も無く、瞬きをする間に距離を詰め、目の前まで迫ってきた。男は迷わず、悲鳴を上げて妻を置いて逃げた。夜の閑静な住宅街を『影』はやはり音も無く、滑るようにして追いかけてくる。あれに捕まったら、自分はどうなるのだろう。一度、考えてしまうとどうしようもなく、恐ろしかった。
「お、お、お、オレが、何したってんだよ……っ!」
走って逃げている最中、丁度通りかかったタクシーを止め、男は背後を気にしながら車内に乗り込む。行き先なんてどこでも良い。あの『影』がいないところへ行ければ、どこでも良いのだ。タクシーが出発すると、怖さの余り背後を確認する。『影』はもうすぐそこまで迫ってきていたようだったが、流石にタクシーには追いつけないようだ。
みるみるうちに遠ざかっていく『影』を見てほっと胸を撫で下ろし、男は背後に向けていた体を正面に戻した。
すぐそこに『影』がいた。助手席の陰からこちらを恨めしそうに見つめている。丁度、助手席から半分だけ体を出し、人間では到底不可能な体勢で、こちらをじっと見つめていた。
「うわぁあああああああああああああああっ!!!!!!」
絶叫を上げ、男は目が覚めた。朝。閉められたカーテンの隙間から朝陽と共にちゅんちゅん、と雀の鳴き声が聞こえてくる。自分のベッドの中で、男は汗だくで飛び起きたようだ。いつ帰って来たのだったか、いつ眠ったのだったか、思い出せない。隣を見ると既に妻は起きているのか、布団は捲られたままだ。そこで漸く、さっきまで見ていた光景が全て夢なのだと男は理解できた。
「――なんだ、夢……」
起きようと自分が降りる方へ目を向けた時だった。目の前に『影』が立っていた。
男は今度こそ絶叫し、ベッドから転がるようにして逃げ出した。