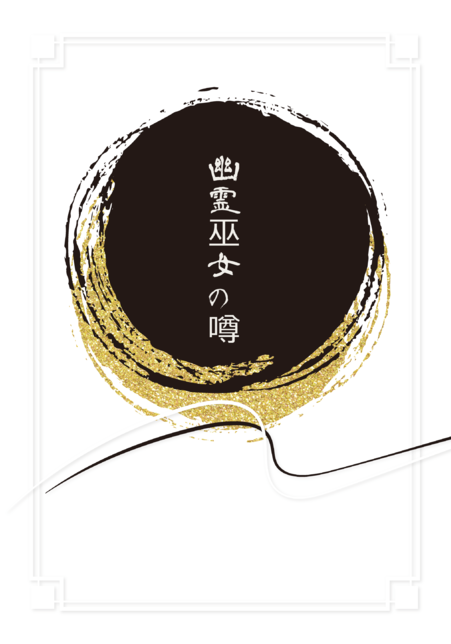第八話
小蛇が帰って来ると、巫女は「おう、お帰り」と迎えた。小蛇が戻って来たと知らされた涼佑は、慌てた様子で巫女が見ている方へ目を向ける。廊下にちょこんと小蛇がいて、こちらを見ていた。小蛇は涼佑の傍まで来ると、その手を伝って肩に登ってくる。
「ちゃんとしてきたか?」
巫女の言葉に小蛇はうんと頷く。彼女らのやり取りを呆然と見ていた涼佑だったが、はっと我に返り、小蛇と巫女に訊く。
「ほ、ほんとに、復讐……してきたのか? 樺倉」
その問いに、小蛇は嬉しそうに目を細めて頷いた。恐る恐る、巫女にも確認する涼佑に、巫女は「安心しろ」と小蛇との約束を話した。
「命までは取るなと言ってある。だから、殺人は起こっていない」
「で、でも……復讐、って……良いのっ!? 止めたりとかは――」
「? なんで私が止めなきゃいけないんだ?」
「え……?」
心の底から疑問に思っている巫女の表情に、涼佑は虚を突かれたようだった。あまりにも巫女の態度が堂々としているせいで、自分の方が何か間違ったことを言っているのではないかとすら、思えてくる。望の父親の心を覗いた時、あんなに悩んだのに、という思いもあった。未だ納得していない涼佑に、巫女が言う。
「何を悩んでいるのか分からないが、涼佑。これは望とその家族の問題だ。私達がどうこうできる問題ではないし、願われた訳でもない。最初からこいつの復讐に私達がごちゃごちゃ言う権利なんて無いんだ」
「でも……オレ……」
言い淀む涼佑を置いて、巫女は今一度、小蛇に「それで、どうしてやったんだ?」と確認する。小蛇は何度か瞬きをして頷き、巫女も何度か頷いて、話を要約してから涼佑に説明した。
「呪いとまではいかないが、自分の姿を目に焼き付けさせてきたらしい。――結果的にそれで死のうとも、自殺ってことになるから、望の魂に影響は無いな。良かった良かった」
巫女は「良かった」と言うが、本当にそれで良かったのだろうか、とどうしても涼佑は考えてしまう。いくら望や彼女の母親に暴力を振るったからといって、その子供である望に手を下させるというのは、本当に良かったのだろうか。涼佑は何ともやり切れない思いを抱えたまま、巫女に撫でられて目を細める小蛇を見つめるのだった。
「じゃあ、うちはこれで」
それだけ言って、そそくさと帰ろうとする柳を涼佑が止めようとしたが、まるでもう未練など一切無いと言い切っているかのような足取りで、気が付いた時には既に姿が見えなかった。その後を慌てて追いかける鬼の足音を聞いて、漸く巫女が先程まで柳がいた場所へ目を向ける。
「またすぐ帰ったのか、柳のやつ。すまんな、涼佑。悪い奴じゃないんだが、あいつ人間嫌いだからなぁ」
「いつもなら、二、三日余裕で泊まったりするんだが」と巫女が言っていることから、相当人間が嫌いなのだろうということだけが分かった。尚も小蛇と戯れている巫女に、諦めて座り直した涼佑は、ぽつりと訊いてみた。
「なぁ、巫女さん」
「なんだ?」
「……オレの方が間違ってる、のかな」
「いや? 私は涼佑の言うことも間違ってないと思うぞ」
不安げな彼に巫女はすぐさま、はっきりと言った。意外な言葉に、思わず俯いていた顔を上げる涼佑。巫女は小蛇を涼佑の肩の上に戻しつつ、元気づけるように続ける。
「私や望は既に現世における肉体を持たない。現世の人間と関わることはあっても、私達は再び同じ肉体を持つことはできないんだ。生き返ることなんて、できない。でも、お前は違うだろ?」
「……うん」
「現世に未練の無い私達に比べて、お前には帰るべき家があるし、場所がある。そんな奴が再び人間として生きていく為には、死者である私達と全く同じ考え方になっちゃいけないんだよ」
「だから、その考えは絶対に捨てるなよ」と言われて、涼佑は納得すると同時に、別に彼女達に拒絶された訳ではないと分かって安心した。ほんの少しだけほっとした顔をする涼佑に、巫女は「それに、悪いことばかりじゃないぞ」と励ました。
「見てみろ」と小蛇を指し示す巫女に倣って、涼佑は小蛇を手に乗せて見た。小蛇の尻尾の先を見てみろと言われてその通りにすると、よく見ないと分かりにくいが、尻尾の先がほんの少し白くなっていた。「なんか白くなってる」涼佑がそう言うと、巫女は満足そうに笑んで頷いた。
「おそらく、望が自分で復讐を果たしたから、恨みが少し浄化されたんだろう」
「浄化?」
そこからの巫女の説明は、涼佑にとって僅かな希望に繋がった。彼女が言うには、元々恨みというものは、人によって一定量というものが決まっていて、対象者が多ければ多い程、基本的には分散されていくものなのだという。
「人間社会そのものへの恨みは、また別の話になってくるが、個人の恨みというのは、そういうもんだ。最も恨みの深い者に対するものでも、最初の量というのは個人で決まっている。謂わば、涼佑。お前は負債を抱えている状態と同じようなものだな」
「……負債、っていうことはそれを返していけば――」
「いずれは呪いが解けて、現世に戻れるってことだ」
その結論に涼佑はぱあっと表情を明るくさせ、思わず巫女の手を取って喜んだ。その光景にはさして興味は無いのか、小蛇は欠伸をしてとぐろを巻き始めている。漸く見えてきた希望に小躍りでもしそうな勢いの涼佑を宥めて、巫女は「但し」と人差し指を立てた。それに思わず、背筋を伸ばす涼佑。
「その為には涼佑、望の恨みを浄化するには、望をよく知る必要がある。こいつをよく知り、話し合い、恨みを少しずつ浄化させていけば良い。その為の努力は怠るな」
「話し合う――って、言われても……。巫女さんはこいつの言葉が分かるみたいだけど、オレには分からないんだけど……」
「そこを含めて『努力せい』ってことだろ?」
「えぇ……」
なんかズルいと思いつつも、手の中でぷぅぷぅと眠り始めてしまった小蛇を見て涼佑は「どうしたもんかなぁ」と溜息を吐いた。そんな彼に助け舟を出すことは無いまま、巫女は「そいでだ、涼佑」と話を続ける。
「望の呪いが少しずつではあるが、解けると分かった。ので、お前には暫くの間、ここに滞在してもらうことになる」
「うん。…………あっ、もしかして、守役の話?」
ピン、ときた涼佑に巫女は「そうそう」と相槌を打ちつつ、「童子ー」と鬼を呼んだ。その呑気な声に応じてすぐ来た鬼へ、巫女は涼佑の今後のことを簡単に説明すると、「今日からお前の弟子だから、何か渡したい物あったら、持って来ると良い」と言うと、「ならば、少々待っていろ」と涼佑に言って、鬼は客間を通り過ぎて行った。その姿を見送りながら、巫女は涼佑の方へ振り返ると「後はそうだな……部屋移動するか。ここ客間だし」と涼佑に部屋を移ろうと合図を送る。彼女の合図に頷き、涼佑は取り敢えず、部屋の隅に寄せていた布団を移動させる為、掌で寝ている小蛇を布団より先に連れて行くことにした。
「歳も近いし、私の守役になるんだから、隣の部屋で良いだろ」
社務所の後ろにある住居の方に移った巫女は、一緒に来た涼佑に空いている部屋まで案内した。そこは巫女の私室の隣で、綺麗に掃除がされている洋室だった。他に空いている部屋は無いらしく「まぁ、空いてる部屋はここしか無いから選択権なんぞ無いが」と言われて、何故か涼佑の方が恥ずかしがった。
「いや、巫女さん。流石に女の子の隣の部屋はちょっと……」
「なんでだ? 嫌なのか?」
「嫌……っていうか、何か気まずい」
「いきなり入って来そうだし」と小さく呟かれた言葉は、しっかり巫女に聞こえていたらしい。「そんなに私はデリカシーが無いと思われてるのかっ!?」と心外そうに声を上げた。
「そんなことな……くも、無い、ぞ! うん!」
「自分でもちょっと思ってるんじゃないか」
弁明の途中で今朝の起こし方を思い出したらしく、言葉が詰まった巫女に涼佑が冷静に指摘したところで鬼が一振りの木刀を手に合流した。
「ここに居ったか、主人」
「ああ。今、部屋を移ってもらおうと思って案内してた。そしたらさぁ、涼佑のやつ、恥ずかしがって隣じゃやだって言い出してさ。ほんと困ってんだよー」
「オレ、そんな我が儘言ったかなぁ? 巫女さん」
それこそ心外だと言いたげに、涼佑は巫女を不信そうな目で見る。鬼の目には同い年の少年少女が戯れ合っているようにしか見えず、何とも微笑ましいものだと密かに巫女に友人が増えたことを喜んでいた。それを表情に出すような無様は晒さないが。
「部屋の件はお二人で話し合ってもらうとして、涼佑。己の弟子となったからには、そなたには新しい日課をこなして頂きたい」
「日課? 何ですか?」
鬼は涼佑の前へ木刀を差し出した。不思議そうな顔のまま彼が受け取ると、鬼は簡潔にただ一言だけ告げて去って行った。
「正式に主人の守役となったからには、これから毎日、これで素振りをしろ。百回だ」
「あ、分かりまし――え?」
それ以上質問は受け付けないと言うように、木刀を涼佑の手に握らせ、さっさと踵を返してしまった鬼の背へ「えっ!?」と涼佑は手を伸ばすが、とりつく島も無い。彼らのやり取りを静観していた巫女は、合点がいったという顔をして「ああ〜……」と零す。
「あいつも何だかんだ言って昔気質だからなぁ。ま、頑張れよ。涼佑」
「じゃあ、私寝るわー」と言って巫女もさっさと自分の部屋へ引っ込んでしまった。後に残された涼佑は、暫し呆然としていたかと思うと、はっと我に返って頭を抱えた。
「部屋の件、まだ納得してないんだけどぉ〜……!」
廊下で唸りながら頭を抱えていた涼佑だったが、やgていつまでもそうしていられないと諸々のことを諦めて、渋々部屋の中を確認しようとドアを開けた。
なんで。
いつでもどこにでも現れる『影』から逃げ続け、男は思う。なんでオレがこんな目に遭わなくちゃいけないんだと。早朝から家を飛び出し、会社に行くどころではなく、どことも知れぬまま走り続けた。逃げろ逃げろと、頭の中でいつまでもいつまでも警鐘が鳴り響いている。逃げろ。どこに? どこでもいい、あいつがいないところへ。いつまで? ――いつまでだろう。もしかしたら、永遠に……?
「うぁあああああ…………っ!!!!!!」
終わりの見えない鬼ごっこに、男は気が狂いそうだった。だから、その終わりが唐突に訪れたことで、男は漸く安心できたと同時に恨みを抱いた。必死に逃げて逃げて逃げて、いきなり体が宙を舞う感覚が男を襲った。すぐに全身を硬い地面に打ち付けられる痛みと衝撃。
「人が轢かれた!」
「誰か救急車を! 早く!」
正気を失っていた男には、周りを気にしている余裕など無かった。ただ何か壁のような物が横から全身を強かに打ち付けられ、気が付いたら倒れていた。ゆっくりと赤黒い血が流れていく。遠くで誰かが助けを呼ぶ声がしていたが、男には聞こえない。代わりに男の視界と聴覚を支配していたのは、理不尽に対する怒りだった。
どうして自分がこんな目に遭わなければならない。自分が何をしたというのか。目の前を流れていく血が信じられず、少し遠くに佇んでいるミラーに映った、地面に惨めに転がっている自分の姿が許せず、男はあの『影』を憎んだ。たとえ幽霊だろうが、それ以外だろうが、関係無い。オレをこんな目に遭わせたんだ。何としても捜し出して――
「ご、ろ……じで、やる……!」
人の目には見えない、黒い靄のようなものが男の体から立ち昇る。それは場違いな程青い空に不釣り合いで、やがて救急車で運ばれて行く男からぶちっと千切れて、グニャグニャと形を変えていった。
布団を移動させ、言われた通りに木刀で素振りを百回頑張った涼佑は、疲れ果てて眠っていた。もうとっくに昼過ぎだが、巫女も涼佑も起きてくる気配が無いので、鬼は下ごしらえだけ先に済ませていた。ふと、微かに妙な気配を感じた鬼は目だけで辿ろうとしたが、瞬時に大した力は持っていないと分かると、すぐに興味を失って冷蔵庫に入れるものにラップを軽くかけた。
どがんっと激しい打音のような音に驚いて、涼佑は飛び起きた。未だあまり覚醒していない視界で部屋の中の異常を捉えようとして、すぐに見つけた。自分のすぐ傍の壁に巫女が黒い靄のようなものへ刀を突き立て、暴れる巨大なそれを壁に縫い付けていた。涼佑が起きたと分かると、彼女は無表情のまま、目だけを涼佑へ向ける。
「涼佑、下がってろ。こいつは私が仕留める」
驚きと恐怖のあまり何も言えず、動けない様子の涼佑を見てすぐに判断を切り替え、自分が離れた方が良いと思った巫女は壁から刀を抜き様に靄へ体当たりして窓から外へ靄と共に落ちて行った。
「巫女さん……!!」
外へ落ちて行く巫女の姿を見て、漸く体が動き出した涼佑は必死に手を伸ばすも、その手が彼女に届くことは無かった。