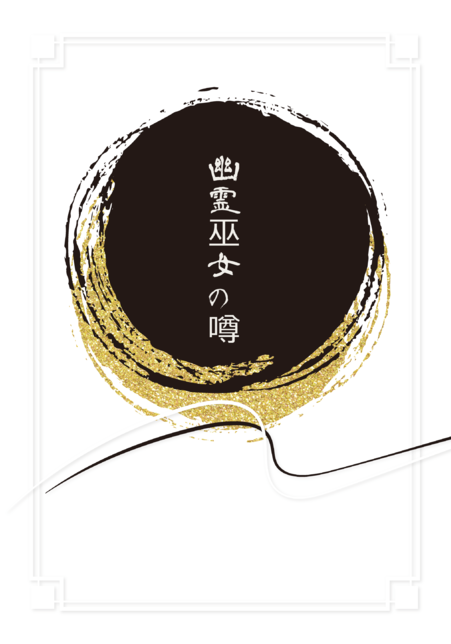第六話
さて、『心移し』を予防するにはどうしたらいいか。なんて、柳にとっても初めて考えることだ。普段の彼は、『心移し』に遭った若者のケアをするのが主な仕事だが、今回は予防をするのだ。今までに無い策を考えなければならない。「ううむ……」と彼は考え込んだ。今までの対処法と言えば、『とにかく他者の心を見ない』。これに尽きるのだが、今回のケースは少々特殊だ。そもそも『心移し』が起こった者がサトリではなく、人間なのだ。柳にはますます対処法など見当も付かない。
「一つ、訊いてもえい?」
「一つと言わずにいくらでも良いぞ」
「そちらの人間さんは今まで『心移し』に遭うたことは?」
柳の言葉にふるふると首を振る涼佑。それを受けて、彼は少々興味を唆られたようで、少しだけ身を乗り出した。
「ほう? 今まで遭うたことが無い?」
「は、はい。正直、あんな体験、したこと無くて……」
「まぁ、人間やきねえ」と何か含みがあるような言い回しをしたが、そこには特に言及されなかった。しかし、良い機会かもしれないと柳は思った。ここで考えた予防策をこの人間で試して成功すれば、儲け物だと。多少の調整は必要だろうが、人間に通じれば妖怪にも応用は効く。
「ということは正真正銘、うちもおんしも初めてのことやねや」
涼佑の返答を待たずに柳は「じゃあ、やれることは全部やってみるかねえ」と覚悟を決めた。
『サトリの窓』を前にして、柳は「まず……」と懐から仮面を取り出した。彼と同じような目隠し用の可愛らしい猿面だが、彼と揃いの黄緑色ではなく、赤茶の物だ。木で作られた物で、猿の地肌部分は本来の木の質感と木目や色を残し、毛が生えている部分はまるで栗饅頭の皮のようなつるつるとして且つ、ぽっくりとしている塗装がされていた。やや幼い顔立ちに彫られたその面を柳は涼佑に差し出す。
「なんか……まだ子供みたいな面ですね」
「『みたい』じゃのうてそうなが。おんし、小猿みたいなもんだしなあ」
にやにやと嫌味な笑いを含んだその言葉で、やっと喧嘩を売られているのだと気が付いた涼佑だったが、相手にしてはいけないと思い、「それで、これを被るってことですか?」と話を進める。そんな彼の態度に気を悪くした様子は無く、柳は続ける。
「そうそう。まずはうちらと同じように目から入るがか、見てみんことには分からんきな」
それを付けて『サトリの窓』を見ろ、と言う柳の言葉通りに涼佑は「じゃあ……」と自分の顔に付けて巫女へ声を掛けた。
「巫女さん、付けてみたから窓まで連れてってくれ」
「あ、涼佑。その前にちょっと良いか?」
そう言って巫女は慎重に立ち上がった涼佑に「手首出してくれ」と言って出させると、そこに細い注連縄を巻き始めた。何をされているのか分からなくて、涼佑は「巫女さん?」と少し不安げに訊いた。巫女はしっかり注連縄を巻き付けた後、元気づけるように涼佑の背中を軽く叩く。
「もし、窓に吸い込まれそうになっても、これを引っ張って出られるようにしておいたから、大丈夫だ」
「なるほど。命綱って訳か」
注連縄の強度を確かめてから巫女は涼佑の手を引いて、『サトリの窓』の近くへ連れて行く。相談の結果、いきなり望の父親の心を見るのは止めにして、まずは安全な人物の心を見ることになった。
「現世で安心できる奴っているか? 涼佑」
「う~ん……安心、だったら、直樹かなぁ」
直樹とは、涼佑に『幽霊巫女の噂』を教えた張本人で、彼のお陰で涼佑は助かったとも言える。心身共に健康で、普段から声が大きく涼佑とは親友同士だった。そんな直樹の心を覗くことに罪悪感が無い訳では無かったが、望の父親の心に比べたら、多少は仕方ないとも思える。巫女は特に直樹個人のことは訊かずに、「じゃあ、それで良いか」とあっさり採用した。
『それ』と称されたことには特に言及せずに、涼佑は見えないながらも目の前に窓があると仮定して、直樹のことを思い浮かべた。すると、すぐにまた窓の方へ体が吸い寄せられるような感覚がし、ぬるりと片手が何かに入ったような感触がした。
「涼佑!」
巫女が慌てて注連縄を引っ張る。しかし、それだけでは涼佑の体は窓から離れられず、どんどん彼の手は入っていってしまう。仮面で視界が塞がれている中、涼佑も抵抗しようと空いた方の手を窓枠に掛けようと探ったが、上手く手を掛けられない。焦る二人の背後からす、っと割り込んだ柳の手によって涼佑は襟首を掴まれ、背後に投げられた。投げる必要性は無いと思うが、「いてて……」とぶつけた腰を摩りつつ、涼佑は仮面を外して巫女の方を見た。
「あ、ありがとうございます……」
「別にえいが。……巫女ちゃん。おまさん、ようこがな妙なの拾うたねや。一般的な『心移し』の対処法が効かんなんて、変な奴じゃ」
「気持ち悪い奴じゃ」とあからさまに不快感を表す柳に、巫女は「おい、私の『客』だぞ。口を慎めよ」と注意する。一頻り「気持ち悪い」と騒いだ後、柳は「しかし……」と話題を変える。
「この方法が通じんとなると、対処法なんて無いんやないか」
「いや、諦めんなよ」
もうお手上げだと言いたげに巫女をじと、と見つめる柳に、何事か思案していた涼佑が言い出した。
「あの、今まで『心移し』の対処法って、『見ないこと』でしたよね?」
「そうじゃ。じゃが、見ても見いでも変わらんなら、仕方ない」
「返せ」と言われて涼佑は素直に仮面を返す。返しながら、涼佑は初めて他人の心を覗いた時のことを思い出し、言った。
「目隠ししてもしなくても吸い込まれちゃうなら、オレ一度はこっちに戻って来られたし、次も大丈夫なんじゃ……」
途端、涼佑の胸倉を柳が掴み、ぐいと容赦なく自分の方へ引き寄せた。浴衣の筈なのに首が締まり、「ぐえ……っ」と涼佑の口から苦しげな呻きが漏れる。そんなことには一切構わず、柳は凄んだ。
「おんしゃあ、バカか? それとも阿呆か? どっちでもえいし、どうでもえいけんど、うちや巫女ちゃんの労力も考えろ。殺すで」
「ご、ごめんなさい……」
柳に凄まれて、一気にしょぼんと肩を落とす涼佑。しかし、当の巫女は「まぁまぁ、落ち着け。柳」と宥めてからすぐに言い放った。
「どちらにせよ、涼佑とは『客』としての契約はしてるんだ。こりゃあ、本格的に飛び込んでみるしか無さそうだな」
巫女のその言葉に、柳は堪らないとでも言いたげに涼佑を放り出して立ち上がる。
「なんで!? なんで巫女ちゃんがそこまでせんといけんが!? たかが人間らあの為に……!!」
「お前にとっては『そう』でも、私にとっては違うからだ」
ぴしゃり、と毅然とした態度で放たれたその言葉に、柳は黙り込んでしまう。有無を言わせない真っ直ぐな目に、また柳の方が折れることになりそうだ。柳が黙ったのを見て、それを「了承」と捉えた巫女は涼佑を助け起こして「で、だ」と口を開く。巫女の背後からこちらを睨んでいる――仮面で見えないが――柳から目の前の巫女へ意識を逸らしつつ、涼佑は聴いていた。
「涼佑。見なくても『心移し』が起こってしまうということは、今のところ対策のしようがない。だからもうぶっつけ本番で行くぞ」
「ぶ、ぶっつけ本番!? で、でも……」
「大丈夫だ。今までもこれがあれば、戻って来られただろ」
そう言って巫女が示すのは、手首に巻かれたままの注連縄。細いそれを何重にも巻き付けられている手首を見て、せめてと涼佑は言った。
「巫女さん。せめて手首じゃなくて、腰に巻いていいか?」
「良いけど、こっちから引っ張ること考えると多分、痛いぞ?」
巫女の尤もな意見に少し悩み、「じゃあ」と涼佑は代替案を出す。
「足首でお願いします」
「分かった」
手首から足首に巻き直したが、後で涼佑「やっぱ手首にしとけば良かった」と心の底から後悔したのは、また別の話だ。
もう一度、注連縄の強度を確認してから涼佑は『サトリの窓』に近寄る。今度は本番、樺倉望の父親の心を見るのだ。そろそろと意味も無く、慎重に窓へ近付き、望の記憶の中にあったあの男の顔を思い浮かべる。またぐにゅ、と手が窓に吸い込まれる感覚がして、涼佑は今度は一気に自分から頭を入れた。
窓を潜り抜けた先は、ひどく空気が澱んでいた。物理的に視界はスモッグに似た、黒い靄のようなもので所々覆われており、周りの景色が非常に見えにくい。これで匂いまであったら、大変だろうなと涼佑は口の端を引きつらせた。ここからどうやって望が呪いとなった具体的な原因を探ろうかと考えていると、不意に胸の辺りが気持ち悪い、ような気がする。
「うっ……」
段々と胸の中がムカムカしてきて、涼佑は思わず胸を押さえた。迫り上がってくる吐き気を押さえようと口を塞ぐが、その指の間からごぽ、と何かが無理矢理吐き出された。
「おぅえ……っ」
あまり見たくはないとは思いつつも、手の中に吐いたものを涼佑はちら、と見る。それは黒い液体に塗れた小さな黒蛇、のように見えた。自分が吐いた物の正体が信じられず、涼佑は呆然と「なんだ、これ」と呟いた。不思議と胸のムカつきも吐き気も無くなっており、嫌でも手の中に意識が向く。吐いて少し落ち着いた彼はふと、小蛇がどことなくぐったりしているように見えた。何だか元気が無い。自分で吐いたとはいえ、仮にも生き物が手の中にいると思うと、涼佑はちょっと心配になってきた。恐る恐る指先でちょいちょいと触ってみる。小蛇ひんやりとしていて、触るとぐに、とやや硬い感触がした。
「大丈夫か? 樺倉」
はた、と思った。何故今、自分はこの小蛇を「樺倉」と言ったのだろう。考えても答えは出ず、それより先に小蛇に動きがあった。ゆっくりぱちぱち、と瞬きを数回して小蛇は目を覚ましたようだった。ゆっくりと小さな頭を擡げ、涼佑をじっと見つめる。その赤い双眸はしっかりと涼佑を認識すると、まるで火に触れたようにびょんっと飛び上がって地面に落ちた。
「おわっ!? いきなり飛ぶなよ、危ないだろ」
地面に落ちた小蛇は相当焦っているらしく、逃げようとして却ってもたもたと身を絡れさせている。そのままでは誤って踏んでしまうそうだと思った涼佑は、細心の注意を払って捕まえた。両手で包むようにして捕まった小蛇は手の中でもわたわたと転がっている。そのぬめぬめとした感触に「おおー……っ!」と鳥肌になる涼佑。それでも両手をそのままにそっと隙間を作って覗いてみると、それまでずっと動き回っていた小蛇はぴたりと動きを止め、こちらの動向を窺うようにじっと涼佑を見つめ返していた。怯えているのかと思った彼は、努めて優しく語りかける。
「大丈夫だよ、樺倉。何もしないよ。ただ、ここから先は危ないから大人しくしててくれな」
果たして、言葉は通じるのだろうかと思ったが、それは杞憂だったらしく、小蛇は涼佑の手から肩へ登ってきた。心なしか、ぶるぶると震えているようだ。涼佑にというより、この空間に怯えているのかもしれないと思った涼佑は、指先で小蛇に優しく触れて「大丈夫だからな」と元気付ける。そうしていると、少しは安心したのか、小蛇は涼佑の指に頭を寄せて目を細めている。すっかり大人しくなった小蛇をそのままに、涼佑はこの澱んだ心象風景の中へ足を踏み入れた。
窓の中にずぶずぶと沈んでいく縄をじっと見つめ、引っ張るタイミングを図っている巫女に、柳は「なぁ、巫女ちゃん」と声を掛ける。それに視線は外さず「なんだ?」と返事をする彼女に、柳はある約束を持ちかけた。
「うちはな、はっきり言って、人間なぞどうでもえいと思っちょる」
「それはもう知ってる」
「やき、おまさんに言っておこう思っちょったやき、言うけんど。もし、巫女ちゃんがあいたぁの道連れになるようじゃったら、うちは迷いなくその縄、切ろうと思っちょる」
「本気じゃ」といつの間にか手に鋏を持っている柳に巫女は呆れたように溜息を吐いて、「本当に、お前の人間嫌いにはいっそ尊敬の念すら覚えるよ」と言うも、特に反応を返すことの無い彼に、「……心配してくれて、ありがとな」と返した。
「おまさんはぎっしりそうじゃ。他人にばっかりてごうて、自分を簡単に犠牲にしちょる。あいつらぁがおまさんに何を返した? ぎっしり一方的に願ってばっかりじゃか! その代償というもんを、よお考えもしやあせん!」
『心移し』の恐ろしさを知っているせいか、いつもとは違う一面を見せる柳に巫女は「まぁ、落ち着け」と言って座らせた。巫女も柳の気持ちが分からない訳ではない。それでも、自分には使命があると、彼女はもう何度も言っている台詞を口にするのだった。
「それでも、私が『幽霊巫女』である限り、人間を救わないなんて選択肢は無いんだよ。柳」
「お前の気持ちは嬉しいけどな」とやはりいつも通りの答えを返す巫女を、柳は納得がいかないと言いたげに見つめていた。