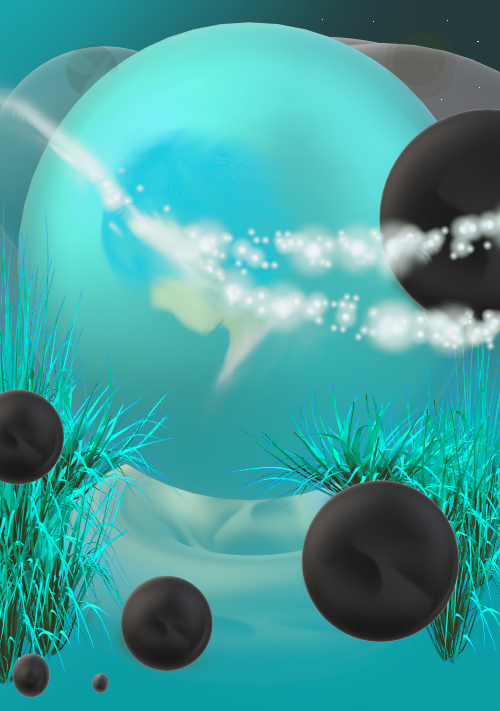泣きっつらに蜂.2
——…。
もとからあったものと合わせると、ふたつが。
高さと
そうして。
その地が、しゃんしゃんと降りそそぐ太陽の恵みさらされた、はじめの日。
ほどなく、正午になろうかというころ。
目をさましたセレグレーシュの視界には、
高温にさらされたせいで、ごわごわする頭髪。
熱を持ち、そこいらじゅうひりひりする皮膚の痛みをもてあましながら、まっさきに目に
そんな彼に近づいてきたのは、黄褐色の髪の法具店店員。見習いのアントイーヴだ。
「すごい顔だね、セレシュ君」
かけられた言葉をうけて、顔の表皮でも
ほてりは感じられるので、手や腕どうよう、高熱にやられて多少は赤くなっているのかも知れなかったが…――いまのところ、どこにも
全身くまなく見て確認したわけではなかったので、おおよその
「そのようすだとここ何日か、まともに寝ていないんじゃないかい? 街で少し、休んでから行こうか……と、いうのは建て前で、ぼくが休みたいというのが本音。――ほとんど寝てなくてね…」
相手の言葉に共感をおぼえたことで、遅ればせながら完全には消えていなかった疲労をひしひしと自覚したセレグレーシュである。
頭だけは妙にすっきりしていたが、こころなしか身体が
手元の水で
「帰るのか?」
喉の奥のあたりがひりついていたが、予測よりは、ちゃんとした声が出た。
「散らばった君の荷物、集め終わったらね。
「うん」
「どこに行ったんだろう? 反応ないんだけど……」
アントイーヴの胸の前で、やわらかな布地の八角がゆれている。
「(夜だったし、光球)活かしてた?」
「うん」
「おかしいな…。なら、簡単には飛ばされない。反応も強く出るはずなんだけど……。ほかに(
「《ミキシングボウル》……に《
「それは確保した。――問題は《
そのひとが右の手のひらに乗せているセピア色の
もとは無色透明な少量の粒子が、砂色や緑、青など、色彩を帯びながら、真珠色の布地の表面をするするとすべりまどって、一帯の気脈の属性をしめしている。
自然な状態では分析結果が複合的になるので、いまはとりとめのない動きを見せているが、法具のような特殊な物体が近くにあると、その性質を示す色を表現して集まったり、総量を増し、特徴的な模様や立体的な構造を築いたりする。
あくまでも三次元的な
適切な処置がほどこされているので、法具箱に入っている道具に対しても同様だ(
「君は休んでいていいよ」
「…。ひとり。
答える代わりに疑問を返したセレグレーシュの声が、少しばかりかすれて
「うん、彼かい……。そのへんにいるんじゃないかな。それより君、
「うん…。自分でできる」
「そう? 少しは持って来ているから、好きに食べて使っていいよ。君の備蓄は、たぶん……あらかたダメになったんじゃないかな」
気負いのない笑みをたたえていたアントイーヴが真顔になり、手もとの
まだらに焦げ、表面が吹きとばされ部分的に茶色の地面が露出したりもしている円形の苔野を横切って、離れていく。
目を覚ました当初から、セレグレーシュの視界のはしには、金色の髪の女
なにをするわけでもなく、広げられた飾り気のないシートの上に
セレグレーシュは黙々と作業を進めたし、その人も話しかけてくることはなかった。
見なれない法具箱に気をとられながら、負担にならないていどに喉と胃を満たし、身のまわりの状態を整える。
そうしてから彼は、目についた焼け野の中央——石碑があるあたりを物色しに立ちあがった。
確かめたいなら後にしろと言われた法印のコアが隠されている場所へと。
森のシンボルとしてあった碑は、上部と側面の一部が熔けてゆがんでしまっている。
昨夜の青白い
素材として使われている御影石の熱に対する耐性は、さほど高いものではないので、よく
それはともあれ……疑いをもって注視してみると、やはり。
その下部に固定されている《
完成形の
それは周辺の構成をとりのぞかなければ、入ることも出ることも、ひも解くことも不可能な空域だ。
それなのに……からっぽだった。
視点を移せば、いくらか中央からはずれた空中の一点に、アントイーヴが築いた《
少し気になったが、のぞく時は注意しろと言った
石碑の根元あたりに縮小されて見える封魔法印の中枢――。そこに見られる光の
——
思ったセレグレーシュは、複雑なおももちで視線をおとし、うつむいた。
(あいつ…。どこに行ったんだろう?)
そのあとは気になる姿を視野に捜しつつ、セレグレーシュも法具探索に参加した。
吹き飛ばされてばらばらになったり、燃えたりした荷物の大半は、そんなに重要ではなかったが、法具は壊れたり狂いが生じたりしても持ち帰る決まりになっている。
放置された法具は誰が手にするかもわからないし、
ゆえに組織は、その管理に神経質なのだ。
一般に流通するような法具にさほど危険なものはないが、門下生である彼らが用いる道具は、癖や効果が高いので、そのかぎりではない。
むろん、その土地や物体に固定された法印に使用された
持ち帰る必要がある種類の法印は、形成段階から
持ち歩くことが可能になることで出てくる問題もあり、いずれにせよ、そういった形式には封じきれないというのが現実で、常識でもあった。
「…とげ?」
「うん。あの、もとからここにある法印で……あっただろ?」
それは、ふたり。アントイーヴとセレグレーシュが、森林の中を散策しながらに交わす
「ばらばらな配置で、ひねりの入った
「あれは……。先々、ゆがみの原因になりそうなものを排除したんだと思うよ」
「…ゆがみの原因になりそうなものって、なにを?」
「おそらく、自生していた木をはじめ、植物の類」
「植物?」
「ん。木は特に
「そんなんで、よく、あんな重量があるものを置けたな」
「石碑のことかい?」
「うん」
「固い構成だからね……」
「時間が経てば、ゆがみにならないか?」
「あれを置く時、家も関わっている。法具ではないけど負荷も見えないし…。碑の製作を請け負ったのも、《(
「抑え?」
「後付けの盗賊対策だよ。まず、あれを寄せないと着手できないよう、補強されている」
「寄せるって、あんなもの、どうやって……」
「そんなに難しくないけど、へたに寄せたら困ったことになるよ?」
「簡単なのに、困るのか?」
「容易には回避できない
古い時代のものは、その限りでなかったりもするけど、基本、法印は解くことを想定して築くものだ。でも、あれはもう、解こうとする者と中の者に、ご愁傷様というしかないかもね」
「つまり…、解けないってこと?」
「どうだろう? ざっと視ただけだから。腰をすえて