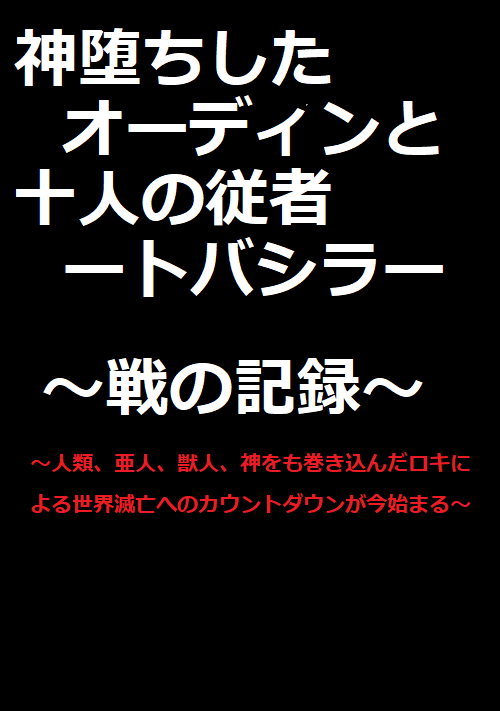泣きっつらに蜂.3
アントイーヴとふたり。
日が暮れるまで一帯を探しまわったが、《光球》は見つからなかった。
気になっていた
彼らは、みつからなかった法具をあきらめて、翌朝、この場所を発つことにした。
家の馬具(法具)には守護的な作用があって、法具の使い手がいない時でも、ちょっとした災害なら
夜半の騒動も許容の範囲内だったようだから、たいしたものである。
「火を見ても、暴れなかったのかな…」
「生物は火に対して過敏だからね。守りが働くし、目にしても、それと理解しなくなる仕様だよ。それでも
セレグレーシュの荷も、馬に背負わせたままにしていたら無事だったのかもしれない。
重量を軽減する作用が備わっていようと、そのままでは十全ではない。
肝心のセレグレーシュがその装備のあつかいを熟知しているわけでもないので、彼らの負担を考えると
「一頭は、彼のために残していこう」
「…。使わなかったら、どうするんだ?」
「
出発まぎわ。
残してゆく青鹿毛の
なんとなくおもしろくなかったセレグレーシュは、そこで話題を差し換えた。
「いい馬だな」
「うん。《クレバー》だったりしてね」
アントイーヴが応じると、セレグレーシュは目を丸くして黒馬を凝視した。
そう言われると目の前にいる動物が、とても利口そうに見えてくる。
《クレバー》は、高い知性を備えていて《神馬》《炎馬》、また、イチゴを好むという理由から《フレジエ・ホース》とも呼ばれる伝説の馬だ。
その特徴や生態・ありかたはどこまでもあやふやで風聞の域を出ない。
「これは違うよ。《家》には居るそうだけど…」
「いるのか?」
「たいていは外見じゃ見分けつけられないらしいけど……
幻の獣のようにもいわれる伝説の馬が、家のかたわらに広がるあの草原にいるんだと。
意識したセレグレーシュが息をのむと、アントイーヴは、いささか
「すぐ、真に受けるんだね」
「え? だって……(いるって…)。もしかして、(それも)噂話のレベル?」
「あまり期待しないほうがいいよ? 能力にかなりばらつきがあって、そんな、大層なものではないようだから……。あ、これ、部外者には内緒だよ? 秘密事項だから」
たしかに、そんなものがいるとわかれば、よからぬ考えを起こす者もあるだろうが…――。
軽い口調で念押しされたことで、とたんに真実味が失せた。
もしかしたら、からかわれたのかも知れない。
いずれにせよ、それが事実だろうと虚実だろうと、どうでもよい気がしてきたセレグレーシュは、そこで現実に立ちもどり、探りをいれてみることにした。
「あいつ。そのへんに、いるんだな?」
アントイーヴは、そのとき。
意味深な笑みをたたえるだけで〝いる〟とも〝いない〟とも言わなかった。
なにか
「わたしは、ひとりで乗るわよ」
女
いま残してゆくものも含め、馬は三頭しかいないので、セレグレーシュは、アントイーヴと馬の背を共にすることになった。
セレグレーシュは、ずっと、
セレグレーシュの挙動から、その思いを察してか……。
街を目指す道中――さほども進まぬうちに、馬の背を共有しているアントイーヴが言葉をくれた。
「彼ならきっと…。そのうち、ふらっと出てくるよ」
なだめてくれたのだろう――けれども。
「こじれた法具をそのまま利用したら逆流しちゃってね。――(
そこで成された法印
なので、セレグレーシュは彼の語りかけを途中で
「オレは、あいつを捜してるわけじゃない」
始終、視点がおよいでいる自覚があっても、セレグレーシュは認めなかった。
契約関係にないにせよ、あれはアントイーヴとつるんでいる
こちらに住む例の種族は、思いいれがないかぎり自分から人間に関わってこようとしない。
なかには物好きや、はた迷惑な個体、必要に迫られている場合もあるというが、それでも関わる相手は選ぶものだし、あの少年の場合は、きっと気が向かない方面には徹底して無関心だ。
セレグレーシュの異質さに多少好奇をくすぐられているにせよ、アントイーヴに力を貸していた。
ふたりが絆を結ばないのは、おそらく、いっぽうの少年が鎮めのパートナーに不適当といわれる子供だから。
それだけのこと。
そう、理解している……。
つもりなのに…。
この
セレグレーシュは、なによりも自分自身に腹をたてていた。
ヴェルダとの思い出が大切だった。
それなのに自分は、ヴェルダが見つからないからって、声が似ているその闇人をヴェルダの身代わりにしたてあげようとしてるのではないか?
おそろしく、はき違えたことをしている気がしてならない。
彼にとって、ヴェルダはひとり。
代わりなどありえないはずだった。
それなのにどうしたわけか、ヴェルダへの思いがその
見つけたような気になってしまう。
不快だったし不本意このうえないのに、それは感情的なもの——認めたくなかろうとめばえてしまう願望で…。
理性では、どうしようもなかったのだ。
「…それで――」
気分を変えたかったし、ふと想起され、思いつくと非常に気にもなったので…。
セレグレーシュは、それまで、すっかり失念していた疑問を口にする。
「オレの試験――これから仕切り直すことになるのかな?」
「流れるだろうね。君の試験場所、ベルドルーゼ方面みたいだから。ここから最短だと、難所も少なくない。いまから
〔どうって…。知らないわ。もう家に帰るんじゃないの?〕
(…知らないって、ひどくないか? だいたい、この人、スカウオレジャだって言ったのに……)
〔……。プルー。——
〔邪魔だから置いてきた(――必要ないし、重かったもの)〕
〔採点表も?〕
〔いまは持ってない。
〔いや、渡してほしいわけじゃないけど……そうか(――それじゃあ不履行なりに、その方向の努力証明もできないな……)〕
前と後ろで交わされた内容に目をまん丸にしたセレグレーシュは、発する言葉もかたちにできずに口をぱくぱくさせて、うつむいた。
(……うそだろ……オレの試験——この
スカウオレジャに着くと昼もなかばを過ぎていたので、彼らは西へとのびる街道がほど遠くない立地の宿に一泊することにした。