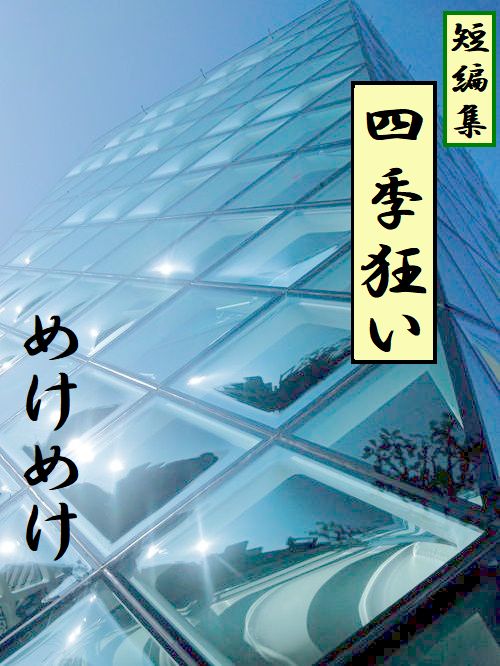266 ラクトの言葉/ケント、砂漠を眺めながら
「あの方が、キャラバンの村を取り仕切っている、村長さまなのですね」
長老が去った後、シュミットはラクトに言った。
「ああ、そうだ。村のみんなからは、長老って呼ばれてるよ」
「とても、瞳に強い光を感じました」
「えっ、長老に?」
……そうか?
ラクトはイマイチ、シュミットの言葉がピンとこなかった。
「私は彫刻を掘るとき、特に、目には気を付けてるので」
「そうなのか。まあ、長老は、歳の割には、元気だと思うぜ」
「おいくつなのですか?」
「……あっ、あの~、それはちょっと、詳しくは分からないけど」
「あはは!そうですか」
「へへ」
シュミットと笑い合うと、ラクトは、今度はサーシャのほうに顔を向けた。
「あんたの印象、変わったよ」
「……?」
急な発言に、サーシャはキョトンとしてラクトを見た。
「ラピスの運搬依頼のときは、礼儀知らずの、まともに話せないヤツって感じだったからな」
「あの時は、作品の製作に、集中してたから……」
サーシャが、少しうつむきがちに、言った。
「それにさっき、護衛の無事も祈っていたし、いまも長老とちゃんと話してたし、意外とやさしくて、ちゃんとしてるじゃねえか」
「……」
「それに、やたら強いな。援護しに行ったら、すでに一体のロアスパインリザード倒してて、ビックリしたぜ」
「えっ!?あの生物を!?」
「お姉さま、戦ってたの!?」
シュミットとニナが驚いて、サーシャを見た。
「ああ。場所が違ったから、見てなかったんだろうが。いつの間にか馬車から出てて戦ってて、ものすごく強かったんだぞ」
「えぇ~!見たかったよ~」
ニナは残念そうにつぶやくと、バルコニーの端に行き、中央広場を見下ろした。
「……あっ!マナトお兄ちゃん達だ!」
広場にある高台の下の長椅子に、マナトとミトが座っていて、ニナは手を振った。
2人も気づいて、手を振り返している。
「おう、ミト、マナトか」
ラクトがバルコニーから、顔を出した。
「あっ、ラクトだ」
2人はラクトに気づいた。
「ラクト~!メロの国に行くの、明後日になったって~!」
「大丈夫だ!知ってる!」
ラクトがサーシャのほうに、振り向いた。
「明日、テキトーに迎えに来るわ。そんじゃあな」
そして、ラクトはバルコニーを、ぴょんと飛び降りた。
「えっ!?」
「ラクトさん!?」
ニナとシュミットが、ビックリしてバルコニーから顔を出して、下を見た。
――スタッ。
ラクトはなんということもなく着地すると、2人のもとへと走り去っていった。
※ ※ ※
朝早く、村から砂漠へと続く道を、ケントは歩いていた。
人気は少なく、小鳥のさえずりが聞こえるほどに、静か。
ヒュゥゥと、少しひんやりとした風が、道を通り抜けた。
「……いよいよか」
いつものように、交易に行くときの装備をまとう。背中に大剣を背負い、日差しを避けるための、ベージュのマントを羽織る。
ケントは村の端に着いた。
その先は、もう、砂漠。
徐々に明るくなりゆく、砂の世界を眺める。
いよいよ、メロ共和国との、交易だ。
「……」
ケントは、周りを見渡した。
「……てか、誰もいなくね?」