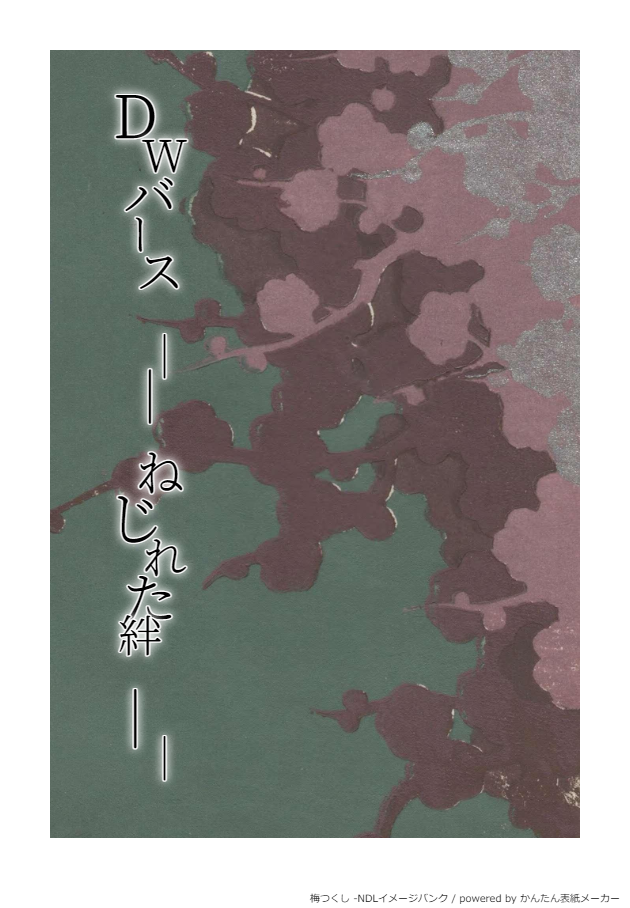【二十九】最初の朝
「い……――おい! 起きろ!」
厳しい怒声がした直後、僕は揺り起こされた。
僕は朝が弱いから、思わずぼんやりと瞬きをする。学園では、単位制だったから、本日の曜日は朝の授業がなくて、ゆっくりと寝ていてよかったはずだ。
「この煩いアラームをさっさと止めろ!」
「ん……」
「止めるからな!」
激昂しているのは、山縣だった。
僕はそれを見て、飛び起きた。そして短く息を吐いた。
自分が昨日から、ここに住んでいるのだと、漸く思い出す。
「三十分も鳴りっぱなしで、よく起きないな。お前の聴覚はどうなっているんだ?」
「ご、ごめん……おはよう、山縣」
「……」
僕の言葉に両眼を嫌そうに眇め、大きく溜息をつきながら、山縣は腕を組んだ。
挨拶が返ってくることはない。
「朝食は食べた?」
僕は慌てて言葉を探し、作り笑いを頑張った。
「まだだ。だが、だからなんだ?」
「僕、作ろうか?」
「できもしない料理をするというよりも先に、さっさと顔を洗って着替えろ。これから捜査協力を依頼されているから、出るぞ。助手を連れてこなければ協力させないと言われてな。別にこちらだって好きで協力しているわけではないが、事件には興味がある」
謎を解決したいというのは、探偵才能児が持つ根源的な欲求だという。
それを思い出しつつも、僕は大きく頷いた。
僕にとっては、初の事件だ。
そして山縣にとってはきっと、気にかかってたまらない真実が横たわっているのだろうと推測した。
部屋から出ていく山縣の背中を、少しの間僕は見ていた。
それから慌てて身支度をし、階下のリビングへと僕は顔を出した。
するとそこには、カフェで出てきそうなクロックムッシュが、皿にのり置いてあった。ハムが覗いていて、その上からは、とろけて皿にたれているチーズがあり、バターの香りが漂っている。卵や牛乳のしみ込んだ柔らかそうなフランスパンではさまれている。僕は思わず息を飲んだ。
「これ……」
「食べたくなければ、別にいい。だが、捜査中は、食べられない可能性が高いことを付け加えておく」
「い、いただきます!」
この日食べたクロックムッシュは、信じられないくらい美味だった。
また後に知ったのだが、山縣は非常に規則正しい生活をしていて、どんなに遅く眠ろうとも、朝の四時には起きて、護身術の自主稽古や筋トレをしていようだった。二階には、僕の部屋と山縣の部屋の他に、専門のトレーニングルームや書斎、資料庫などが存在していたため、覗く内に把握したのである。
――山縣は朝が非常に早い。
――山縣の辞書には、寝坊という単語は掲載されていない様子だ。
――山縣は、本当に何でもできた。一人で完結している。
それでも僕は、山縣の助手だから、出来る事を探していきたい。
そう願っていた。