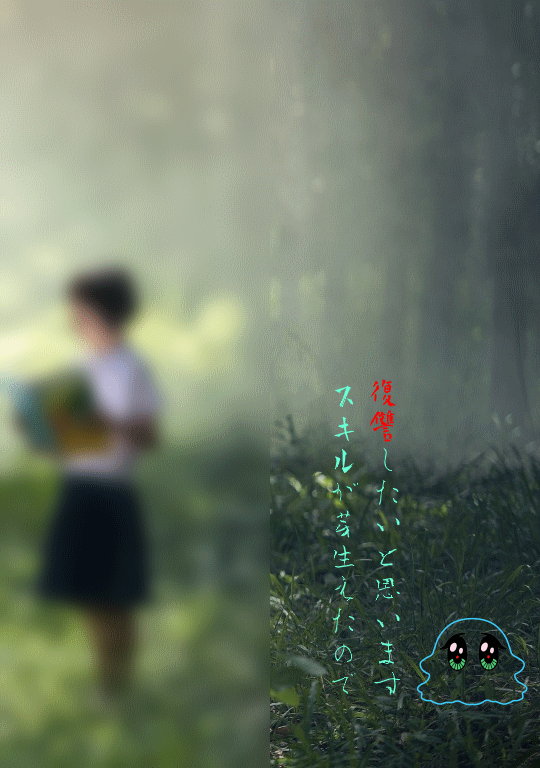竜の落とし子
夏の盛りが過ぎた森を、歩く者あり。方向音痴で半人半妖の
吹く風が涼しくなり始め、過ごしやすくなった。瑞々しい葉は、少しずつ乾いていく。この間まで激しく鳴いていた蝉の声は、もう聞こえない。代わりに、長くなりだした夜になると、虫が甲高い音を響かせた。
遊行は、いつもの通り竜宮へ続く洞窟を抜けて、入って行った。
遊行が竜宮に辿り着くと、朝の謁見の真っ最中であった。遊行は、
「貴方は最近、
側近の竜が話しかけてきたことに、遊行は目を丸くした。今日は、天変地異でも起こるのではないかと思ってしまった。その驚きを悟られないように、平静を装って、遊行は答えた。
「そうですね。天子様の命で、そうさせていただいてます」
「童子は、我々の期待の星です。変なことは教えないでいただきたい」
「どういうことです?」
「童子が外に出たい。森を出たいと言うのです」
「出させてあげればいいじゃないですか」
遊行がそう言うと、側近は強い口調になる。
「それでは困るのです。外へ出して何かあったらどうするのですか。もしも烏天狗に遭遇し、食われでもしたらどうするのですか?貴方は責任取れますか?」
周りがきっちり蚕月童子を見守って、烏天狗に襲われたときは、周りが助けてやればよいだけのことではないかと、遊行は考えた。遊行自身が傍についてやれるのなら、己が喰われようとも、助けてあげる自信が遊行にはある。それに、仮に助けられなかったとしても、それは弱肉強食である世の常として、諦めるべきなのだ。
「だからといって、危なくない場所で、囲って暮らせば幸せというものでもないでしょう。童子には、もっと教えるべきことがあると思いますよ」
「貴方が口出ししないでください。所詮、貴方は部外者でしょう」
遊行は口を噤んだ。「部外者」という言葉がやけに引っかかった。前の遊行であれば、「部外者」という言葉に何も思うことはないだろう。遊行は竜ではないのだから、当然である。しかし、遊行も童子の今後については、思うことがある。仲のいい友人のことを、気にかけない者はいない。遊行は苛立ちを隠し、強く拳を握る。
「どうしましたか」
険悪な雰囲気に、天の助けのように、天子が声をかけてきた。どうやら、朝の謁見は終わったようだ。側近は経緯を説明する。
「いえ、私はただ、この者に蚕月童子に余計なことを教えるなと言っただけです」
「ええ。それで、遊行はなんと答えたのですか」
「童子には、もっと教えるべきことがあると言いました」
「それから?」
「部外者が口を出すなと言いました」
天子はいつものように微笑みながら、互いの話をじっくりと聞いている
「そうですね、蚕月は、我々、竜の将来を担うことになるでしょう。だから立派に育ってほしいと思います。たくさんのことを学び、健やかになるように私たちが導くべきなのです」
「そうですよ。童子は大切な御子なのです」
「だから私は遊行に、蚕月にお話しするようにお願いしました。蚕月が森の外のことを知ることは、後々役に立つと、私は思ったからです。また、蚕月が竜以外の存在とふれあうこともまた、今後のためになると思っています。また、竜は『子育て』という習慣が御座いません。だから、他の種から『子育て』について参考にするのも手かと、考えています。それが『余計なこと』であるのなら、私の判断は正しくないと、貴方は仰るのですね」
側近の顔が青くなる。焦った側近は訂正する。
「天子のお決めになったことが、間違いであるなどと滅相もございません。出過ぎた真似をいたしました。私は務めがありますので、失礼いたします」
側近は深々と頭を下げて、そそくさと出て行ってしまった。天子は、深くため息を吐いた後、深々と頭を下げ、遊行に詫びを入れる。
「どうもすみませんでした。貴方に無礼なことをして」
「いえ、天子がお気になさることではございません」
「本当に『子育て』というのは難しい。あの子に何を教え、どう過ごさせる方がよいのかわかりません」
遊行は、前々から思っていた疑問を、この機会に天子に尋ねることにした。
「あの、童子を外へ連れ出したりしないのですか。貴女が連れ出そうとすれば、連れていくことが出来ると、思うのですが……」
天子は、目を瞬かせた。そして、俯いた後、天子は心の内を語って下さった。
「そうですね。私や八角玄竜、七角驪竜は、蚕月を一度くらい外へ出したいと、思ってはいるのです。しかし、臣下たちは先代の意向に背くからと、反対をしています」
遊行は、前に語って下さった、先代の天子の話を思い出した。その昔、四角の小竜を育てていたが、初めて外へ出た時に、運悪く天敵の烏天狗に襲われ、命を落としたと。
その後、また四角の小竜である、蚕月童子を育てることになった時、先代の天子は外へ出すことを禁じ、童子を奥座敷へ閉じ込めたのだ。
「私は元々、余所者で若輩者です。私が先代天子の意向に背き、蚕月を亡き者にしたいのだと、邪推する者もいるでしょう」
天子の蚕月童子に対する愛情を見れば、そんなことをするはずがないのにと、遊行は思った。
「可愛い子には旅をさせよという通り、危険を冒してでも、蚕月を外へ出すことが、あの子のためになると、重々理解しているのです。しかし、万が一、失ったことを考えると、辛いのです」
天子は、今までに見たことのないくらい、悲しげに笑う。遊行は、蚕月童子に対する天子の葛藤を理解した。そして、この尊敬する若き天子が、微妙な立場に置かれていることも。竜たちの間でも、蚕月童子の処遇に対して、複雑なものが交錯していたのだ。遊行は眉根を寄せる。
「遊行。貴方は、蚕月のことを、そこまで考えて下さっているのですね。ありがとうございます」
天子は、礼をしながら、感謝の意を唱えた。遊行は、天子の言葉に目を瞠った。そして、何故己が、竜のやり方に、口を挟んでしまうのかを考えた。そして、ふと思ったことを口に出した。
「俺は、童子に悔いの無いように生きてほしいんですよ。ただそれだけです」
「そうですか。考えておきます」
そう言いながら、天子は、先ほどとは違った顔で微笑んだ。
「今日も、蚕月にお話してくださるのですか?」
「ええ。そのつもりです」
「あの子は本当に、貴方のお話を心待ちにしています。これからもよろしくお願いしますね」
天子の言葉に、遊行は深々とお辞儀をしてから、奥座敷へと向かった。
奥座敷へ辿り着いた遊行は、蚕月童子に声をかけた。
「やあ童子。久しぶり。いい子にしてた?」
奥座敷を退屈そうにしていた童子は、遊行の声にくるりと振り返り、弾むような笑顔になった。
「あっ遊行。こんにちは」
遊行は、慣れた様子で、狭苦しい格子戸を潜った。童子は立ち上がって、ちょこちょこと遊行の方へ歩み寄って来る。その可愛らしい仕草に、遊行は笑みを浮かべ、寄ってきた童子の頭を撫で回す。遊行の大きな手に撫でられて、童子の表情はうっとりとした。周りを見渡すと、この間あげた蝉の抜け殻は、書物が置かれた棚の上に置かれていた。その隣には、なでしこの花が活けられていた。
「ねえ、遊行。今日はどんなお
遊行の腕をがっちり掴んだ童子は、ワクワクした様子で、遊行に訊いてくる。どうにも待ち遠しかったようだ。急かすように、早く早くとせがむのがいじらしい。
「そう急かさなくても話すから、落ち着きなよ」
慌てることなく、遊行は座布団に胡坐を掻いた。そして、笠と合羽を外して、傍らに置く。正面に、童子がちょこんと正座をした。
「今回の旅は、面白いものを見たんでな。その話をしよう」
「
童子はいつも以上に目を輝かせて、遊行を見た。身を乗り出し、期待に小さな手をぎゅっと握りしめる。童子の反応に、遊行はにやりと笑った。今日も遊行が語りだす。
俺が旅をしていたら、小さな港町に辿り着いた。港には漁船が並んでおり、漁が盛んであることが伺える。浜辺の近くを歩いていると、地元の漁師に声をかけられた。
「そこの兄ちゃん。ちょいと地引網を引っ張ってくんねけ。大物が掛かったみたいで、人手が足んねんだ」
俺は、漁師に連れられて浜辺の方へ向かった。そこには、男手だけでなく、老若男女が総出で網を引っ張っていた。掛け声をかけながら引っ張っても、網は一向に引き揚げられずにいた。俺も腕を捲って、引き子の間に割って入った。そして、掛け声に合わせて網の付いた綱を引っ張る。中々力のいる作業であり、足を踏ん張っても、引き潮に持っていかれそうになる。それでも懸命に一丸となって綱を引いた。それにしても、これだけの人数が引っ張っても引揚げられないとは、鯨でも人魚でも引っかかっているのだろうか。未だ見ぬ獲物に期待をし、体を傾けながら引っ張る。中々引揚げられなかった網も、段々には浜に上がった。網の中を見た漁師が、声を上げた。
「なんだ、見たこともない大きな生き物がいるぞ」
「龍だ!龍が上がったっぺ」
龍という声に、引き子たちが網の中を見る。俺も網の中を覗いてみると、面喰らった。まさに驚天動地だった。大小さまざまな魚に紛れ、それとは比べ物にならないくらい、大きな生き物がいた。蛇のように鱗に覆われた、五尺(大体1.5メートルほど)はありそうな、銀白色の長い躰。しかし、四肢が生えているので海蛇などではない。その四肢の先は、鋭い五爪である。頭部には二本の角が生えており、吻が前に突き出ていた。頭部から尾の先まで水で濡れた、白銀の鬣。正に竜である。
驚いた漁師は、絡まった鬣や角、爪に四苦八苦しながら、丁寧に網を切りながら、解いてやった。竜は、躰を丸め、目を閉じている。規則的な息をする度に、体が上下した。どうやら眠っているようだ。暢気なものである。竜にしては小さい気がしたので、どうやら小竜のようだ。皆がざわついた様子に、竜が片目を開けた。その眼の色は、天色で鮮やかだった。そして、大きく欠伸をした。竜の欠伸は、地を震わせるほど響き、皆が魂消た。集まった子どもが泣いて、それぞれの母親に縋りつく。しかし、小竜は知らん顔で、また眠り始めた。
「まさか龍を引揚げちまうとはなぁ」
「どうすっぺか」
「名主様に相談すっか」
漁師たちは、引揚げた竜をどうするかを話し出した。
俺は、眠る小竜を見つめた。そして、しゃがみ込み、銀白色の躰を揺すった。早く起き上がって、海に潜るか、天に昇った方がいい。しかし、そんな俺の思いとは裏腹に、小竜は寝息を立て続けた。
大きな荷車を持ってきた漁師たちが、竜を十数人がかりで持ち上げて、荷車に乗せた。それでも竜は起きることなく、眠り続けている。俺は後を追うことにした。名主の家に辿り着いた竜は、そのまま領主の居る城へ運ばれることになった。
城下町では、この滅多にない大事件に、多くの者が集まった。そして、竜が乗った荷車に、人々は道を開けた。小竜は注目の的であった。そして、竜が発見された瓦版がばら撒かれ、その一枚を俺は拾った。
数日後、竜は江戸城へ運ばれる後、京の帝の元へ献上されることになった。城を出立する時、まるで大名行列のような物々しさであった。
小竜は、中が木製の牢屋になった山車で運ばれた。その細い四肢には、鉄製の獣用の枷が嵌められていて、吻も口輪がされていた。竜は金属に弱いため、山車の中の小竜は、ぐったりとして、その天色の眼は弱々しかった。その大きな目からは、今にも涙が零れんとしている。
流石に、これはやりすぎではないか。周りの民は、土下座をして行列が過ぎるのを待っていた。行列が過ぎた後、矢張り小竜を見た人々が、可哀想だと口々にした。
城を出立したときは晴天であったが、段々暗雲が垂れ込めた。そして、ぽつぽつと降り出した雨は、次第に土砂降りになった。そして、雷霆がどんどん一行に迫りつつある。当初の予定では、海路であったらしく、港へと運ばれた。
三日経過しても、雨は降り続いた。港近くの宿に泊まり、嵐が鎮まるのを待ったが、時化が鎮まることはなく、一行の泊まる宿に高潮が襲った。
行列は、予定を変更して、陸路を選んだ。しかし、治まることのない雨に、一向に進まない。しかも、雷霆が轟き、行列のすぐ傍の木に稲妻が落ちた。雨の中でも燃え盛る木が倒れ、行列の武士を巻き込んだ。これには行列の中の武士も、平伏する庶民も、竜神の祟りではないかと、噂になった。
山道に差し掛かれば、土砂崩れや雷霆が襲い、川岸に着けば、滅多に荒れない川も暴れ川になった。こうしている間にも、檻の中の小竜は、どんどん疲弊していく。
一行が雨で足止めを喰らっている晩、警備が手薄になっていることもあり、俺は竜の様子を見に行った。
小竜はぐったりと項垂れ、目を閉じるが、眠ることは出来ないようである。口輪や枷で繋がれている箇所は、鱗が剝がれ、肉が剥き出しになり、火傷のように爛れているではないか。いくら何でもこれはやりすぎだ。俺は、小竜が不憫で仕方がなかった。木の檻を壊すことはできても、厄介な枷はどうすることもできなかった。
俺は、印籠に入った傷薬を、傷口に塗ってやった。森の河童が教えてくれた、妙薬である。屹度、竜にも効くであろう。傷口に沁みたらしく、小竜は暴れた。
「しーっ。暴れるなよ。見つかっちまうだろう」
俺は、人差し指を立てた手を、口元に寄せた。そして、小声で小竜を注意した。小竜は、すぐに大人しくなった。もう暴れる気力も無いのであろう。
手持ちの木綿や手拭いを裂いて、傷口に巻いてやった。更に、これ以上小竜を傷つけることがないように、口輪や枷を、隙間なく布で巻く。
「何故、お主はわしを助けるのじゃ?」
小竜が話しかけてきた。俺は少しばかり目を見開いたが、答えてやった。
「竜の友達がいてね。その子のことを思ったら、見て見ぬふりは出来なかった」
己とは違う竜の話に、小竜は何か反応を見せるかと思ったが、ただただぐったりとしている。
「ヒトの子め!わしに黒鉄の枷を嵌めおって……。おまけに、獣の肉を餌に与えてきよる。わしは竜じゃぞ。生き物は喰わぬ」
小竜は力なくも、ヒトに対する怒りを表した。そして、金属が当たらなくなったことに安心したのか、眠りについた。俺は、その寝顔に安堵の表情を浮かべ、後にした。この時、俺は警戒心が薄れてしまった。
「何者だ!」
俺は、警備をしていた侍に見つかってしまった。これはまずい。咄嗟に逃げたが、数人の侍に囲まれてしまう。万事休すだ。懐剣の賽ノ牙を構えるが、相手は打刀や槍を構えている。なんとも分が悪い状況だ。何とか応戦するが、最初から勝負は決している。とうとう、俺は侍どもに捕まってしまった。
捕まった俺は、侍どもの拷問を受けた。雁字搦めに縄で縛られ、夜通しで何遍も鞭でたたかれる。蚯蚓腫れからは血が溢れる。痛みで気絶しそうになると、すぐに水をぶっかけられた。
「さては、汝は上様や天子様に捧げる龍を、盗もうと企んだのか」
「違う。俺は竜が怪我してたから、薬を塗っただけだ」
「嘘を申せ」
侍どもは、俺の話に聞く耳を持たない。血塗れの状態で、俺は領主の前に引き出された。
「殿、この者が龍の檻の前で、怪しい動きをしておりました」
「龍の怪我に、薬を塗ったなどと宣っております」
「懐剣まで持っておりましたぞ。如何いたしましょう」
眠っていた領主は、機嫌が悪そうに家臣たちの報告に耳を傾けている。家臣から恭しく差し出された懐剣の賽ノ牙を、領主は受け取った。手元の賽ノ牙を鞘から抜いて見ている。
「下郎の者にしては、いい短刀を持っておるのう」
刃先を眺めていた領主は、色々な角度に賽ノ牙を持ち帰る。その瞬間、とある角度に持ち替えた時、行燈ぐらいしかない暗い室内で、領主は眩しそうにした後、手元がくるって、賽ノ牙を落とした。落ちた賽ノ牙は、領主の手をすっぱりと切った。領主の手からは血が溢れ出した。領主は、先ほどの眠そうな態度とは一変する。家臣たちは慌てて手当をする。脂汗を流しながら、領主は切れた手を抑え、俺を睨みながら、問いかけた。
「龍の怪我に、薬を塗ったというのは本当か?」
「本当です。竜は黒鉄が苦手でございます。口輪や枷で、爛れています。竜の脚や吻を御覧になってください」
俺は必死になって訴えたが、領主は興味がなさそうに聞いている。そして、傍らの火鉢から火箸を取り出し、俺の蚯蚓腫れにそれを押し付けた。
「ぐあああ」
のたうち回りそうな痛みが、俺を襲う。領主は俺の髪を引っ掴んで、宣った。
「五月蝿いのう。あれは、上様や天子様にお見せする大事な宝。怪我をしていようが、龍に手出しをするでない」
なんとも酷薄な笑みを浮かべている。大事な宝というのなら、怪我をしていない方がいいではないか。領主は、傍らの太刀を鞘に納めたまま、振り回して俺の頭を殴った。
「して、此奴は如何いたしますか」
「天変地異が続くようであれば、人身御供にすればよかろう」
残酷な宣告が、打たれた頭にこだまする。そして、意識が遠のいていった。
余りの天変地異に業を煮やした領主は、著名な祈祷師を呼びつけた。信仰心の強い祈祷師は、檻の中の弱々しい小竜を見るなり、小竜を放すように進言した。このままでは天竜が怒り狂い、更なる恐ろしい天変地異が襲ってくると。しかし、領主は聞く耳を持たず、刀を抜いて祈祷師を脅した。仕方なく、祈祷師が加持祈祷を行ったが、雨脚は強くなる一方であった。
小竜を献上するために、城を出立してから九日目になった。三日間の祈祷師による加持祈祷も空しく、雨は止みそうになかった。昏い天に扇を掲げ、領主は宣言した。
「よろしい、ならば人身御供を捧げるまでよ」
体中を拘束された俺は、侍どもに引きずり出された。外の騒がしさに、檻の中の竜が目を開けた。そして、俺と目が合った。領主は、俺を繋いだ縄を持って、天に向かって、高らかに声を上げた。
「天の神よ。御仏よ。今からこの者の命を、貴方様に捧げます。どうか鎮まり給え」
目の前の荒々しい濁流に、俺を落とすことで神々の怒りを鎮めようとしている。無益なことをするもんだ。神々というものは心優しく、命を無下にすることを嫌うのに。侍どもが俺を突き落そうと、後から棒で突いた。山車の檻の中の竜が、突如叫んだ。
「とと様!!」
小竜の叫び声は、俺にしか聞こえていないようである。そして、地響きがして、地が揺れた。
次の瞬間、天から竜が降りてきたかのように、激しい稲妻が八筋起きた。そして、耳を劈くような音を轟かせ、一撃の雷が、山車に落ちた。一際強い雷が落ちると、暗雲の狭間から強い光が差し込んだ。激しい光に目が眩む。
目が慣れた頃、一際大きな竜が、眼前に現れた。大きな竜は、八匹の竜を連れている。先ほどの雷で、山車の中の檻が壊れたようで、小竜が大きな竜によたよたと歩み寄った。どうやらこの大きな竜は、小竜のとと様であるらしい。自身も苦手であるだろうに、口輪の着いた小竜の吻を、自身の吻で擦り寄せた。それは、あたかも愛しの我が子に、頬擦りをしているようだった。その眼差しは優しい。
竜のとと様が連れてきた八匹の竜は、侍どもに襲い掛かる。竜に恐れをなした侍どもは、蜘蛛の子を散らすように逃げていった。竜の一匹が、俺を睨みつけた。それは品定めでもしているようだ。
「兄弟よ。その者は黒鉄に布を巻き、わしに薬を塗ってくれた恩人じゃ」
それを聞いた竜のとと様は、俺の方に寄ってきた。睨みつけてきた竜は、俺に巻かれていた縄を嚙み千切る。そして竜のとと様が、俺に吻を擦り寄せた。見る見るうちに傷が癒えていく。そして、傷を治した後、竜のとと様は頭を下げる。
「産み落とした我が子を助けていただき、ありがとうございます」
なんと貫禄のある声であろうか。見よう見まねで、縄を千切った竜や、捕らわれていた小竜も頭を下げる。
話を聞いているとこうだ。この竜は、天空に住まい、母親が卵を父親の胎に産み付け、父親の胎の中で育ててから生まれてくる。(ちなみに言うと、蚕月童子といった、森の竜たちとは生態が異なる)しかし、この竜のとと様が寝ている間、どうにも寝苦しかったようで、一匹だけ胎から産み落としてしまったようだ。他の兄弟竜や母親と探したら、地上のヒトに捕らわれていた。返すように数日、雷雨を引き起こしたが、返してもらえず、小竜の叫びを受けて地上へ降臨した。なんともまあ、人騒がせなことだ。
「ひいいい」
領主が叫ぶのが聞こえ、そちらを見ると、他の七匹の竜に取り囲まれていた。太刀を振り回すが、竜たちは上手くかわしている。一匹の竜が、太刀を振り回す腕に尾を巻きつけた。強い力で巻きつけられたので、領主は耐えきれず、持っていた太刀を落としてしまう。竜のとと様は、そちらを睨みつける。
「我が子の枷を取れ」
睨みながら、竜のとと様は領主を脅した。領主の脚はがくがくと震えている。領主は目を逸らそうにも、四方八方から竜に睨まれている。
「早う我の子の枷を取らんか!!」
竜のとと様が、吻を目いっぱいに広げて叫ぶ。すぐ近くに稲妻が落ちる。その響きに大気が、地が、川が揺れた。目の前で大きな竜に叫ばれた領主は、余りの恐怖に腰を抜かし、尿を漏らす。震えた領主は、散り散りになった家臣に命じた。どうやら、竜のとと様が言っていることは、領主や家臣たちにも分かったようだ。
「りゅ、龍の枷を外せ!」
「し、しかしよろしいのですか」
「愚図愚図するでない。予を助けよ」
枷の鍵を持った家臣が、恐る恐るやってきて、口輪と枷を外してやった。鍵持ちの家臣は、外す間、竜たちの催促にあっている。家臣は、鍵を外すと這う這うの体で逃げていく。領主もまた、数人の家臣によって運ばれていった。
小竜は解放に喜び、ふわりと浮いた。そして、俺の方へ飛んできては、吻を擦り寄せた。どうやら吻を擦り寄せるのは、親愛の証らしい。
「ヒトの子よ。ありがとう。そちの友達にもよろしく伝えておくれ」
俺は笑いながら、小竜に声をかけた。
「こっちこそありがとう。とと様や兄弟と、達者で暮らせよ。もう落ちるなよ」
捕らわれていた小竜は、竜のとと様の背中に乗った。そして、竜のとと様は、子どもたちの竜八匹を引き連れて、天へ向かい飛んで行った。
「とと様、わしをおっことさんで下され!」
小竜は、とと様の背中で怒っている。
「ごめーん」
竜のとと様は我が子に謝っている。竜の一家が天へ昇り、光りの射す雲の切れ間へ帰っていく。すると、いつの間にか小雨になっていた雨があがっていた。そして、世にも珍しい十色の虹がかかっていた。なんとも美しいその光景に、侍や川辺の宿場町の人々が、歓声を上げる。泥だらけになるのも構わず、その場に膝をついて、天変地異が止んだことに、手を擦り合わせながら拝む者もいた。俺は、いつまでも竜たちが昇った方を見つめていた。
「竜が空から落ちてきたお話は、これにて御終い」
天から落ちてきた、自分たちとは異なる竜の存在に、童子はもっと興味を示すかと、遊行は思っていた。しかし、童子の反応は違った。どうにも不安そうな顔立ちをして、座布団から少し前に這い出た。そして、遊行の胴体を見つめ、手を伸ばしてきた。
「どうしたの?」
「遊行、大怪我
ぺたぺたと、小さな手で腹あたりを触っている。童子は、話の途中で怪我をした遊行のことを、気遣っているのだ。童子の心配をよそに、遊行は笑ってしまう。遊行はとても嬉しかったのだ。
「大丈夫だよ。竜のとと様に治してもらったから」
童子は、遊行を見上げて、柔らかく笑った。まるで安心したかのように。遊行は、微笑みながら、童子の頭を撫でる。
「天に帰った
「屹度、家族に囲まれて楽しくやってるよ」
「……いいなあ」
童子は、小さく、すごく小さく呟いた。しかし、遊行は聞き漏らすことはなかった。寂しげに笑った童子は、家族に囲まれて育つ小竜のことが、羨ましいようだ。気持ちが痛いほど分かった遊行は、膝の上をぽんぽんと叩いた。
「おいで、童子」
童子は立ち上がって、遊行の胡坐の上に座る。今度は、きちんとしっぽを遊行の躰に巻きつけるようにした。遊行は、左腕を童子の腹の方へ回し、右腕で頭を撫でる。童子が如何に小さいかが、よく分かった。
こんな小さな子どもが、たった一人で、薄暗くてじめじめとした奥座敷にいるのは、心身の成長に良くないだろう。あの小竜のようにはいかなくても、誰かに愛され、お天道様の下で伸び伸びと生きる方が、童子のためになるだろうと、遊行は思った。
「い
童子は、遊行に抱きしめられながら言った。童子の願望が大いに詰まっていた。
「逢えるさ。屹度」
遊行は囁くように言う。
「
童子がへにゃりと笑った。遊行は、この子どもも、この檻から出してやりたいと思った。しかし、遊行にはそれだけの力も勇気もない。己の不甲斐無さを噛みしめながら、遊行は、童子の頭を撫で続けた。