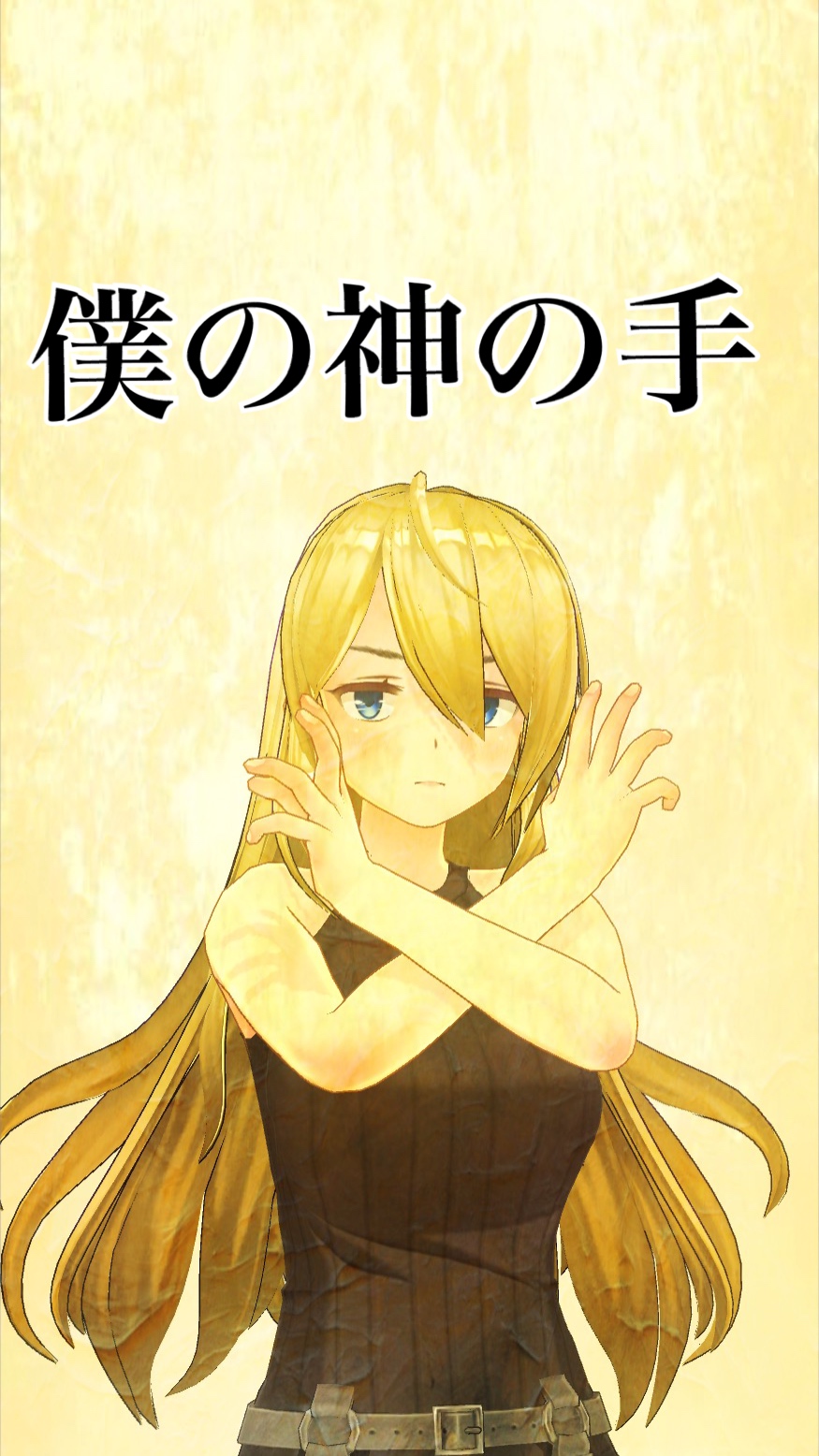エピローグ
あの戦いから、二日経った。
僕は、ピレックルの大通りに面するホテルの一室に来ていた。いつもはお父さんが最高級の部屋を用意してくれていたけど、今日はお父さんはいないから、普通の部屋を使っている。
今日はクリスマスイヴ。ピレックルの噴水の広場と大通りは朝からクリスマスパーティーの準備で大忙しだったけど、昼になった今は作業の手を止め、休憩している人も多い。
イベントの責任者であるアイリーも、僕の隣でくつろいでいる。
「ジュース、飲む?」
僕はザサンノジュースを取り出した。
「ありがと。お兄ちゃんにしては気が利くじゃん」
朝からずっと作業が続いて疲れていたからか、アイリーはザサンノジュースを一気に飲み干した。
僕もザサンノジュースを飲む。本当は僕が飲みたかっただけなんだけど、僕だけが飲むのはなんだか気が引けるから、アイリーにも飲んでもらうことにしたのだ。
「こういうイベント、羨ましい」
窓の外の光景を見ていたフレアが振り向いた。
「FoMじゃ、こんなのしようと思っても絶対誰も乗ってこないし、そもそもそういう発想がないし。森で戦ったり、ギルド同士で戦ったり、とにかく戦ってばかりだから」
「でもさ、いつでもこっちに来れるんだから、遊ぶ時はこっちに来ればいいじゃん。お兄ちゃんでも誘ってさ」
「ぶっ」
思わずザサンノジュースを吹き出しそうになってしまった。
「いいわね。でも今はちょっと無理そうだけど」
部屋の外で足音が聞こえ、ドアが開いた。
シェレラとアミカだ。
「ケーキ、買ってきた」
シェレラは両手にケーキの箱を持っている。両方ともかなり大きい。この人数なら、一箱でも十分足りると思うんだけど……。
「一人、一個ね」
シェレラは謎の言葉とともに、ケーキの箱をテーブルに置いた。
ここにいるのは五人。そして、ケーキの箱が二つ。
どう計算したら、一人一個になるのだろうか。ひょっとして一つの箱にケーキが五個入っていて、もう一つの箱はケーキじゃないのだろうか?
「開けていい?」
シェレラに断って箱を開けた。中にあったのは丸太の形をしたケーキ、ブッシュ・ド・ノエルだ。
ということは、これを五等分しようということなのだろうか。じゃあ、もう一つの箱は……。
おそるおそる、開けてみる。
ごく普通の、クリスマスケーキだ。ホイップクリームで覆われたホールケーキの真ん中にサンタクロースがちょこんと座っていて、いちごがその周囲に並んでいる。
ますますわからなくなってきた。
「えっと、シェレラ、一人一個っていうのは、どういう……」
僕の疑問を無視して、シェレラの指先が動く。
空中から、ケーキの箱が出現した。
それをテーブルに置いたシェレラが、またケーキの箱を出現させる。それをまたテーブルに置き、また箱を出現させる。
合計五個のケーキの箱が、テーブルを埋め尽くした。
「リッキはどれがいい?」
「ちょっと待って」
一呼吸置いて、目の前で起こったことを落ち着いて把握する。
「一人一個ってのは、一人一箱ってこと?」
「そうだけど?」
「あ……う、うん、えっとね、シェレラ。たぶん、一つのケーキを切り分けて、みんなで食べるのが、いいと思うよ」
「そう? じゃ、そうする」
結局、食べることにしたブッシュ・ド・ノエル以外の四つのケーキが、シェレラのアイテムウィンドウに入れられた。
切り分けられたブッシュ・ド・ノエルに、フレアが入れた紅茶が添えられた。
「じゃあ、いただきます」
ブッシュ・ド・ノエルをフォークで一口サイズにカットして、口へ運ぶ。濃厚なチョコレートは、甘さの中にちょっと苦味が含まれていて、とてもおいしい。すっきりとした味の紅茶を飲むと口の中がリセットされ、またおいしく食べることができる。
「この間のことなんだけどね……」
紅茶を一口飲んで、フレアが話し出す。
「もうFoM中が大混乱よ。『キロンジェンの大噴火』のせいで」
片肘をつき、だるそうにブッシュ・ド・ノエルにフォークを刺した。うんざり、という感情を、あからさまに口調や態度に含ませている。
僕たちはあの日、本当は『キロンジェンの穴』と呼ばれる、垂直に地下に伸びる巨大な穴へ行って冒険をする予定だった。その穴は下へ進むと霧が濃くなって先へ進めないため、底がどうなっているのかを知る人は誰もいない、という場所だった。
その『キロンジェンの穴』から、突然、大量の素材アイテムが吹き出してきたのだ。激しい勢いで空高く舞い上がった魔石や鉱物、それに星屑が、まるで火山が撒き散らした灰のように地上に降り注いだ。『キロンジェンの大噴火』と呼ばれることになったこの現象によって巻き散らかされた素材は極めて良質で、FoM中の誰もが文字通り降って湧いたこの幸運を手に入れようと、我先にとアイテムを拾い集めた。
素材の奪い合いは、結局全く起きなかった。
素材があまりにも大量に、そして広範囲に降り注いだからだ。
「おかげで素材アイテムの価値は大暴落。今でもちょっと歩くだけで簡単に拾うことができるわ。武器や防具もハイスペックなものが出回りまくって、もうそれが標準と言ってもいいくらい。これまでの武器や防具は、全部ゴミね。ゲームバランス? 何それ? って状態よ」
やけに小さくカットしたブッシュ・ド・ノエルを口に放り込み、紅茶を一口飲んだフレアが、ぼんやりと天井を見上げた。
「こんなことになるんだったら、戦うんじゃなかったなー」
僕たちが岩の巨人と戦った円形のフィールドが、実はキロンジェンの穴の底だったこと。
穴の底を隠していた濃密な霧は、岩の巨人が吹き出す水蒸気によって作られていたこと。
戦っていた時は、そんなことは全く想像できなかった。
もちろん、岩の巨人を倒すことであの円形のフィールド全体が壊れ、地下の資源が空高く吹き出すなんてことも。
「世界を買うどころか、世界を壊しちゃったって感じ。責任感じちゃうわー」
「でも、私たちが岩の巨人を倒したせいだってのは誰も知らないんだしさ、知らんぷりしてればいいじゃん。こうなっちゃったら、もうしょうがないって」
「アイリーのそのポジティヴ思考、羨ましい……」
僕から見ればフレアも十分ポジティヴだと思うけど、アイリーと違って根が真面目なぶん、なかなか立ち直れずにいるようだ。
「それに、あの戦闘で一番活躍したのって、あんまり言いたくないけどハンジャイクじゃん。だからフレアが責任感じることなんかないって」
「アイリー、もう言わないで。それはそれで悔しいから……」
岩の巨人の四つの目のうち、二つはハンジャイクが破壊した。ハンジャイクがいなければ、巨人を倒すことができなかったのは間違いない。
あの日僕たちが触手に捕まって、コンクリートの部屋へ飛ばされたこと。
その先の通路を通ってキロンジェンの穴の底へ行き、岩の巨人と戦ったこと。
それらは全て秘密にしてある。
昨日、フレアはザームと二人で、触手が生えるあの岩の場所へまた行ったそうだ。でも触手は生えてこなかった。キロンジェンの大噴火が起きたことでスタッフが気づき、通路へつながる手段や通路そのものを撤去したのだろう、というのが、僕たちの結論だ。
だったら、今さら言っても仕方がない。このまま黙っていたほうがいい。
「唯一良かったことといえば、ゾトルハ鉱山での争いがなくなったってことね」
『黒獅子党』がゾトルハ鉱山にちょっかいを出していたのは、鉱山の資源を独占するためというのが表向きの理由だった。良質の素材アイテムがそこら中に落ちている今、その理由は意味をなさなくなってしまっている。
「ハンジャイクも、地下で何があったのかは一切言っていないみたい。『黒獅子党』から今回のことについてのうわさ話なんかは全然出ていないし。というか、大噴火のせいで何もかもがうやむやになったって感じね」
「それに、ゾトルハ鉱山とキロンジェンの穴がつながっていたなんて、誰も思わないよ。いくらゾトルハ鉱山で騒動があったからって、それをキロンジェンの大噴火と結びつける人なんていないんじゃないかな」
「そうよね。私が考えすぎなのかな」
ずっと天井を見上げながら話していたフレアが、僕を見て少し恥ずかしそうに笑った。
アイリーの右手の指が、せわしなく動き出した。
「ごめん、パーティーの準備で用事ができちゃって。パーティーは夜からだから。絶対来てね!」
食べかけのブッシュ・ド・ノエルを残して、慌ただしく部屋を飛び出していった。
「アイリー、頑張ってるわね。いいの? リッキは何もしなくて」
シェレラは一度片付けたクリスマスケーキをまた取り出して切り分け、アミカと二人で夢中になって食べている。話しているのは僕とフレアだけだ。
「家でクリスマスパーティーをすると、なかなかクリスマスって感じになりにくくてさ。特にアイリーはそう感じているはずなんだ。だからそのぶん、リュンタルでは張り切っているんだと思うよ」
「どうして? 何かクリスマスパーティーをやりにくい事情とかあるの?」
「うん……そのことでなんだけどさ」
アイリーが聞いているはずはないのに、僕は声をひそめた。
「実は、みんなに相談があるんだけど……」
○ ○ ○
「おつかれー!」
「おつかれー!」
十二月二十五日。太陽はほぼ沈み、魔石による照明が噴水の広場を照らしている。
前日の夜から行われていたクリスマスパーティーが終わり、スタッフ同士がお互いをねぎらっていた。
「アイリー、おつかれー!」
「うん、おつかれ」
アイリーに声をかけてきたのは、一緒にパーティーを運営した友達だ。
「どうしたの? あんまり元気ないね? 今日は朝からずっとだったから、疲れちゃった?」
「そんなことないよ。全然疲れてなんかないって」
「あーひょっとしてお兄さん? 昨日の夜はいつもの友達と来てたけど、今日は来なかったよね? それでがっかりしちゃったの?」
「そそそそんなことないって!」
「アイリー、顔が赤くなってるよ?」
「……そりゃまあ、来てほしかったけど」
アイリーは赤くなった顔を指で掻いて、照れ隠しをした。
「でも今日はインしなかったみたいだし、たぶんリアルでやることがあったんじゃないかな?」
「あーそっか、お兄さんみたいな人が、クリスマスにリアルでヒマなはずがないもんね」
「それは絶対にないって」
友達の発言を笑い飛ばす。
「お兄ちゃん、結構ヘタレだし。絶対ないない」
そう言いつつも、アイリーには心当たりがあった。
シェレラ、アミカ、そしてフレアも、今日はインしていなかった。
もしかしたら、リアルで誰かから誘われていたのかもしれない。
そんなことあるはずがないと決めつけて心の奥に封印していたけど、あらためて指摘をされると、やっぱりそうなのかもしれないという気持ちが沸き起こってきた。
「やっぱりちょっと疲れちゃったかな。今日はもう落ちるね」
アイリーの指先が、ログアウトを選択した。
◆ ◆ ◆
部屋は、暗かった。
ログアウトするのは夕食の時間に合わせることが多いから、暗いのはいつものことだ。
ゴーグルを外し、そのまま部屋を出てすぐ隣の部屋のドアをノックした。
「お兄ちゃん?」
返事はない。
そっとドアを開ける。部屋は暗く、誰もいない。
きっと台所にいるのだろう。それもいつものことだ。もしかしたら、もう夕食を食べ始めているかもしれない。
階段の電気をつけ、降りる。ちょっとした違和感。
一階が、暗い。
廊下の電気もついていないし、その先のリビングから漏れてくるはずの光も、ない。
誰もいないの?
もしかしてお兄ちゃん、本当に誰かに誘われてどこかに行っているのかな……。
おそるおそる、リビングのドアを開けた。
「お兄ちゃん? いるん――」
突然、部屋が明るくなった。眩しさに思わず腕で目を覆う。
パンパンと乾いた音が鳴り響いた。何事かと少しずつ腕をどかすと……。
「ハッピーバースデー、愛里!」
クラッカーから放たれたカラフルな紙テープが、遅れて愛里に降り注いだ。
◇ ◇ ◇
「えっ、ちょっ、えっと、な、何これ? ど、どうなってんの!?」
僕と智保、玻瑠南、それに西畑からクラッカーの祝砲を受けた愛里は、まだ現状がよくわかっていないようだ。
「何って、誕生日のお祝いだよ。ほら、座って」
「う、うん」
椅子を引いてあげて、愛里を座らせる。テーブルの上には、ろうそくに火が灯されたバースデーケーキ。
「このケーキ、沢野君が焼いたのよ。すごいよね、沢野君ってこんなケーキまで作れるなんて。愛里ちゃんが羨ましくて仕方ないわ」
「お兄ちゃんが? 私のために?」
西畑の話を聞いて、愛里は僕を見て、ケーキを見て、また僕を見た。
「本物のリュンタルのことで、愛里にはいろいろ気を使ってもらったしさ。何かお返しがしたかったんだ」
きちんと言おうとすると、なんだかちょっと恥ずかしい。
でも、これは必ずきちんと言わなければならないことだ。
「それで思ったんだけど、愛里は誕生日が十二月二十五日だから、いつも誕生日とクリスマスがごちゃまぜになったお祝いになっていただろ? プレゼントやケーキもひとまとめにされちゃったりさ」
「う、うん」
「だから、ちゃんとした誕生日パーティーをやろうと思って。クリスマスパーティーはリュンタルでやったから、今度はリアルで、クリスマス抜きの、愛里のための誕生日パーティーをやろうと思ったんだ」
「愛里ちゃん、ほら、ろうそく、消して」
パーティーの主役に、玻瑠南が促す。
十三本のろうそくが立てられたケーキを前に、愛里は立ってテーブルに手を置き、身を乗り出した。
そして。
思い切り吹きかけた息は、それでも全部のろうそくを消すことはできず、ふっ、ふっ、と追加の息を吹きかけて、やっと全部のろうそくを消すことができた。
「おめでとーーー!」
改めてみんなで愛里の誕生日を祝い、拍手をした。
「ちょっと、失敗しちゃった」
愛里は立ったまま、少し顔を赤くして、小さく笑った。
「愛里ちゃん、これ、プレゼント」
智保がテーブルの下から箱を取り出した。両腕を回しても届かないほどの大きな箱には、きれいなラッピングが施されている。
「私も」
「私も、これ!」
玻瑠南と西畑も、ラッピングされた包みを愛里に差し出した。
三つのプレゼントを目の前にし、愛里は立ち尽くしたままそのプレゼントを見つめている。
「愛里、ちゃんと受け取らなきゃ」
「う、うん」
愛里は差し出された順にプレゼントを受け取り、それを椅子の横に重ね、席についた。
「ごめん、僕はケーキを作るのに忙しくて、プレゼントを買いに行く時間がなかった」
愛里はうつむいている。
「後で絶対にプレゼントするからさ、その、誕生日プレゼントなのに過ぎてから渡すなんて、本当はダメなんだろうけど、でも、絶対にプレゼントするから」
愛里はうつむいたまま、顔を上げない。
「愛里、その、怒らないでくれよ。あ、そ、そうだ、ケーキを食べようか」
ケーキナイフを手に取り、立ち上がる。
「お兄ちゃん……」
愛里の小さな声。まだ、うつむいたままだ。
「ケーキは自信があるんだ。きっとおいしいからさ、だから」
「お兄ちゃーん!」
突然、愛里が飛びついてきた。その勢いで飛び散りそうなほど、涙が頬を流れている。
「お兄ちゃん、大好き!」
「ちょっ、危ない、ナイフが」
「お兄ちゃんのバカ! 大好き!」
どっちなんだよ。
真っ赤な顔を涙で濡らして、愛里は僕を抱きしめて離さない。
「プレゼントなんかなくっていい! お兄ちゃん大好き! プレゼント絶対忘れないでね!」
だから、どっちなんだよ。
ケーキナイフを、テーブルに置く。
喜んでもらえた、ということでいいのかな。
僕もそっと愛里を抱きしめた。
なんだか照れくさいけど、たまにはこういうことがあってもいいのかもしれない。
「ただいまー」
玄関のドアが開く音と、お母さんの声。
「遅くなってごめんねー。からあげ屋さんでクリスマスのチキンが売れ残ってて。安くなってたからいっぱい買ってきちゃった。あとそれと、こうちゃん今日遅くなるんだって……あ、お友達が来てたのね。いらっしゃい」
リビングに入ってきたお母さんが、みんなに挨拶をした。
それはいいんだけど。
「お母さん! クリスマスはダメ! 今はクリスマスはダメ!」
僕は小声だけれども息を強く出し、両手を交差してバツを作ってお母さんに注意した。
でも、お母さんの目にも耳にも、僕の注意は届かなかった。
「あいちゃん! ねえあいちゃん、どうしたの?」
お母さんには、泣きじゃくっている愛里の姿しか見えていない。
「ひょっとしてりっくん? りっくんがあいちゃんを泣かせたの?」
「ち、違う! 違うって。ぼ、僕じゃない。ちょっと、みんなからも言ってくれよ!」
「私、立樹が愛里ちゃんを泣かせたのを、しっかりと見ましたー」
「私も、沢野君が愛里ちゃんを泣かせちゃったのを、間違いなく見ましたー」
「あたしケーキ切っていいかな」
「りっくん!」
「違うって! 誤解だよ! 誤解だから!」
さすがにまずいと思ったのか、お母さんに事情を説明する玻瑠南と西畑。
勝手にケーキを切り始めた智保。
そして、
「本当に、ありがとう、お兄ちゃん」
ようやく泣き止んだものの、まだ僕から離れない愛里。
こんなに喜んでもらえるなんて、思っていなかった。
でも、それよりも、
「僕のほうこそ、ありがとう、愛里」
愛里がいたから、愛里が僕を思ってくれていたから、僕は立ち直ることができた。
愛里に感謝の気持ちを伝えることができて、本当に良かった。
「ケーキ、切ったけど。
「お母さんももらっていいの? じゃあ、お母さんも食べようかな!」
今度は勝手にケーキを皿に取り分け始めてしまっている。
いつまでも抱き合ってはいられない。
「お母さんも食べていいけど、智保、ちょっと待って。愛里のためのケーキだから。ほら、愛里、席について」
やっと僕から離れた愛里が、席に戻った。
そして、みんなの前に、ケーキとジュースが置かれた。
「じゃあ改めて。愛里、誕生日おめでとう! 乾杯!」
「かんぱーい!」
すっかり泣き止んだ愛里が、笑顔でジュースを飲み、そして僕が焼いたケーキを食べている。
「おいしい! お兄ちゃんが作っただけのことはあるよ。本当においしい」
「ありがとう」
サプライズ誕生日パーティーは大成功だ。こんなにうれしいことはない。
喜ぶ愛里の笑顔を見ながら、僕もケーキを一口食べた。自然と、僕も笑顔になった。
「いけない、すっかり忘れてたわ! クリスマスのチキンも食べ」
「お母さん! クリスマスは忘れて! 今だけは忘れてー!」