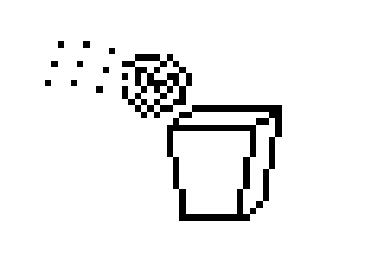4−3: ウィンドウ
「大したことじゃないんだ、」
イルヴィンは手前のディスプレイに目を戻した。
「本当に大したことじゃないんだ」
ディスプレイの二つの数字を指差した。
「トムの運が悪かったのか。俺の運が良かったのか。それとも二人とも運が悪かったのか」
左を向き、テリーを見た。
「だいたい、都市伝説じゃないか。君だって、だから楽しんで遊んでいるんだろ?」
「そうかもな、」
テリーはイルヴィンから目を逸らさずに言った。
「だから、何があったのか教えろよ。あんたは少しだけだとしても気になっているんだろ?」
右手の親指と人差し指で5mmほどの隙間を作り、イルヴィンの目の前にかざした。
イルヴィンは首を振り、答えた。
「右手が痺れたんだ、」
またディスプレイを指差して言った。
「このタイミングで。そしてトムは倒れた、」
右手の人差し指を突き出したまま前後に手をゆすり、ディスプレイを指差した。
「このタイミングで」
両手を机に置き、続けた。
「ただそれだけだ」
椅子を後に下げてイルヴィンは続けた。
「百数十だろ。20万のなかの百数十だ。たったそれだけで何かが起こるなんてことがあるのか?」
「20万で見れば、百数十で見れば、そうかもな」
テリーはマニュアルを閉じた。
「じゃぁ聞くが、サロゲートが、たとえばトムが、それともしかしたらたとえばあんたが、ここの20万ユニットだけに繋がっていると考える理由は?」
「それなら、世界中でその時に何ユニットがパージされたのか教えてくれよ」
テリーは両手を広げて答えた。
「できないんだ。マニュアルを見る限り、ここのことしかわからない」
右手の人差し指で下を指して続けた。
「R&Dのこともな」
壁の10枚のディスプレイを指差した。
「ユニットのこともな。交換ユニットはどこから来る? パージされたユニットはどこに行く? あんたは見たことがあるか? このセンターの廃棄物の所にユニットがあるのを見たことがあるか?」
「聞いたことはあるか?」
イルヴィンは両手で一辺が10cmほどの空間を包んだ。
「ユニットがどういうものなのか」
「脳の部位という噂以外はよく知らないな」
「R&Dに入って行く連中とすれ違ったことがある。その時に連中は『マトリクス』と言っていた」
テリーを見てイルヴィンは続けた。
「聞いたことがあるか? ユニットのマトリクスの話を」
「いや、ないと思う。帰ってから調べれば見付かるかもしれないが」
「トムが言ってたんだ。ユニットの基盤のようなものには蛋白質のマトリクスがあるって」
「タンパク質のマトリクス?」
「あぁ」
イルヴィンは空間を包んでいた両手を開き、左手を広げた。
「ユニットの基盤には導電性のタンパク質の端子がいくつも並んでいるって。そこから信号を出しながら、タンパク質を成長させながら、神経細胞を成長させながら、神経細胞の集りの適切な箇所に接続するんだそうだ」
左手の上に右手を乗せ、指先をすぼめながら右手を上げて見せた。
「その基盤は、ユニットの端子へと結線されているってな」
イルヴィンは両手を広げた。
「全部、マトリクスという言葉からトムがでっち上げたことかもしれない。ただの冗談としてな」
「あるいは、トムはそういう話を聞いたことがあったのかも」
イルヴィンは首を振った。
「どっちにしろ、わからないことだ。だいたい、どっちが簡単だ? 人工知能の技術が発達したのと、R&Dで脳の部位を培養するのと」
右肘を机につき、イルヴィンはテリーを見た。
「結局、噂なんだよ。君も、この噂が本当なのかどうかは興味がないんだろ? 研究所での活動を聞く限りでは」
「あんたがそれでいいならな。トムが倒れたことも、あんたの右手が痺れたこともただの偶然。それで納得できるならな」
「納得か」
「あぁ、納得だ。今後何かが起こるかもしれないなんてことは考えもしない。ただの偶然だった。一回健康診断を受ければそれで済むってな」
イルヴィンは息を吐いた。
「そうだな。健康診断で充分だ。脳がどうのこうのと言うなら、そこを見てもらえば済むことだろう? 俺がそうだというなら、俺の脳に何かがあるだろう。何もなければ、全部噂なのかもしれないし、少なくとも俺はそうじゃないってことがわかる」
テリーはイルヴィンの横顔を見ていた。