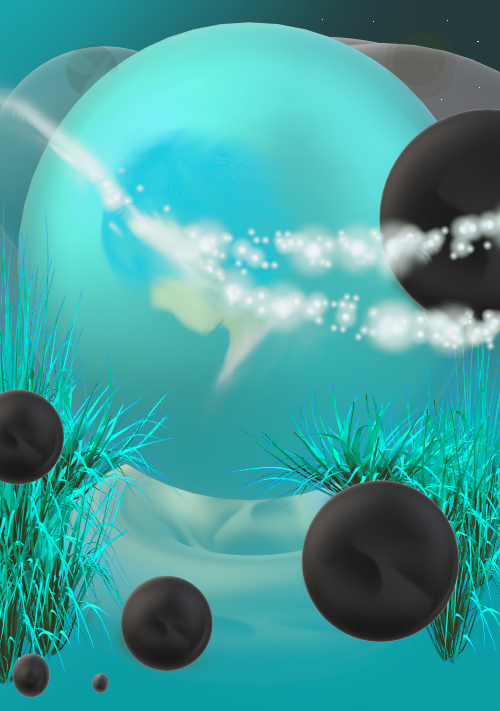月流し.2
その草原は、赤い……。
どこまでも
いっけんには、自然そのままの原野から樹木をとっぱらっただけに見える雑草
わけあって背の高い植物が根づきにくく、雨に見まわれようと
見る目をそなえ、その異質さを感知する者には、奇怪な側面を見せる土地。
セレグレーシュがその地面を行けば、他者の血が染みこんだ糸や葉脈、樹形のようなものに
踏まれた存在が、その苦痛に
ともすれば身の丈のはるか上にもおよぶ、そういった空域に迷いこんでしまった感覚…――悪酔いするのにも似た幻想的な予感にのまれそうになる土地だ。
現実には、その大地に
一〇〇〇年あまり続く平穏が、その事実を証明している。
永遠に
けれどもそれは、あまりにも
いつの日か、突然の怪異に襲われそうな予感をおぼえてしまうセレグレーシュとしては、どうしてもなじめない。腰が落ちつかなくなる一帯だった。
《法の家》は、そんな怪しい土地のただなかに位置し。
もとの敷地の高さのままに残された内苑を中央に囲いながら、こんもりと。
ドーナツ状に土が盛られて形成された人工の丘陵に
二年前は、恐る恐る踏みだし…――いてもたってもいられなくなって、全力で走りぬけた草地。
とにかく嫌なところだった。
けれども試験の待ちあわせ場所として示されたのは、そのただっぴろい緑の草原の中に、ぽとぽとと散らばっている円形の植物の小山。
どの方面に向かうものだろうと、一次考査は、だいたいそこが始点とされるという。
《転移法印》は、みだりに使わないというのが定式(特例がないわけではない)なので、《法の家》の外に出ようと思えば、嫌でもこの
待ち合わせの目印としてあげられた《空白の円》とは、《
魔封じの
一般には、
抑圧的な法則で拘束された大地に点在する術のほどこされていない部分であり、
ひっくるめて《円》と呼ばれてはいるが、形成の目的と手順を異にし、ときに《
内部に踏みこめないほど植物が
セレグレーシュは、この丘を歩いていると、ぽつぽつと、とり残されてあるその樹林の中(ちょっとやそっとのことでは内部に侵入できないので、明確には表層上面)へ、逃げこみたい衝動にかられるのだが……。
集合場所は、あくまでも、その中や上ではなく
だから、しかたなく…――。
その緑深い植物の小山の手前——これと示された円の北側で、不安そうに肩を
視界に広がる一面の大地。
現実にどれだけの個体が封じられているのか……。
確認したいとも思わなかったが、それが一体や二体ではなく、けっこうな数にのぼることをセレグレーシュは感じとっていた。
くわえて、これといえる
大昔に
この丘は、いまでは法印技術の
初期の
《適性考査》を目前にした
待ちあわせ場所におもむいたセレグレーシュは、自分の胴より太く厚みのあるリュックを肩にひっかけたまま、おろそうとはしなかった。
できるだけ妖威の密度が薄そうなすきまを選んで、つま先や
ほんとうは、きちっと固まって見えても、人血が染みこんでいるように思える地面には、足はもとより荷物も乗せていたくないのだったが……
彼は、気もそぞろに足もとを意識しながら、試験に同行する者が