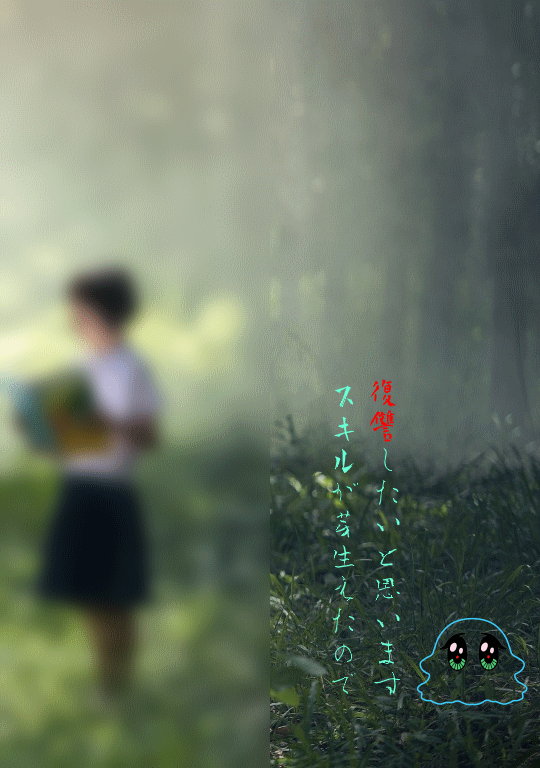54
今更ですが……
『恋愛』から『ファンタジー』にジャンル変更します。
恋愛系のお話しが少ないとのご指摘を多々いただきまして……
寛大なお心でご了承くださいませ。
志波 連
イーサンが肩を竦めてシェリーの座ったソファーの正面に腰かけた。
「僕があれからどうしていたかを話そうと思ったんだ」
シェリーは黙って頷いた。
「自暴自棄になって領地に引っ込んだ僕の元に、エドワードさんが訪ねて来たんだよ。剣士なら誰でも知っている『黒狼』だ。もちろん話を聞いたさ。するとまるで訳の分からないことを言い出したんだ『数日後に王妃からの使いが来る。ブラッド家嫡男に招集令状が出るから、身代わりを申し出ろ』という内容だと言うんだよ。面食らっていたら今度はブルーノがやってきてね」
仲良しの弟の名前にシェリーの心が跳ねた。
「三人で話し合ったよ。結局僕がブルーノの代わりに出兵することにして、バローナ国へブルーノが作った薬を秘密裏に届けることになった。準備もあるから一度王都に戻ったら王弟殿下が来られて説得されたけど断った。あの段階では誰が誰の味方なのかわからなかったからね。でも僕としては君の安全が第一だったから……」
シェリーはギュッと掌を握った。
「うん、その話はサミュエル殿下から聞いたわ。あなたらしいって思ったの。だから疑いもしなかった。それにしてもブルーノはそっち側だったのね」
「君に悟らせるわけにはいかないだろ? そこは責めないでやって。あの時点ではアルバート殿下の動きは把握していたんだ。ローズ嬢の状態も分かっていたしね」
「アルバート殿下と王妃は、もう仲間だったということ?」
「いや、仲間ではないな。同じ目的を持っているのだとお互い認識していた程度だよ。何より王妃が辺境伯には見放されていると思っていたからね。まあ、今もそう思っているだろうけれど」
「なぜ?」
「辺境伯が……救いの手を差し伸べなかったからだ」
「どうして助けなかったの? 実の妹でしょう? しかも随分齢が離れた末妹なのに」
「領地を離れるわけにはいかなかったそうだ。ロナードが怪しい動きをしていたからね」
「それにしても……」
「そして僕は戦場に向かったことにして、替え玉と成り代わったんだ。彼は前の戦争の時一緒だった。彼は僕の命の恩人さ。僕を逃がそうとして怪我をしたんだ」
「まあ! そんなことが?」
「うん、彼にはシルバー侯爵家の領地に来てもらっていたんだけど、教会の下働きではなく子供たちに字や計算を教えてもらっていた。その時に出会った女性が奥さんだよ。彼らは詳しい事情は知らないけれど、僕の替え玉になることを了承してくれた」
シェリーは黙ったまま話の続きを促した。
「僕は戦争で行方不明ってことになって、その通りの報告が為されたはずだ」
「ええ、そう聞いたわ。アルバートが酷く狼狽えて、私を慰めようと必死だった」
「そうなの? 彼は……優しい?」
「ええ、とても気遣ってくれるわ」
「さっき……彼を信じて着いて行くと言ったね」
「ええ、そう言ったわ」
「僕との未来は……無い?」
「イーサン?」
「ははは……ごめん。未練がましいね……ごめん、ホントごめん」
「イーサン、私たちは引き裂かれるような形で別れたでしょう? 心が残っていて当たり前だし、私も時間が戻せるならと何度も考えた。でもね……私はもうアルバート・ゴールディの妻なの。これが現実なの」
「そうだよね、うん。それでこそ僕の愛したシェリーだね。ごめんね、こんな時って男の方が未練がましいって言うけど本当みたいだ。うん……ちゃんと振ってくれてありがとうシェリー……明日から死ぬ気で頑張らないといけないって思ってさ……どうしても確認したかったんだ」
「うん……イーサン……ごめんね」
「絶対に成功させましょう、皇太子妃殿下」
「ええ、国民の暮らしのために死力を尽くしましょう、シルバー卿」
イーサンがスッと立ち上がり最敬礼をした。
その姿にシェリーも渾身のカーテシーで応える。
涙を堪える二人の横で、レモンと戦闘メイド二人が目を真っ赤にしていた。
部屋を出たイーサンの足音が遠ざかる。
レモンから差し出されたハンカチで、シェリーは自分が泣いていたことに気付いた。
「そもそも攫われてきたんだもの。荷造りなんて必要ないわね」
「着替えは用意して貰ってますものね」
シェリーとレモンは顔を見合わせて笑いあった。
ジューンとジュライが移動用の服を持ってきた。
レモンは辺境伯軍の騎士服だ。
「私は騎士服ではないの?」
ジュライが無表情のまま応える。
「妃殿下に合うようなサイズはございませんので、こちらで」
差し出されたのは王宮の侍女服だった。
「なぜこれがここに?」
ニコッと笑っただけで答えは無い。
シェリーは肩を竦めて侍女服を受け取った。
シェリーとレモンは早めにベッドに横になることにした。
少し離れたベッドに座ったレモンに話しかける。
「ここにきてふかふかのベッドは初めてなのに、今日が最後なのね。慌ただしいこと」
「やっとゆっくり眠れますね。どうぞ安心してお休みください」
「あなたもね」
レモンはニコッと笑って頭を下げた。
眠ろうと思ってすぐに眠れるほどシェリーは図太くない。
レモンの寝息も聞こえない。
暮れなずむ空を見ながらシェリーはイーサンのことを考えた。
どれほど悲しかっただろうか……
どれほど傷ついただろうか……
どれほど絶望しただろうか……
その答えを知っているのはイーサンとシェリーだけだ。
それでも明日はやってくるし、この国に暮らす人々の生活は守らなくてはならない。
シェリーは小さな溜息を吐いて目を瞑った。