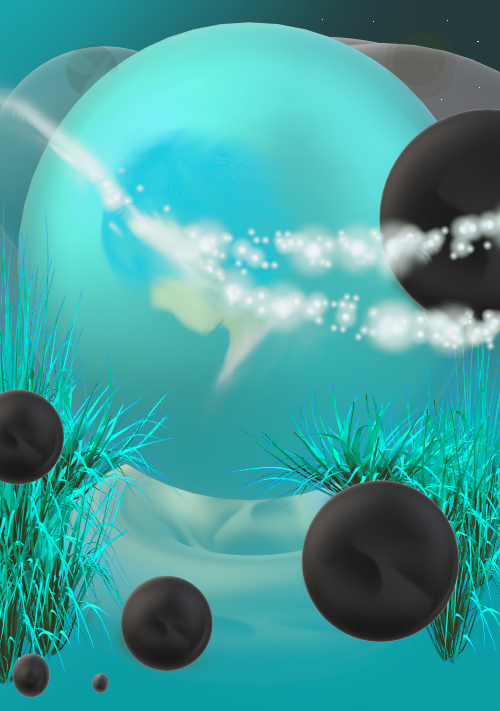第七話 プレリュード・フィズ
今は、深夜の3時を少しだけ過ぎた時間だ。
バーシオンの営業時間は終わって居る。始発が動き出してから、日が落ちるまでがバーシオンの営業時間だ。
「マスター」
男が、バーの入り口からではなく、バーシオンの従業員が使う出入り口から入ってきた。
「なんだ?」
「ごめんね」
何に対しての謝罪なのかわからないが、男はマスターに謝罪の言葉を告げる。
いつもと違う雰囲気の男に、準備をしていたマスターは手を止めて、男を見つめる。
「いい。それで?仕事か?」
「仕事といえば、仕事だけど、今回は別口」
男の言い淀んだ口調に、マスターは違和感を覚えて、聞き直した。
「別口?」
「僕のスポンサーの一人」
男とマスターの繋がりは、バーシオンの裏稼業に関係することだけだ。しかし、マスターも男の生業を知っている。
「あぁ・・・。(表の)仕事関係か?」
「そ、だから、僕は、この後、消えるけどいいよな?」
マスターに客を引き合わせるときには、男は同席するのだが、今回は同席ができないと言っている。
大きな問題は、依頼料だけだ。
「大丈夫だ。資料は?」
「持ってきた」
「紙か?」
通常は、電子媒体になっている。複写が容易にできてしまうが、破棄も簡単なために、情報の伝達に使われることが多い。
紙での伝達は、複写に手間がかかるし、破棄にも時間が必要だ。あまり使われなくなった手法だ。
「そ、ちょっと難しそうな案件でね」
マスターは、男が持ってきた資料を受け取って、パラパラとめくる。
全てを読む必要はない。必要な事柄は限られている。
「これのどこが仕事になる?」
読み込みはしていないが、情報の斜め読みだけで、マスターは仕事に繋がりそうな状況が把握できなかった。
新聞の切り抜きがはられている紙を見ながらマスターは男に言葉をぶつける。
「マスター。喉が渇いた」
「ん?水か?蛇口を捻れば出るぞ?」
「違う。違う。そうだ!少し、意味は違うけど、プレリュード・フィズ。お願い」
「時間外だ。それに・・・。そうか・・・」
男の注文に、マスターはプレリュード・フィズのカクテル言葉を思い出す。
「そう。プレリュード・フィズ。真意を知りたい。この場合は、”真実”って意味だけどね」
「わかった。でも、依頼主が期待できるような未来ではない可能性が高いぞ?」
紙に記載されている情報だけだが、マスターの受けた印象では、依頼主は加害者側だ。新聞や雑誌には、加害者側にかなり配慮した書き方になっている。このまま信じてしまうのもいいだろう。書かれている内容は、”優しい嘘”だ。
「それは、僕も思っている」
「もしかすると、真実が表に出ると、依頼主は全てを失う可能性もあるのはわかっているよな?」
「もちろん。スポンサーの一人を失うのは痛いけど、しょうがないよね。それに、傷を最小限に留める方法は、マスターが考えてくれるでしょ?」
「わかった」
マスターは、シェイカーを取り出して、カンパリ、カルピス、レモンジュースと氷を入れてシェイクする。一つの液体になった物を、グラスに注いで、ソーダで満たす。レモンをスライスして、グラスの底に沈める。
マスターは、コースターの裏に数字を書き込んでから、男の前においた。コースターを男の前に移動してから、グラスをおいた。
「プレリュード・フィズ」
「ありがとう」
男は、グラスを持ち上げて、一気に液体を喉に流し込む。
マスターがおいたコースターの裏側を見て、ニヤリと笑ってから、ペンを取り出してサインをする。サインを書いた後で、マスターが書いた3という数字に訂正線を入れて、5と書き直す。
飲み終えたグラスをコースターの上に戻した。
「さすがマスターだね。美味しかったよ」
男は、懐から、厚さが5センチはある封筒を取り出して、グラスの上においた。
バーシオンの従業員が使う扉から男は、明星が見える繁華街に姿を消した。
マスターは、閉じた扉をにらみながら、男が置いていった封筒を無造作に手に取り、いつも使っている部屋の箱に投げ入れる。箱の中には、同じように男が置いていった封筒が大量に入っている。
マスターは、店の扉がノックされる音で現実に引き戻された。
「どうぞ」
スーツをしっかりと着込んだ男性が一人、バーシオンの扉から入ってきた。
男性をカウンターの席に誘導した。
「君が」
男性がなにかを言おうとしたときに、マスターは手を上げて言葉を遮る。
「ここでは、注文以外では固有名は必要ありません」
「・・・。わかった。君たちの流儀に従おう」
「なにか、お飲みになりますか?ここは、”バー”です」
男性が眉間に寄せていた皺が、”ふっ”と緩んだ。
「そうだな。君に任せる。アルコールが強く、甘い物を頼む。娘が甘い物が好きだった」
「かしこまりました」
マスターは奥の棚から、バランタイン30年を取り出す。本来なら、このまま飲むのが筋なスコッチウイスキーだが、マスターはあえてカクテルの素材として選んだ。
ドランブイを取り出して、男性の前に並べる。
同量を、氷を入れたロックグラスに注いで、軽くビルドする。
「ラスティネイルです。強いので、ゆっくりとお楽しみください」
マスターは、カクテルとは別にチェイサーに氷を入れた水を用意する。男性は、黙ってグラスを持ち上げて、液体を流し込む。
ゆっくりと、見えない誰かと会話をしているように、一口一口、確認をしながら飲んでいく。
全ての液体を飲み終えてから、マスターが用意した氷が溶けてしまったチェイサーを一気に飲み干す。
「美味しかったです。マスター。ラスティネイルにも、カクテル言葉があるのですか?」
「ございます」
「教えていただけますか?」
「苦痛を和らげる」
「・・・。マスターもあの方と同じなのですね」
「私は、バーテンダーです。お客様が望まれる物を提供いたします」
「なら!」
「貴方が望む方法では、貴方が全てを失う可能性もあります」
「覚悟はできている」
「わかりました」
「いくらだね」
「チェックですか?席代は頂いておりません。2,500円です」
「それは・・・。そうだな。ここは、バーだったな」
男性は、1万を出して、グラスの下に置いて、立ち上がった。
「釣りは、あの方に、アルコールが強い、それこそ、火が着くくらいの一杯を飲ませてあげてください」
「承りました」
男性は、深々と頭を下げてからドアを開けて、明るくなっている繁華街に消えていった。
マスターは、看板のスイッチを入れる。
バーシオンは通常営業時間になり、営業を開始する。
夜の蝶や、夜の帳を楽しんだ者たちが、店に足を踏み入れる。
淀みを落とすように、一杯のカクテルを飲んでから、朝日が眩しい繁華街に消えていく。
10日後。
営業を終了したバーシオンの扉から、男が入ってきた。
「マスター。助かったよ」
「仕事をしただけだ」
「そうだけど、お礼は受け取ってよ。見事な落とし所だよ」
男は、椅子に座りながら、週刊誌をカウンターに投げる。
週刊誌には、有名女優の離婚が書かれていた。
表紙の端に、とある有名企業の”創立家族の爛れた関係”と、センセーショナルなタイトルで、家族間での愛憎が面白おかしく書かれた記事の見出しがあった。その中で、何も知らなかったのは、常に現場の最前線で企業の旗振りをしていた男性だ。記事は、男性に同情的な論調だが、男性が企業ばかりを見て、家族を顧みていなかったことが原因だと締められている。
男性は、企業の経営権を手放した。男性は、法に背いたわけではない。しかし、今のこの国では、許される状況ではなかった。