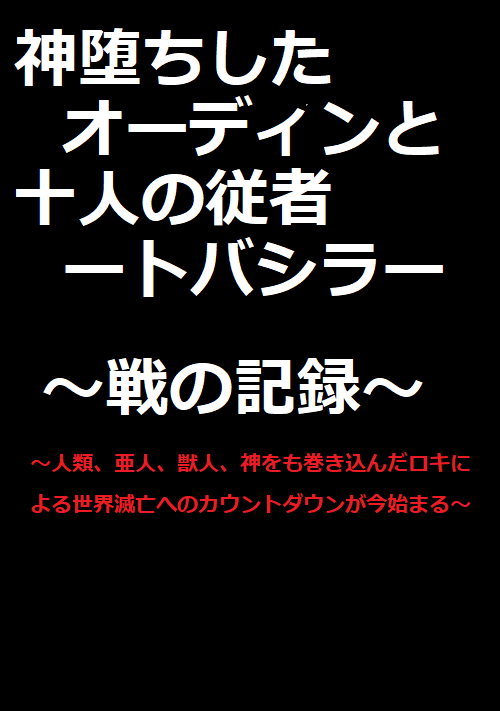第三話
上手く土ゴーレムを撒くことに成功したわたしたちは、先ほどわたしが身を隠していた、大きな葉が生い茂るコーナーにしゃがみ込んでいた。
ひとまず、ここで落ち着いて、作戦を練らないと。
「いい? 土ゴーレムの弱点は水。あんたの水魔法で、どうとでもなるわ」
「それくらい、知ってる……」
「じゃあ、さっさと……」
言いかけて、はた、と気づく。
こいつ、さっき、後先考えずに魔力を大量消費して、苦戦を強いられていたんだった。
正直、わたしが水魔法を使って倒してもいい──けれど、さっき風魔法を使ってしまった。風属性も水属性も使いこなせることがバレたら、悪目立ちしてしまう。それは避けたい。
なんとしても、クソガキに倒してもらいたいのだ。
「……俺は絶対、勝たなきゃなんねーんだ」
クソガキが、眉間に皺を寄せたまま、呟いた。
クソガキの魔力不足にわたしが気づいたことを、彼も察したようだ。
「理事長の息子で、でかい態度取ってるのに……! 魔力切れで試験に落ちたなんて、醜態晒すわけにいかねーんだよ……! 魔力がなくたって、俺がやんなきゃダメなんだ……!」
消耗しきった魔力。ノープランで土ゴーレムに向かっていく無鉄砲な姿勢──それでも、決して諦めようとはしない、意地。
生意気な態度の裏には、彼なりに背負いこんでいたものがあった。たとえ不器用にしか活躍できなくても、やらなきゃいけない場面で諦めるという選択肢は、絶対にない。
「あんた、やっぱり馬鹿ね」
「はぁ!? 喧嘩売ってんのか!?」
クソガキの両手を、わたしは掴んだ。
「なんだよ、離せ……!」
「……わたしの魔力を、分けてあげる」
「え」
クソガキの指に、指を絡めて、強く握った。
「お、おい、ちょっ……」
「黙って」
目を瞑る。わたしの魔力が手を通じて、クソガキへと伝っていく感覚がした。半分くらい与えれば大丈夫だろう──持病の『成長止め』は、見た目と体力に影響を与える病だが、魔力には作用しない。趣味と実益を兼ねた日々の鍛錬の甲斐あり、わたしは人並み以上の魔力を持っている。
予定した量の魔力を与え終わり、わたしは目を開けた。
──そこには、真っ赤な顔をして固まっているクソガキがいた。
「お前……っ」
「どう? これで魔法は使えそう?」
「えっ、あっ……」
握っていた手を離す──自由になった両手を見つめ、握ったり広げたりするクソガキ。復活した魔力を実感して、不思議そうな顔をしている。
「すげぇ量の魔力……」
「そう? 半分あげただけよ」
「これで半分……!? ほんとにお前、なんなんだよ……!?」
ズドォン! ズドォン!
「もう、ここもすぐ見つかるわね」
土ゴーレムの足音が近づいてきた。動きは遅いものの歩幅が広いので、逃げてもすぐに追いつかれてしまうだろう。
「なんでもいいわ。水魔法をあのゴーレムに食らわせてちょうだい」
わたしの言葉にクソガキが頷く──もう「指図すんな」とは言ってこないようだ。
「!」
黒い影がわたしたちに覆い被さった──振り返れば、土ゴーレムが、上からわたしたちを覗き込んでいる。
土で生成された拳がゆっくりと重い動作で、振り上げられた。
「【ウォーター・フォール】!!」
クソガキが唱える──土ゴーレムの頭上から、大量の水が出現した。
バッシャアアアア──!!
雪崩のように、水が土ゴーレムを叩きつけた。
土ゴーレムはドロドロとただの土に戻っていき──上から下に落ちる水はそのまま波となって、地の上を勢いよく這っていく。
「【ウィンド・パージ】」
洪水に巻き込まれる前に、わたしは風属性魔法【ウィンド・パージ】を唱えて、クソガキもろとも浮遊する。
「やったか……?」
クソガキが呟く。天井に頭がつかないギリギリの高さまで浮く──土ゴーレムのいた場所に大きな土の塊ができているのが見えた。そこを中心として円状に、水源を失った水がだんだんと失速しながら流れていく。
『──アン・デリックチーム、試験合格です。教室に戻ってください』
試験終了のアナウンスに、ほっと胸を撫で下ろす。
クソガキを見やると、力の抜けた子どもらしい表情をしていた。
……とにかく、第一関門突破かな。