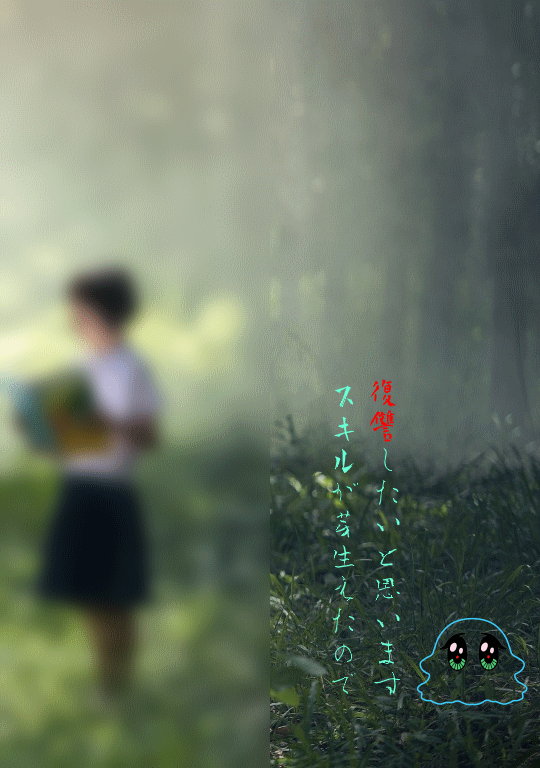二章の一 文花からお茶を誘われる。
朝から雨がひどい。毎日が自転車通勤の一華も、さすがにバスを利用した。
定時が十七時にあって、いつもだいたい、一時間から二時間の残業をする。だが、こういった雨の日に限って、仕事のスケジュールが噛み合わない。
納入に余裕があって、要は、暇だった。それなのに、梱包、運搬を主にしている次朗が忙しい。
次朗には、足の期待をしていた。次朗は、今ではあまり見かけなくなった、スポーツカー乗りである。
まあ、一華にとっては、車種に興味はない。足になれば、なんでもよかった。
仕事が終ったら電話するように、次朗にはきつく言っておいた。
一華が勤務している工場は、本社工場であるが、十年ほど前に縮小を余儀なくされた。北側にショッピング・センター、西側に住宅展示場とスポーツ・クラブが存在している。
縮小の際、広大な土地を切り売りしたようだ。
本社工場の正門前には、ショッピング・センターの駐車場があり、駐車場を横切ると、すぐにショッピング・センターへ入店できる。
あんまりにも、工場の正門が分かりづらくなっていた。知らない人がやって来ると、ショッピング・センターの駐車場内に、突如工場が現れたような
まだ雨は、止みそうにない。一華は、工場の正門を出て、すぐ先のショッピング・センターで暇潰しを考えた。
「お疲れ様。今日は、早いんだね」
思わぬ人物から話し掛けられた。文花が、正門の脇から近づいてくる。
一華は、正直なところ身構えたが、ここ最近の文花との接触が、身構えを半分くらいに減少させた。
「もう帰るの?」
なにかと文花は、絡んできた。ずっと一華は、文花を避けていたのに、気が付けば、こうして話すまでの関係になっている。
「ちょっと時間潰しをしようと、そこまでね……」
正直、話したくはなかったが、予定の行動を包み隠さず伝えた。
「じゃあ、お茶しよう」
やっぱり、誘われた。そうなるんじゃないかと、なんとなく予感はしていた。
文花と一緒にいるだけで、気が引けた。とにかく外見の差がありすぎる。工場内の作業着から、着替えての私服は、Tシャツにショートパンツで白の運動靴を履いていた。今からジョギングでもするのかと、自分で突っ込みたくなる出で立ちをしている。
一方の文花は、上下黒光りしたスーツに、ほんの少し高い、黒のヒールを履いていた。
確か文花は、今日も製造部巡りをしていて、工場内では作業着をあてがわれているはずだ。つまり、出社時と退社時しか着用しないスーツを、生真面目に身にまとっており、自然と清潔感が滲み出ていた。
王女様と使用人ぐらい、とまでは言い過ぎだとしても、あまりにも格差がありすぎる。
やはり、一緒にいたくなかった。一緒にいるだけで恥ずかしくなってくる。
そうは思っていても、流れは文花に握られていた。「じゃあ、お茶しよう」と促されて、
断る理由が捻出できなかったのだ。
ショッピング・センターに、次朗とやってくるときは、二階のフード・コーナーで暇を潰した。複数のテナントが軒を連ねていて、メニューだって豊富だ。何よりも、安くて親しみやすい。
しかし、流れを握っている文花は、端っから二階のフード・コーナーに行く気はなかった。一階のスターバックスに直行する。
恐らくは、お洒落云々の理由だろう。スターバックスが、お洒落かどうかは別として、文花の許容範囲に入っているのだと、一華は踏んだ。
店内はジャズっぽい音楽が流れている。やはり一華にとっては、お洒落に感じざるを得ない。
「コーヒー大丈夫?」
コーヒー屋さんに連れてきておいて、聞く質問ではないが、一華は、軽く二つ、三つと、首を縦にして頷く。
一華は、文花が注文する飲み物をなぞった。実のところ一華は、スターバックスに初めて入店していた。
四人席に、相対して座る羽目になった。
恐る恐る、文花の顔を見ると、自然とコーヒーを飲んでいる。文花のほうは、緊張などしていないだろうし、なんとも思っていないのだろう。
確かに間近で見れば、ケチのつけどころのない顔立ちだ。一つでも強引に挙げるとしたら、澄ましたときの顔の表情で、上唇が、なだらかな「M」の字になって、少し前歯を覗かせた。が、そこも人によってはアクセントになり、愛嬌に繋がるのだろう。
他にも、化粧や体つき、ふんわりと香る匂いなど、したくなくても意識させられた。もう、分析すればするほど、同性として嫌になる。
「前々から一華ちゃんとは、こうやって話したかったんだ」
文花の歯の浮くような台詞に動揺する。けっして悪くない気持ちと、何を言ってるんだと、拒否せねばという気持ちが
「私も、いろいろとね……」
一華は、ボソッと口ずさんだ。なんとか反発心のほうが勝った。
「この前、部長がね、一華ちゃんの話をしてね――」
文花は、止めどなく話しだす。間違いなく、話し相手が欲しいのだろう。またなによりも、一華の人材資源を活用したがっている。
一華の見立てでは、会社内の文花は、あまり人間関係がうまくいっていない。とりわけ悪く言う奴はいないが、評判といえば外見ばかりで、親しくなる者は見かけなかった。
文花の会社内の立ち位置が、そのままウィーク・ポイントに見えてきた。
一華は、文花の思惑等を、前々から薄々感じてはいた。だが、今に至っては、己の強みとして認識し始める。
転じて、攻めの意識が芽生えた。こうなったら、やってやる。こちらだって、聞きたい話や言ってやりたい暴言は、いくらだってあるのだ。
「腹が減ったから、二階へ行こう」
一華は、己のホームへと導いた。