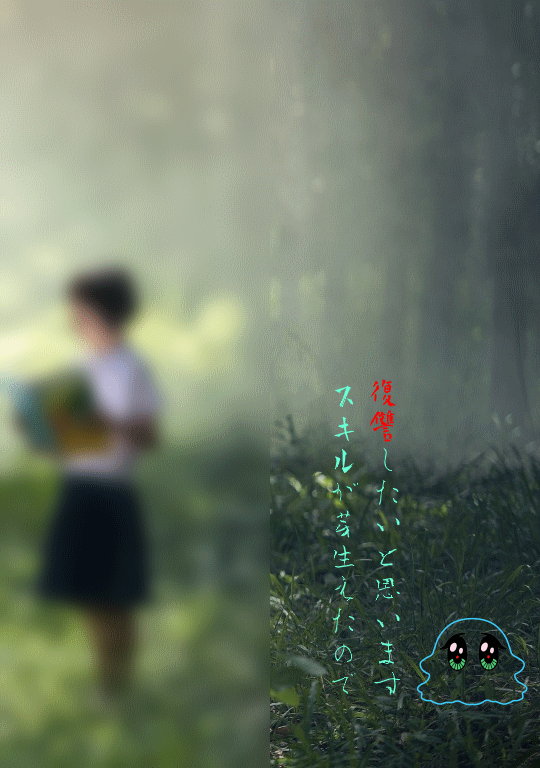執事コンテストと亀裂㉛
同時刻
その時藍梨は、伊達と一緒に原宿へ来ていた。
「人すごーい!」
そこには、立川に負けじと多くの人たちで賑わっている。 先刻伊達が言っていた通り、若者が凄く多かった。 今日はまだ気温が高い方のため、人の多さでより暑く感じる。
「まぁ、渋谷の方が人は多いと思うけどな」
伊達はそう言い、二人は駅から出て適当に街を歩き回った。 伊達と初めての休日で緊張している藍梨を、遠くから太陽が優しく照らしてくれている。
そんな太陽が、とても眩しく感じた。 だが歩いている最中頑張って彼に付いていくも、人が多過ぎてたくさんぶつかってしまう。
「あ、ごめんなさい・・・」
藍梨は東京の人ごみには慣れておらず、人とぶつかったりするなんて夏祭り以外にはあまり経験がなかった。
接触し謝っても東京の人は謝ってくれず、罪悪感だけが藍梨に残る。 そんな藍梨を見かねて、伊達が優しく声をかけてくれた。
「大丈夫?」
その言葉を聞いて、小さく頷く。 そう頷いてしまったが、頑張って人を避けながら歩くもやはり人とぶつかってしまった。
原宿には女子同士で来る人や、カップルがとても多い。 カップルにぶつかってしまうと、男の人が怖い顔をしながら藍梨の顔を見ては通り過ぎていく。
―――・・・何か、怖いな。
そんなことを考え油断していると、目の前から来た人と思い切りぶつかってしまった。
「いたっ」
その勢いでこの場に崩れそうになるが、伊達が手を伸ばし藍梨の身体を支えてくれる。
「いや、大丈夫じゃないでしょ」
そう言って、彼は少し笑った。 みっともない姿を見せてしまったことに、恥ずかしくて静かに俯く。 伊達は人が少ない場所まで誘導してくれ、藍梨と向き合ってこう口にした。
「手、繋ぐ?」
「え?」
躊躇いもない突然の発言に、少しドキッとしてしまう。
「もし藍梨が、今みたいに人とぶつかっても俺が支えられるように。 それと、俺たちがはぐれないように」
伊達は優しく微笑みながらそう言い、藍梨に左手を差し出した。 この行為はコンテストの練習でよくされているため、少しは慣れている。
藍梨は伊達の優しさを素直に受け入れ、彼の手に自分の右手をそっと添えた。 すると彼は、先刻よりも優しく微笑む。
そして二人は竹下通りへ来た。 ここは商店街なのだろうか。 若者がより多く、とても賑わっている。 まるで夏祭りに来ているようだった。
伊達は迷いもなく、竹下通りへ入っていく。
「この通りは女子中学生や女子校生がよく来る場所なんだ。 きっと藍梨も、気に入ると思うよ」
そう言って、二人は可愛い小物がたくさん置いてある雑貨屋さんに来た。 人が多くて奥までは見えないが、可愛らしいものがあるということはお店の雰囲気で分かる。
『入る?』と聞かれたので頷き、伊達が藍梨の前に立って道を空けてもらいながら奥へと進んでいった。 進みながら、飾られている小物をずっと見ていく。
大きなものや小さなものがたくさん置いてあった。 とても可愛くて見入ってしまうものがあるが、伊達はどんどん奥へと進んでいた。
「あっ、これ可愛い!」
藍梨は頑張って次々と流れていく小物を見ていると、今まで小物を見ていた中で一番可愛いストラップを見つけ思わず声を上げてしまう。
その声に伊達は気付き歩く足を止め、振り返って藍梨の近くまで寄って来た。
このストラップは鍵の形をしていて、鍵の中には色の付いた小さなハートがぶら下がっている。 とても可愛くて、一目見ただけで凄く気に入った。
このストラップをずっと見ていると、伊達は藍梨に向かって小さく呟く。
「それ、可愛いね」
その言葉に笑顔で頷くと、伊達は藍梨の目を見てこう言った。
「そのストラップ買う?」
その問いに少しの間考え、彼に向かってそっと口を開く。
「一緒にお揃いの買おう?」
この鍵のハートの部分は、5種類の色がある。 今日は折角伊達と原宿へ来たため、思い出を残しておきたかったのだ。
彼は少し躊躇っていたが、照れ臭そうにこう言葉を返す。
「うん、いいよ。 じゃあ俺は、青にしようかな。 藍梨はピンク?」
そう言いながらハートがピンク色のストラップを手に取り、藍梨の目の前まで持ってきて見せてくれた。
彼は藍梨の好きな色を憶えてくれていた。 そのことも踏まえ笑顔で頷くと、伊達と再び手を繋ぎストラップを持ってレジへと向かう。
「俺が奢るから」
そう言って二つまとめて払い、ピンク色のストラップを藍梨に渡してくれた。
藍梨は『自分のものは自分で買いたい』と言ったが、伊達は『大丈夫だよ』の一点張りで言うことはを全然聞いてくれず、結局は奢ってもらう形となる。
伊達には感謝をしていた。 このストラップをどこに付けようかと話し合った結果、学校のバッグに付けることになった。
それからは人ごみに慣れたのか、買い物がスムーズに進みとても楽しい時間を過ごすことができた。
ふと携帯を見ると、そろそろお昼時。
「お腹空いたなぁ・・・」
そう小さく呟くと、伊達は藍梨の言った言葉が聞こえたようで優しくこう言ってくれた。
「どこかへ入る?」
「私、あまり食べられないと思うから・・・」
その言葉に首を横に振りながらそこまで言いかけると、彼は何かを察してくれたようで藍梨をフォローするように言葉を発した。
「あぁ、そうだったね。 藍梨は少食だっけ。 じゃあ・・・」
そう言うと伊達はしばし黙り込み、突然何かを思い出したかのように声を上げる。
「あ! そうだ、じゃあクレープでも食べる? この通りで、有名なクレープ屋があるんだ」
そして伊達は、藍梨をクレープ屋まで連れていってくれた。 流石に有名ということもあり、人もたくさん並んでいる。 二人は最後尾に並び食べたいクレープをそれぞれ決めた。
―――どれも美味しそうだなぁ。
クレープの種類はたくさんあり、迷ってしまう。 フルーツだけでなく、サンドウィッチみたいな野菜や肉を使ったクレープもあった。
―――流石にこれは量が多くて食べ切れないな。
―――私はフルーツのものにしよう。
色々と決めていると、藍梨たちの番が来てそれぞれ注文する。 クレープ代も伊達が払ってくれた。 そんな彼の行為に、藍梨は申し訳なく思ってしまう。
「ありがとう」
クレープを受け取り、二人は人通りが少ないところまで行きそこでクレープを食べた。 今いるこの通りはお店がないため、休んだりしている人が多く見受けられる。
藍梨たちも、さりげなくその中に加わった。
「美味しい!」
「そう? よかった」
伊達は安心した顔をしながらそう返す。 伊達と一緒に食べるクレープはとても美味しく、とても甘かった。
この時の藍梨は、本当に幸せな時間を過ごせたと思う。 それはやはり、結人のことを考えていなかったからだろうか。
結人のことを考えるだけで、いつも胸が苦しくなってしまう。 だけど今は、藍梨の目の前にいるのは伊達だ。 結人ではない。
だから今は伊達のことだけを考えていればいい。 今もなお二人を照らしてくれている太陽は、そんな藍梨を励ましてくれているかのように思えた。
そして――――“大丈夫、藍梨は一人じゃないよ”と、囁いてくれているような気もした。