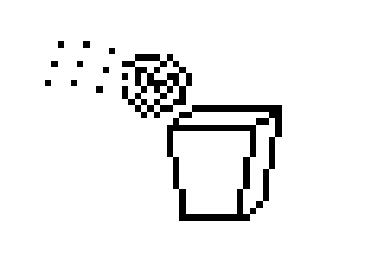3−5: サロゲート
「ユニットの大きさについてはどうなの、テリー?」
「さぁ、どうかな、」
ウェブ表示が変わり、「ユニットのサイズ」というタイトルが中心に来た。
「見てみよう」
それは、脳が分解されていることに加え、一辺が10cmの立方体、そして一つの面には、電気信号用の端子が一組、栄養と酸素のためのチューブが一組あるという内容だった。
「これは案外正確かもしれないな。これは関係者の誰かが漏らしでもしたのか?」
イルヴィンが呟いた。
「いや、それはわからない。イルヴィン、いいか、こういうので大切なのは、わからないものはわからないままとして扱うことだ」
「そうなの。人間の認識の形態は限られていて、しかもその機能は暴走してるって言ったわよね?」
エリーはイルヴィンの横顔を見た。
「これに限らないけど、テリーが言ったとおり、『わからないことはわからないままとして扱う』ことが重要なの。でも、それは人間の認識の形態の本態にも反することだし、その本態が暴走している現在はなおさら、そのあり方に反することになるわね」
「ああ、そういうものか。それをわかるとは言えないと思うけど」
イルヴィンはピザに手を伸ばした。
「それで、サロゲートの話は?」
「じゃぁ、今度はそっちだ、」
テリーが言った。
「『根拠がありそうに見える不可解な話』の一覧で、知能サービスに関連するサロゲートの話のみを残してみよう」
一覧が表示されていたウィンドウが前面に現われ、いくつものタイトルが消えた。三人は一覧を眺めていた。
「『サロゲートの存在理由』っいうのはどう? これのウェブを」
TVには「サロゲートの存在理由」というタイトルが中心に置かれたウェブが表示された。
「それを読んでみよう」
テリーに応え、ウィンドウにその内容が表示された。その内容は、知能サービス・ユニットが遠隔操作するサロゲートがあるというものであり、とくに、夜間の徘徊の話だった。
「深夜の徘徊か。話にはなりそうなものだが。真偽はともかく、今参考にするのは、トム・ガードナーだとしよう。だとすれば、必要なのはサロゲートは人に混じっているという類いじゃないかな」
「そうかもね。ウェブをもう一度検討してみましょう」
表示されたウェブをテリーは眺めた。
「ちょっと待ってくれ。トムとは関係しないかもしれないが。『サロゲートからのフィードバック』を見せてくれ」
表示された内容を三人は読んだ。
「この着眼点もあるのか。知能サービスのユニットが脳なら、サロゲートからのフィードバックを与えて計算を補正する」
「脳、あるいは脳の部位がただ計算しているだけだと、誤差がでるかもしれないわね」
「そんな必要があるのか?」
イルヴィンはドリンクを飲んでから聞いた。
「どうかしら。部位に分割されているから違うかもしれないけど。例えば夢で空を飛んだりっていうこともあるんじゃないかと思うけど」
エリーがイルヴィンを見て答えた
「もし、その夢が覚めなければ、飛べるのが当たり前になるかもしれない。でも、もし知能サービスの計算結果がそれに基いたものになると、たぶん困るわよね」
「たぶん困るだろうな。だけど、それだと、深夜の徘徊でもかまわないんじゃないか?」
イルヴィンはそう答えた。
「体を動かすとか、常識的な物理的な運動については深夜の徘徊でもかまわないだろう。だけど、脳の活動はそれだけじゃない。視覚、聴覚、言語なんかもある。特に言語だな。これは深夜の徘徊だと難しいだろう」
「すると、サロゲートは人に混じっていないと、フィードバックの面からも意味がないってことか?」
「そうなのかもしれない」
イルヴィンの問いにテリーが答えた。
「なら、フィードバックを受ける方はどうなってる?」
「それは、」
イルヴィンの問いを聞き、テリーはウェブを眺めた。
「『ユニットの修正』を中心に」
テリーは端末に、あるいはTVに言った。TVはそれに応えて表示を変えた。
「『ユニットの集積体』を見せてくれ」
テリーのウィンドウに内容が現われた。
「これだと、一人分の部位の集積がサロゲートを制御している。ただし、それは生物学的に一人分とも限らず、一人分の部位の集積とは言っても一つの部位が複数含まれていて、分量としても一人分とはかぎらない。イルヴィン、どう思う?」
テリーはもう少なくなったピザに手を伸ばした。
「どうと言うと?」
「トムのことに決まっているだろう。トムは普段どうだった?」
イルヴィンはしばらくTVを眺めていた。
「これと言ってないな。ユニットのパージは多かれ少なかれ毎日ある。だけど、トムに何か影響があったようには見えなかったな」
イルヴィンはドリンクを飲み、缶を振り、袋に戻した。
「そこも気にする必要があるかな。もし人に混じっているのだとしたら、サロゲート個人、いや個人と言っていいのかはわからないけど、ともかく個人にとっても、周囲から見る際にしても、自己同一性の保持は問題になるだろう。イルヴィンがトムをトムとして認識し続けていたのだとしたら、そしてトムがサロゲートだったのだとしたら、自己同一性の保持も必要なはずだ」
テリーの言葉を聞きながら、イルヴィンはまたTVを眺めていた。
「えーと、つまり…… 結局都市伝説ということなのかな?」
「いや、そういうわけじゃない」
テリーはピザを口に運びながら答えた。
「まず、知能サービスのセンターはあそこだけじゃない。それと、一人分の脳の集積は部位ごとに多重化されているとしよう」
「それで?」
イルヴィンは最後の缶を取り出した。
「こういうことね。ある部位のユニットがパージされても、それは多重化されたものの一部だから、サロゲートに影響が出るとは限らない」
エリーが答えた。
「そう。分量としても一人分とか限らないとうことは、部位ごとに多重化がされているかもしれない。それを普通の計算機や、あるいは知能サービスで補完してやれば助けにはなるだろう。だけど、多重化してあれば、パージされたユニット以外のユニットの計算を元に学習できるかもしれない。それなら、パージがあっても自己同一性は保持しやすいかもしれない」
エリーの答えでは不充分と感じたのか、テリーは説明を付け加えた。
「かもしれないが多いな」
イルヴィンはドリンクを飲んで言った。
「そりゃそうだ。だけどトムの時には、何か問題が起きた」
「サロゲートが突然倒れたという都市伝説はないのか?」
TVのイルヴィンのウィンドウに現われているものには、タイトルからはそれに該当するものはないようだった。
だが、軽度の記憶障害や、体の痺れという項目があった。イルヴィンは昨夜の右手の痺れを思い出したが、それを口に出すことはできなかった。
「だが、結局は都市伝説なんだろう?」
イルヴィンは、それだけを言った。