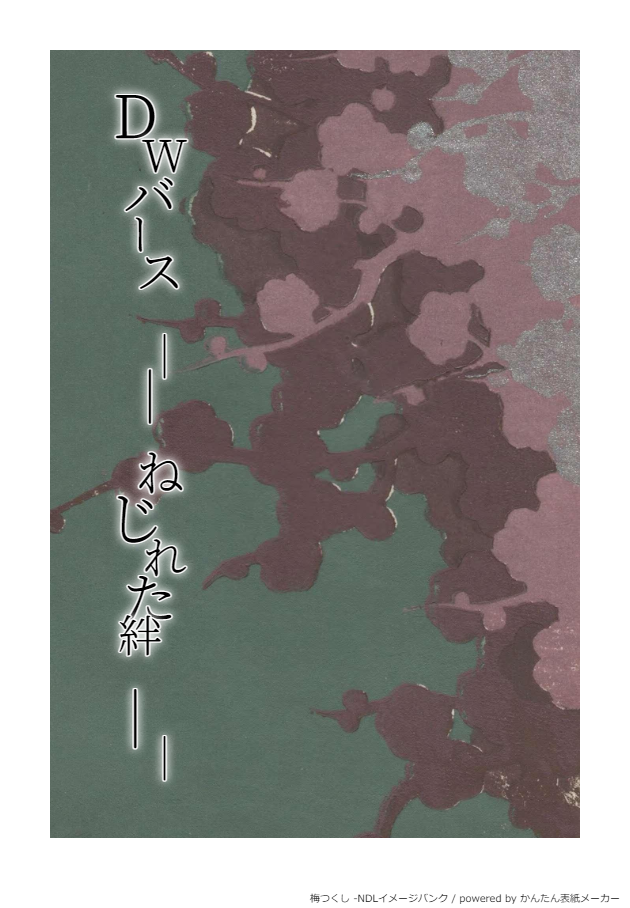【五十四】Sランク探偵の新生と大切なバディ
今では、捜査資料の整理や、青波さんとのやりとりも、僕は任せられている。
ただ朝は、僕は起こされる側に戻った。早く起きた山縣は、朝食を用意してから、僕を揺り起こす。
山縣はとにかく僕を可愛がり、僕を甘やかしている。
僕は思わず赤面する事が多い。いい歳の僕の頭を撫でるクセは、特にやめてほしかったりするが、山縣が喜んでくれるならいいかと、僕は拒否できずにいる。
「朝倉、ずっとそばにいてくれ」
「うん」
しかし……素直になった山縣の言葉と笑顔は、本当に破壊力が高い。
大切にされすぎて、僕はたまに苦笑してしまう。
――探偵ランキングと探偵ポイントは、四月に更新されるのだが、速報として、十月にも一度、その時の状況が発表される。
僕はドキドキしながら、結果の通知が届いたので、探偵機構の連絡用アプリを開いた。
そこには、探偵ランキング一位、探偵ポイント一位、暫定Sランク、山縣正臣と記載されていた。目を丸くし、僕は隣にいた山縣の服を引っ張った。
「山縣、やったよ! おめでとう!」
僕が画面を見せると、最初興味がなさそうにしていた山縣だが、大喜びで満面の笑みの僕を見ると、薄く笑った。それから誇らしげに言った。
「朝倉の望みは、俺は何でも叶えたいからな」
そういうと、山縣が僕の頭をまた撫でた。
僕は、幸せでたまらない。
別に山縣が、Sランクの探偵じゃなくても、そう――ダメなままでも、僕はきっとそばにいた。けれど、今の生き生きしている、自分を取り戻した山縣の方が、僕は好きだ。
その後も僕達は、ペット探しから、殺人事件までをも引き受けつつ、毎日ともに、探偵と助手として、仕事に臨んだ。
僕達は、その後、メディアにも取り上げられるようになった。
なんだか、照れくさい。
そんな日々は幸せで、僕は山縣と、今後もずっとそばにいたいいと思った。
DWバースという、抗えない世界がもたらした関係性からの開始だったけれど、助手という立ち位置を超えて、僕は、山縣正臣という人間を大切なバディだと感じている。
もう、山縣をダメだなんて思わない。
僕に惜しみなく優しさを注いでくれる彼は、確かに僕だけの探偵であり、絆を見つけてくれたのだから。