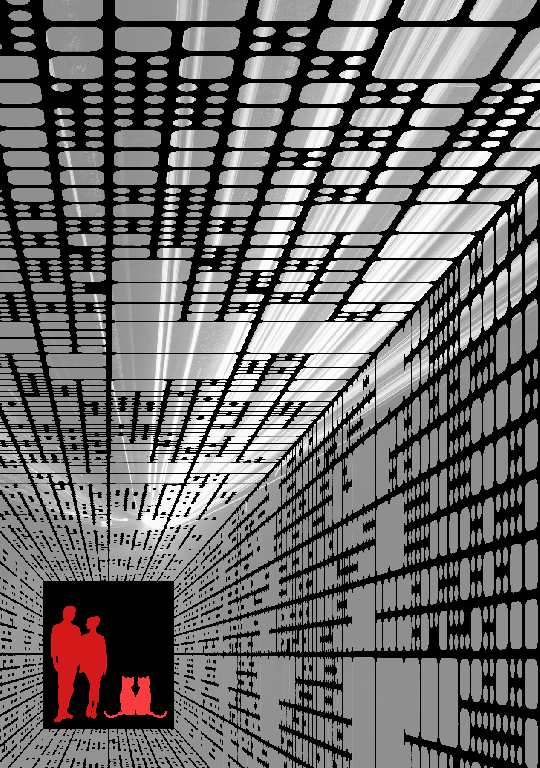10 守りたい、小さな命
地面の上で眠ってしまっている生き物を、しばらくの間ディータは見つめていた。
彼が逡巡しているのがわかる。当然だ。この生き物が一体何なのかはわからないけれど、こんなにも小さくて、無防備なのだ。
でも、もしかしたら大きくなれば人間に害をなすモンスターなのかもしれない。
私はこれが何のモンスターなのかわからないし、ディータも知らないようだ。
わかるのは、今のところ私たちにとって何の脅威にもなりえないということだけだ。
でも、それで十分だと私は思った。
「あ、あの……この子は、安全です!」
私は寝ている生き物をそっと抱きかかえてみせた。そんなことをしても、その生き物は鼻から「すぴーすぴー」という間抜けな音をさせて、起きる気配はない。
抱いてみると、それはずっしりと重さがあり、温かく、柔らかだった。
短く密集した毛が生えていて、独特の触り心地だった。
「ほら、こんなに、こんなに……可愛いですよ」
抱きしめていたら、胸に込み上げるものがあり、何だか涙が出てきそうになった。
人に害なすモンスターや食べるための生き物なら命を奪うのに、この子を殺めることはできないと、どうしようもなく思ってしまったのだ。
「イリメル、殺さないから! ただ、可能性を検討しただけで、俺もその必要はないと思ってるから!」
私が泣き出したことに焦ったのだろう。ディータが屈んで目を合わせ、慌てたように言った。
私も、ディータがこの子を問答無用で討伐すると考えていたわけではない。ただ、この子の〝命〟を感じ取って、胸がいっぱいになっていたのだ。
「とりあえず、ギルドへ持ち帰ろう。それで職員に判断を仰いで……そこから考えなくちゃな」
「そうですね」
火の始末をして、荷物を持って、私たちはひとまずギルドへ帰ることにした。
洞窟に不気味な声を響かせていた生き物は私が抱きかかえ、ディータが移動玉を発動させた。
足元に魔法陣が光るときに少し眩しそうにしたけれど、その生き物は起きる様子はなかった。
腕の中にすっぽり収まる、小さな命。この温かくて柔らかいものを手放すのが惜しいと、私は早くも感じ始めていた。
「さて、報告だな」
ギルドに帰り着くと、カウンターへ続く列に並び、ディータが少し緊張しているのが見て取れた。
たぶん、手応えもないまま依頼を終えてしまったことによる不安と、この生き物にどんな判断がくだされるのだろうかという心配で緊張しているのだろう。
それは、私も同じ気持ちだった。
朝出発したけれど、もう夕方になっていて、一日の終わりの報告ラッシュの時間は過ぎていたのか、私たちはそんなに待たされることなく順番が来た。
空いているカウンターならどこでもいいと思って並んでいたのだけれど、自分を私たちの担当だと思っているのか、あの眼鏡の職員が飛んできた。
「どうでしたか!? ヤバイのいましたか? 無事なんですね! よかったー」
私たちの姿を確認すると、異様にほっとした様子だ。そんなふうに出迎えられると思っていなかったから、私もディータも驚いてしまう。
「あの、実は……お二人を危ない依頼に送り出したことを上長に叱られてしまいまして……過去に、この手の依頼の詳細確認をせずに送りだした少人数パーティーが壊滅するという恐ろしい事件があったそうなので、今後はきちんと段階を踏んで依頼出しますので」
上長とやらにこってり絞られたのだろう。眼鏡の職員は平謝りだ。阿漕なことをするのに安全面には厳しいのだなと、少し不思議な気持ちになる。
「俺たちはこの通り、無事に帰ってきた。洞窟の不気味な声の正体もばっちり掴んだし、安全も確保してきた。もう近隣住民や冒険者が、あの声に悩まされることはない」
「よかったです。それで、声の正体は何でした?」
「この生き物の、腹の虫だった」
「へ?」
ディータが手短に事の顛末を報告すると、職員は拍子抜けしたのか、ポカンと口を開けて私に抱っこされている生き物を見ている。
でも、少しして落ち着きを取り戻したのか、勢い良く首を振る。
「いやいやいや、そんなわけないでしょ! だって、たくさんの人が不気味な声を恐れてたんですよ? それを出していたのが、こんな小さな生き物だなんて……え、これ豚? 違うな、馬面っぽいけど馬じゃないし、何かずんぐりしてるし……え?」
初めは声の正体がこの小さな生き物であることが信じられなかった様子の職員は、今ではこの生き物が何なのかということが気になっているようだ。
ギルド職員として働き、日々様々なモンスターの情報に接しているはずの彼がわからないというのだから、よほど珍しい生き物なのだろう。
「こいつが何なのかはわかりませんが……とりあえず、洞窟の安全は確保されたということでいいですか?」
「ああ、大丈夫だ。こいつが洞窟から出てきてから声は止んでるし、何より洞窟に他に何もいなかったのも確認してる」
「そうですか……それなら、約束通り報酬はお支払しなくてはなりませんね」
職員は渋々といった様子で精算を始めた。私たちの無事を心配してくれていた気持ちと、こうして報酬を払いたくないという感情はどうやら両立するらしい。
私がカバンから草やキノコなどのアイテムを取り出すと、その不満顔が少し和らいだ。たぶん、この手の精算アイテムはギルドの良い稼ぎになっているのだろう。こちらとしても何割かもらえるのはありがたいから、今後も積極的に取りに行くことにしよう。
「じゃあ、お約束の報酬五万ゼニーです。それと、アイテムを精算したぶんの三千ゼニーですね」
「この生き物は……回収されたりするのか?」
報酬の入った袋を受け取りつつ、ディータがおそるおそる切り出した。
この生き物は、問題となっていた存在だ。無事に洞窟の件が片付いた証拠として、ギルドに回収されてしまうのかもしれないと私は心配だった。おそらく、ディータもそうなのだろう。
だからといって、この子をどうしてやるのが正しいのかは、一切わからないのだけれど。
「え? いりませんよ、そんな得体の知れない生き物。というより、引き取れと言われても困りますよ。そういうのは、未確認生物の研究や調査をしている団体に持っていけば、良い値がつくんじゃないですか?」
職員はそれだけいうと、私たちの次に並んでいた冒険者の対応に取りかかってしまった。
仕方なく、私もディータもカウンターから離れ、腕の中の生き物を見つめた。
「よく寝てますね」
「本当だな」
寝息を立ててぐっすり眠っている生き物が、私たちはとても可愛く見えていた。だからこそ、その姿を見つめるのは複雑な気持ちになる。
「未確認生物を研究している団体に行くと、この子はどうなるんでしょうか?」
「安全かどうかは……わからないな。殺しはしないだろうが、この生き物を知るために様々なことをたくさん試すんじゃないかと思う。人間の安全と発展のためだろうが、その手の研究者には研究対象に命の尊厳があるとは、考えないだろうからな」
慎重に言葉を選びながらディータが話しているのがわかって、私は胃がキュッとなった。彼の言ったことを端的な表現にすれば、ようはこの子は実験動物として扱われるということだ。
エゴなのだろうけれど、どうしてもそれだけはだめだと思ってしまった。
もしかしたら、この生き物に対して母性のようなものを抱きはじめているのかもしれない。
「……イリメル、心配しなくても大丈夫だから。その子、飼いたいなって思ってるんだろ? だったら、そうしたらいいよ」
「え……」
私がいつの間にかギュッと生き物を抱きしめていたからか、ディータがなだめるように優しくそう言ってくれた。
でも、私はすぐにそれに頷くことができなかった。
だって、ただでさえ私は、まだひとりで立てない半人前の冒険者なのだ。ディータと組んでもらい、彼に支えられてどうにかやっている。
それなのに、何かを飼いたいだなんて思うのは、贅沢な気がしてしまうのだ。
ただ、その申し出自体はとてもありがたかった。
「……ディータさんはどうして、そんなに私に親切なんですか?」
これまで何度か似たようなことは尋ねてきたけれど、またわからなくなってつい尋ねてしまう。
私に対する親切心から手助けしてくれているのはわかっているけれど、それにしても親切すぎやしないかと思ってしまうのだ。
でも、そんな質問に彼は優しく笑った。
「イリメルがそいつに感じてる気持ちを、俺もきみに感じてるだけ」
何でもないことのように言ってのけるディータに、私はすぐに言葉を返せなかった。
嬉しくて、ありがたくて、でもそれだけでは表せない感情が胸を満たしていく。
その気持ちを表すための言葉を探していると、腕の中の生き物のお腹がまた魔物めいた音を出した。
「腹ぺこモンスターのお目覚めみたいだ。何か買ってくるから、今夜は外で食べようか」
「はい」
生き物が目覚めてしまったことで、さっきの話は何となくうやむやになってしまった。
今はとにかく、この子を手放さずに済んだことを喜ぶしかない。この胸に満ちた温かな感情の正体については、追々考えていくことにする。
外の広場に出てしばらく待っていると、ディータが屋台で調達したらしい食べ物をたくさん抱えて戻ってきてくれた。
具材を挟んだパンや、串焼きの肉、果物など。私たちの食事だけでなく、この生き物が食べられそうなものを。
「ほら、何がいい? お前の食えそうなものを食うといいぞ」
まだ眠そうにしている生き物は、ディータが差し出した何種類かの串焼きと果物を見比べ、そのうち一本を選んで食べ始めた。
串まで食べてしまいそうな勢いだったため、私とディータの二人がかりで慌てて串から肉を抜いてやった。
「そうか、お前は豚肉が好きなのか。じゃあ、スイーラと名付けよう」
旺盛に食事をする生き物を微笑ましく見守りながら、ディータが言った。
彼が口にした名は、何となくこの生き物に似合っている気がする。
でも、私は少し引っかかりを覚える。
(豚肉を意味するスイーラという単語は……今は失われた古語のはず)
私はこの国や近隣国では一部の貴族や王族しか学ばないとされる古語についての知識をディータが持っていることに、少しだけ違和感を感じていた。