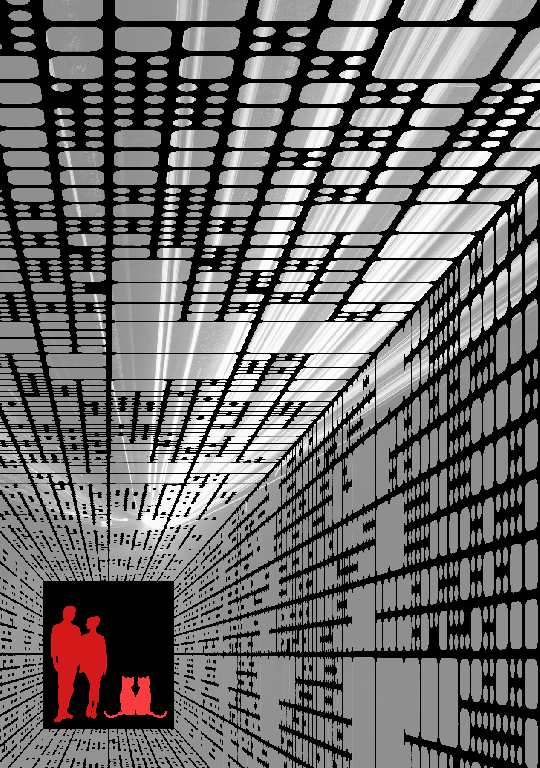【6】伯爵夫人として当然のこと
彼女は、一日に一度入浴をし、三度食事をとるのが、伯爵家の使用人だと考えていただけである。
使用人が特別な理由なくそうしないというのは、家を守る夫人が義務を怠っているに他ならないからだ。
ジェラルドの奥様であるのだから、伯爵夫人として見過ごすことは出来ないのである。
彼女はあまり複雑には考えていない。
単純に、それが使用人に対する扱いだと思っていただけである。
その日の夕食までに、地下にいた者達は、レティシアが嫁いで来る前同様、上階の部屋の使用を許された。地下よりはましである。
下着や衣類も取り替えた。おおっぴらに洗濯できなかったこれまでとは異なるため、全員着替えることが出来た。
それはエーネがレティシアの疑問としてローレンに状況を聞き、ローレンが実行したからである。
食事も振る舞われた。
夕食の席で、ローレンはレティシアを見守っていたが、彼女はそこで特に何か言うことはなかった。
無表情で夕食を食べていて、その後は入浴し、就寝した。
――それからしばらくは何事もなかった。
何も言わないレティシアに、使用人達は、戦々恐々としていた。
一週間後からは、離れの建設が始まった。メルディが、見取り図を手に、業者の手配に行ったらしい。
この地の業者ではなく、レティシアが特別に指名して呼び寄せたらしい。
だから、業者が来るまでローレンは気づかなかった。
設計図以外は、領地の業者に頼むと聞いて、安堵したものである。
領地の者を使わないのは、あまり好ましくないのだ。
設計図くらいであれば、建築物にも好みがあるから、特に貴族であれば許される。
しかし大工や材木店、石屋はそうでもない。
ローレンのそんな考えを、エーネは分かっているという顔で聞いていた。
エーネは何を考えているのかいまいち分からないが、ローレンは徐々に信用しつつあった。彼女は頭が切れる。
メルディも頭の回転は速いが、感情豊かな彼女よりも、エーネの論理的で淡々としている点の方が、なんとなく信用できた。
ローレンは設計図を熟読したりはせず、とりあえず彼女たちにそれは任せて、領地の業者への手配と連絡を請け負うことになった。
――王都から五人組の商人がやってきたのは、三週間後のことである。
季節はもうすっかり春だった。
代表して挨拶をしたのは、ワールバーン商会の代表という男だった。
大荷物を持ってやってきた彼らが、暫しの間滞在すると言うことをローレンは事前に知っていた。レティシアも迎えに出てきた。彼女に向かい、代表のリューレンは、にこにこしながら話しかけていたが、レティシアは一言二言声をかけると自室へと帰ってしまった。
わざわざ呼び出したのに購入しないのだろうかとローレンは顔をしかめそうになった。
滞在予定もキャンセルだろうかと考えた時、エーネがローレンを見た。
――彼女のこの冷たい視線に、ローレンは慣れつつあった。
彼女がこういう目をする時は、『バケモノ』と呼ばれていた使用人達について何かすべき時であり、ローレンがそれに思い至らない時なのだ。
「エーネ、ご案内を」
「かしこまりました」
ローレンも現在では、そう言う場合の対処を覚えている。
……エーネに丸投げするのだ。
自分はいかにも当然だという顔で、最後尾を歩くのである。歓談しながら客人は歩いていく。
ついた先では、メルディが、使用人達を大部屋に集めていた。
来客者に、ほぼ全員が硬直していた。
ローレン自身も、まさか見世物にするわけではないだろうなと危ぶみかけていたが、必死でそんな自分を抑えていた。
使用人達も、見世物にされるのではないかと、一様に不安を抱いていた。
これまでの対応からレティシアを信じたい気持ちもあるのだが、そう簡単に信用できるものでもないのだ。このまま売りに出されることを考える者までいた。
――しかし彼らの不安は、すぐに解消された。
「働きがいがあるなぁ」
なんて言ってから、客人達が挨拶を始めたからだ。
彼らは、医者・人形師・椅子職人・絡繰職人、そして代表商人の五名で、いつも五人で各地を廻っているのだという。
義肢や義眼、車いすや専用寝台などを作ることを専門としているそうだった。
ローレンは最初、ポカンとしていた。そう言う品物の存在を耳にしたことがなかったわけではないが、それらは高級品であり、一般には普及などしていないのだ。
はっきり言ってしまえば、ごく一部の貴族専門の代物である。
商人達は、皆の測定を始め、身体状況を記録し、最適な事柄を模索していく。
彼らが暫く滞在するのも当然のことといえた。きちんと完成するまで、彼らはここにいるようなのだ。きちんと機能することを確認するまで帰らないらしい。
できあがる品は、レティシアにとってはそうでもないのかもしれないが、当然使用人達には払えるわけがない金額である。
使用人の中で最も給与が高いローレンでさえも、車いすを一台購入すれば、生涯借金地獄になると考えられる。
だから思わずローレンは、人目のない場所で、エーネを捕まえていた。
「あのように高価なものを、奥様は一体どういうおつもりで手配したんだ?」
するとエーネは長めに瞬きをしてから、一人頷いた。
「レティシア様は、多分何も考えていないと思いますよ。レティシア様は、例えば手がない方は義手をつけるのが当然だという世界で生きてきた方なので、彼らを見て、逆に何故これまで義手をつけなかったのか、言葉に出さずとも純粋に疑問を感じていらっしゃるようでしたから」
「義手が当然用意されるような世界は滅多にないのでは?」
「レティシア様は、その事実をご存じないんです」
「だが貴方は知っていただろう?」
「旦那様は旅立つ前に、レティシア様の好きなようにして良いと仰せでしたから、お止めしませんでした。レティシア様は、使わない分には良いけれど、無くて困るくらいなら有って損はないとお考えのようです」
「慈悲深い奥様の優しさだと受け取って良いのか?」
「確かにレティシア様は大変優しいお方だとは思いますが、別段優しさではないと思いますよ。レティシア様にとって、使用人の状態を整えることは、伯爵夫人として当然のことなのかも知れませんから。ご本人には、当たり前のことをしているつもりしかないでしょう」
「義務だと考えて嫌々していると言うことは?」
「それは無いと思いますよ。レティシア様は、例え義務であっても、やりたくないことは全力で回避しようとなさいますから」
「信じますからね」
エーネが嘘をついているようにも見えなかったので、ローレンはそう告げた。
その後着々と作業は終わり、客人達は帰っていった。
入れ違うように、別の商人がやってきた。
今度こそレティシアに用があるのかと思えば、彼らもまた使用人達を顧客とした。
その際には、ローレンも測定されることになった。
使用人全員の服を新調するというのだ。夏服と冬服を、毎日交換するものと予備で八着、備品や下着などは沢山購入することになった。
商人達は、物珍しそうに義肢などを見てはいたが、『バケモノ』だと驚くようなことはなかった。
また、義肢を使わなかった者や、首が長かったり足が複数有ったりする使用人には、それに応じたオーダーメイドの服を作った。
その後美容師がやってきた。使用人達の髪などを整えて、櫛をおいていった。美容師は、領地の人間だった。今後は、月に一度来るらしい。
「領主様の家にはバケモノが出るって聞いたけど、見たことがあるか?」
――そう、興味津々な顔で世間話をしていた。
自分がそうだと何人かが答えると、美容師は、「なんだデマか」とつまらなそうな顔をした。
美容師は、ケルベロスという三首の巨大な犬を例に挙げ、
「バケモノを自称するなら出直してこい」
と、不服そうに言っていた。
他の変化はと言えば、女性の使用人は、化粧をするようになった。
「伯爵家のメイドは綺麗にお化粧するものです」
――奥様が言ったからである。
このようにして、使用人達の見た目は変わった。
不思議なもので、来客者も恐怖する人は激減した。
驚愕する者は時折いるが、皆、バケモノではなく、きちんと人間だと認識しているようだった。来客者とは、まぁ商人や領地の長などであるが。
その中には、以前はバケモノだと恐れていた人々もいたが、彼らも今では時に話しかけるほどにフレンドリーだ。
使用人達がフル稼働するようになると、屋敷の清掃が行き届くようになった。
それから、離れが二つ完成した。最初ローレンも含めた皆は、レティシアが引っ越すのだと思っていた。しかしレティシアは、
「何故わたくしが引っ越すのですか? 貴方達が引っ越すのです。毎朝ご飯を食べてからお屋敷に来るように」
と、相も変わらず嫌そうな顔で言った。
この頃になるとレティシアの嫌そうな顔は、本当に嫌なのではなく、そう言う顔なのだと理解するようになっていた。
とはいえ追い出されるのかと恐る恐る向かった結果、車いすなどでも過ごしやすいバリアフリーかつ、一人一室あてがわれた使用人専用の館に、興奮した者は多かった。
首が長い者の部屋には、わざわざ高い位置に鏡が設置してあった。東と西で、男女が別れている。嘗てあまり女性扱いされなかった使用人達の中には、泣いて喜ぶ者もいた。こちらは独身者の寮であり、もう一つの離れは、夫婦で用いる寮だった。
四組ほどそちらに入居した。勿論そこもバリアフリーである。
――邸宅自体は、いつしか本館と呼ばれるようになった。
本館に常駐しているのは、執事のローレンと、元々メイドで新しくできた役職に就いた侍女長のハンナとコックのロジャーである。
他の者は皆外で、持ち回りで数人が本館の待機室に控えるようになった。
ちなみにエーネとメルディも単身者用の寮にいる。
この二人は、毎晩交代で、どちらか一方が本館にいる。
寮にはまだまだ空きがあるから、今後誰かを雇用した場合も、通いでなければ、そちらに入居することになるだろう。
義肢などが必要ない者でも、独身であればそこである。
元々の地下は改装され、現在では食料と備蓄の倉庫になった。
ジェラルドが帰ってきたら驚くだろうなとローレンは思った。
目立つようになったお腹を撫でているレティシアをそれとなく一瞥する。
あっという間に時が流れているのをまじまじと感じさせられる。
レティシアは妊娠しているのだ。
――近いうちに生まれる予定である。