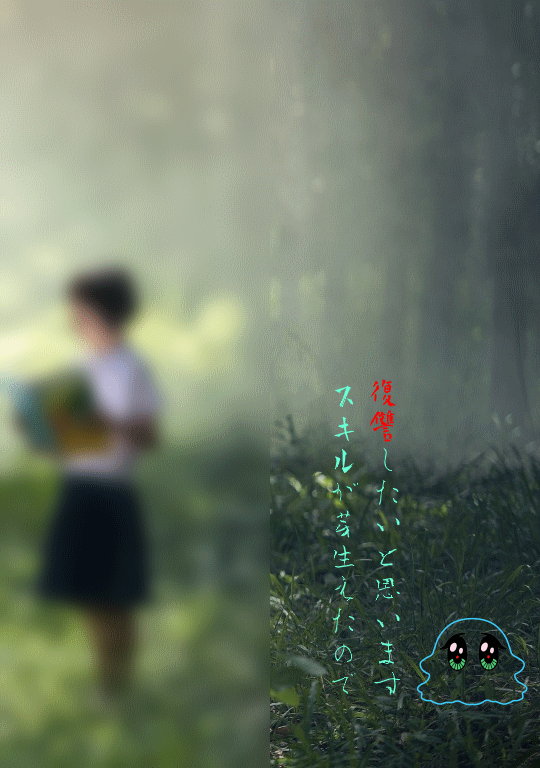一章の五 蔦文花が、うろちょろする。
入社式の翌日。一華は、とにかく不機嫌になっていた。
不機嫌の理由は、蔦文花に他ならない。今まで生きてきた中で、最も嫌いな人間である。そんな人間が、同じ会社に入ってきたのだ。
こんな偶然など、なくていい。もっと心温まる偶然を、なぜよこさないのか。一華は、神様を呪った。
蔦文花は、朝からイライラさせた。
商品搬入等を行う事務所前で、毎日、ラジオ体操と全体朝礼が行なわれる。
ラジオ体操は、誰が決めたわけでもなく、事務所側からホワイトカラーが並び、従うようにブルーカラーが後方を占めた。
スーツを着込んだ文花は、最前列でラジオ体操をしている。
「おい、たまんねえなあ」
「ああ、尻のラインがいやらしいな」
一華の左隣りの次朗の、更に向こうの男どもが、朝から卑猥な会話をしている。紛れもなく、文花を評していた。
次朗が、わざわざ左隣りの男どもの会話に、うんうんと頷く。
男どもは、ラジオ体操第一が進む度に、文花をいじった。
「膝を曲げるだけの仕草が、なんともいえん」
「ああ、恥ずかしげに股を開けないところなんか、可愛すぎる」
ラジオ体操第一、二度目の「腕を振って足を曲げのばす運動」に差しかかった際の、文花への評価だ。
一華は、ケッと小馬鹿にしていたが、自分の股を開け過ぎている現状に気づき、周りを確認してから、膝を曲げるだけに修正した。
次朗は相変わらず、文花を見ながら体操をし、男どもの噂話に頷いている。
一華は、イラッとした感情を抑えきれなくなった。ラジオ体操第一、最後の深呼吸の運動で、どさくさまぎれに、次朗の上腕二頭筋辺りに拳を当てる。
「痛ったい。何するの……」
次朗が驚いて、一華に振り向く。一華は眉の中心に皺を寄せて、顎を
仕事が始まっても、一華のイライラは収まらなかった。
技能部の伝令係として、文花が度々、一華の製造部に姿を見せる。
文花の周辺には、用もなく男どもが群がった。群がる勇気のない男は、遠くから眺めている。
文花を取り巻く景色を、見たくもないのに見せられた。一華は、仕事に集中するしか逃れられないと思った。ところが、逃れる先の仕事も、ちょっとしたミスが増える。
イライラさせた理由は、過去の記憶にある。学生の頃と、周りの反応が同じ状況になっていた。否が応にも、高校生の頃を思い出す。
今の工場内の男どもは、高校生の頃の周りの男子と、大差ない。用もなく群がる者と、遠くから眺める者。今の一華の恋人、尾藤公季は、遠くから眺める者の代表だった。
昼休憩は、さすがに勘弁してほしかった。
一華の昼休憩は、十二時五分前のフライング気味か、一時間遅れの十三時か、どちらかの両極端になった。仕事が忙しいか、忙しくないかで、どちらかに転がるのだ。
フライング気味のときは、同じ製造部の木内幸子、西谷浩美たちと一緒に食事を摂る。一時間遅れのときは、大概が次朗と重なる。
今日は、一時間遅れになった。いつもの食堂で一華は、美味くも不味くもない仕出し弁当を食い終えた。
食堂は人が
「お、この唄、なんていうんだっけ? 妙にサビの部分を口ずさむんだよね」
次朗が、仕出し弁当を片手に、左隣に座った。
「お前、おかしいんじゃないの」
一華は、厳しく削りにいく。いつも次朗にだけ用いる、一華なりの対応だ。
「だって、みんな可愛いんだよ」
唄の批判をしたのに、外見等で擁護する。ときどき次朗は、変な理由、理屈を口にした。
一華は、次朗の上腕二頭筋辺りに、ガツンと拳を当てる。対次朗専用の、愛情表現だ。
「痛ったい。何するの……」
「お前が、肋はやめてって言ったんだろうが!」
あまりの理不尽さに、次朗は口をへの字にして目で訴えてくる。うふふと、一華は、可愛い奴めと笑顔で返す。
いつもと、変わらないはずだった。いつもであれば、昼休憩でリフレッシュできた。
それなのに、ここにも心乱す者が現れる。食堂に入ってきただけで、それまでの空気を吸い取っていく。どうしても、そっちに目が行った。
文花が、食堂の出入口から正面奥に行って、仕出し弁当を手に取る。すると、キョロキョロし出して、何かを探しているようにも見えた。
一華は俯《うつむ》いた。文花が、一華側に視線を向けた気がしたからだ。
一華は、(早く、どっかに落ちつけよ)と心の中で
「隣、座ってもいい?」
文花は、次朗の隣りを指さした。次朗は、俯いて返事をしない。しょうがなく一華は、首をコクリと頷いて見せた。
一つの会議用テーブルに、右から一華、次朗、文花が並んで座る。真ん中の次朗が黙々と、残りの仕出し弁当を食べ始めた。文花は、お茶を用意するために、再度、正面奥に向う。
文花が戻ったときには、すでに次郎は食べ終える。
「仕事が忙しいから、戻るよ」
次朗が一目散に、席を後にした。会議用テーブルには、右から一華、空席、文花と並んだ。一華は腹を