暗闇の金魚鉢【短編】
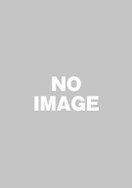
『暗闇の金魚鉢』
愛しいあなたに会うためならば、どんなことだってしてみせる。
この暗い世界の中で、彼の声だけが唯一自分の救いだったから。
『機械人形屋さん、どうか、愛しいあの人を蘇らせてくれますか?』
◇ ◇ ◇
ミアは海に肩まで浸かりながら、陸地にもたれるようにして手を伸ばしていた。
温かな日を浴びているのはわかった。陸の草を指で触れると、だいぶ若々しい草が生い茂る季節になったのだなと理解する。
盲目の自分は、視力以外の五感を敏感にしなければ、この世界では生きていけない。
―――長い尾ヒレは、痛んでしまったために、長い距離を泳ぐことはできなくなってしまったけれど。
「あなたが、人魚のミアさん?」
靴の音が聞こえた時、ミアは顔を上げた。上から聞こえた声は―――まさか!
「初めまして、機械人形屋を営んでいるリオと申します。伝言を頂き、出張してきました。―――私、初めて人魚って拝見しましたよ。カレン、魔女のあなたは?」
「わ、私は―――300年生きた中で、何度か―――人魚には興味なかったですし···」
ミアは、がばりと水面から身体を持ち上げた。
「来てくれたのね!私、私、私!人魚のミア!たまたま道を通った人間さんから機械人形屋さんの話を聞いて、ここに来てほしいって頼んだの!あの人、とても親切な人間さんだったのねぇ!今度来た時お礼言わなきゃ!あ、でも名前を知らないわ!」
ミアはぺらぺらと言葉が出てきた。人間と話すのは、ミアにとって楽しいことだ。
―――いや、リオというのは人間か?カレンというのが魔女とは聞いたが、盲目の自分にはわからない。
「機械人形ってよくわからないのだけれど、亡くなった人を蘇らせることができるのでしょう!?魂を定着させるための器なんて本来存在しないのに、凄いわ!ただの人形に魂定着させても、動かないし喋れないのよ!?魔法でもできないことをできるなんて、異世界の技術は進んでるのね!」
「ありがとうございます。私が作る人形は、『機械』ですからね。あなたの大切な人を、そのままの姿で戻すことができますよ」
「素敵だわ!私、恋人を蘇らせたいの!お願い!機械人形屋さん!」
「···それは良いのですが、ミアさん、貨幣をお持ちですか?何か価値あるものを頂かないと、作れません」
「あー!人間さんから聞いてたわ!私の血をあげる!それでどう!?」
間があった。リオが微かに笑う気配。苦笑、とでも言うのだろうか。
「···リオさん、人魚の血は不老不死の薬です。かなり希少ですし、高値で売買されてますから···」
「あ、価値はあるんですね?じゃあ良いでしょう。しかし問題は···そのお方の姿はどうしましょうか。ご存知のお知り合いとか、いらっしゃいますか?」
リオの声は弾み始めたが、ミアの気持ちは下がった。
彼の姿を、自分は見たことがない。盲目なのだから当然だ。
そして、彼を見た者は···。
「···いるんだけど、無理ね!私、仲間に追放されちゃったの。人間と恋に落ちてね···。それで罰として、私はこの尾びれ、彼は···いなくなってしまったのよ」
軽く笑い、尾を高々と持ち上げて見せると、2人は暫し黙ってしまった。自分は、彼女等を黙らせたことを申し訳なく思う。
「···恋人を蘇らせたいということでしたが、何故、人魚のあなたが人間と恋をしたんですか?」
「カレン、別にそれ私達には必要ない情報だよね?」
リオに咎められ、カレンは口ごもる。ミアは口元に笑みを浮かべ、頭を横に振る。
「普通人魚って、人間のことを見下してるものねぇ!でも私、その人···ウルリクと会って、人間への見方が変わったわ」
ーーミアは静かに、話し始めた。
「私は陸に近づくことを、海の王様ペテルダウノ王からよく注意を受けてたわ。でもね、私は盲目で、つい上に行っちゃうのよ。陸に上がって困っていたら、ウルリクが話しかけてくれたの。彼はね、私のことを『長い銀髪、真紅の鱗。こんなに綺麗な女性を見たことがないよ』って···褒めてくれたの」
「···あはっ、ナンパかな?」
「ウルリクは、そんな軽薄な人じゃないわ!だってあの人、毎日会っても私と手を繋ぎもしなかった!私達はとっってもプラトニックな関係だったもの!でも···毎日会うたびに美しいと褒めてくれて···好きになるに決まってるじゃない!」
ほうっとカレンが感嘆した。
「素敵ですね···異種間の禁断の愛····」
「そう、異種間の恋愛は禁忌···だからある時、ペテルダウノ王の怒りに触れて···私達が愛を語らってた時に···2人とも海の底に引きずり込まれたの」
「え!?」
「私は仲間の人魚達に攻撃を受けて、尾を傷つけられて、群れから追放を言い渡された。ペテルダウノ王は彼に罰を与えると言って···消した、と···」
その時の恐怖を思い出すと、涙が溢れた。
(あぁ、今更泣かなくても良いじゃない。あの人は蘇るんだもの···大丈夫、大丈夫···)
彼を消すと言った海の王のことを思い出すと、心が恐怖で固まる。尾を傷つけられる痛みなど、軽いものだと自分は思う。
愛する彼を失う苦しみが、誰に理解できようか。
「···彼を、蘇らせてくれるのよね?私、彼が戻るなら···何をしたっていい!血だって、あなたが望むまで差し出すわ!」
「ーーー血は、対価の必要量だけで結構です。でも、彼を機械人形にするにあたり、原則をお話します」
「原則?何かルールがあるの?」
「まず1つに、機械人形は胸にあるコアを潰せば壊れてしまいますのでご注意下さい。2つめに、機械人形は自らの意思で誰かの命を奪うこと、傷つけることはできません。3つめに、2つ目の約束を遵守しなければ、自ら壊れてしまうという仕組みになっております。4つ目に返品は受け付けてません。これは、私のいた世界でのルールを反映させたものです」
「返品なんかするはずない!壊れないようにも、もちろん注意する!それに、優しいあの人が誰かを殺すなんてありえないわ!」
「わかりました。姿がわからないとなると、汎用的な人間の機械人形に···ん?」
ミアは、何かの音がしたことに気がついた。足音か?
カレンが「何ですか?」と言ったが、相手?からの声はない。
「···汎用的な容姿の機械人形で、よろしいですか?」
「ええ!私はウルリクがどんな容姿の人間でも良いもの!」
「わかりました。それでは、明日にでも機械人形をお持ちしましょう。カレン、行こう」
カレンはつまるような声を出したが、リオの後についていく。離れていく2人の足音が、聞こえた。
「···誰か、いるの?」
先程何かの気配を感じたと思ったがーー気のせいか?
「ねぇカレン、“あれ”は、何?」
リオが小さく、カレンに問いかける声がした。
◆ ◆ ◆
約束通り、次の日2人はやってきた。
昨日からミアの気持ちは昂り、睡眠をとることもできなかった。
(ウルリクに会えるのね!ペテルダウノ王にされたことを謝らなきゃ!私のせいだし―――!彼、私のことは嫌いにならないわよね?優しい彼なら、私のことを変わらず愛してくれてるわよね?)
仲間に追われたことはどうでも良い。毎日話していた彼を失ったことが、ミアにとって最大の苦痛である。彼もまた、自分のことを心配しているのではないか―――。
『愛しているよ、ミア』
彼が優しく自分に囁いたことを思い出すだけで、胸が高鳴る。
異種族間であっても、自分はどうでも良い。
とにかく自分は彼のことが大好きで―――ウルリクを取り戻したいのだ。
「機械人形はご用意しました。あとはカレン、よろしく」
「···はい。そ、それでは―――」
(?あれ、暗くない?)
どうしてカレンの声が暗いのか、自分にはわからない。
「ププクス!」
「はぁい!可愛いボクにお任せあれ!やるよ~!」
彼の声が聞こえてきたのは、突然だった。足音を出さなかった、少年の声の正体は―――悪魔か。
カレンは魔女だ。魔女というものは、悪魔に代価を支払って魔術を行使する。
ププクスというのは彼女の悪魔なのだろう。
「···ププクスに我が身を捧げた代償として、願います。白き世界の果てから、かの者の魂を呼び寄せん。かの者の名は、ウルリク。我が願いを、成就させたまえ―――」
(魔術!恰好良いなぁ~!)
人魚は魔法を使えない。カレンの魔術の声によって、魔力が集まってくるのを感じる。魔力は増幅し――――。
「レプミリア!」
(え)
目が見えないミアだが、すぐに気づいた。
集まった魔力が、霧散していった。まるで風船が破裂するように、そこから何もなくなってしまったのだ。
「え、何?え?どうしたの?何があったの?ウルリクは?」
「···ミアさん、呼べません」
「どうして?どうしてそんな意地悪言うの?私、血をあげるって言ったよね?ねぇリオさん、どういうこと?何で呼べないの?機械人形に何かあったの?」
「違うんです。ウルリクさんの魂は···」
カレンはとても言いづらそうにしていた。その隣で、リオが微かに息を吐いた。
「ウルリクさんの魂は、召喚できないんですよ」
――――ぇ?
魂を召喚できない?
「それって···」
「い···生きていらっしゃる、ということですよ···!ミアさん···!」
「え···!?」
カレンが言った時、自分は―――喜ぶに決まっている!
「う、ウルリク生きてるの!?え!?彼は生きて···」
彼が生きている。
機械人形の姿ではなくそのままの姿で生きていてくれたなら、心は踊るに決まっている。
「ん?でも―――じゃあ何で、私に会いにきて···くれないの?」
2人が黙った。
(ウルリクが生きていたら、絶対に私に会いに来るはずよ。だって私達は愛し合ってる。愛し合ってるんだから···当然···)
罰を受けた後でも、会いに来てくれるはずだ。生きているのであれば、どうして来ないのだ?
「私、気づいてしまったのですけれどね。彼は、あなたに嘘をついているんですよ」
「嘘?何を···え?何で嘘を?それと、彼が私に会いに来てくれないのに理由があるの?」
急に不安になった。彼との何が、嘘だったというのか。
彼と過ごした日々は本物で、彼の言葉は全て真実のはずだ。
「彼はね、人間じゃないんですよ」
―――何を、言っているのだ?
「何を言っているの?リオさん。彼は人間だと言っていたわ。嘘をつかないで」
「人間であるはずがありません。だって、彼は海に引きずり込まれたんですよね?普通の人間なら、その時点で死にますよ。それなのに罰を与えられ、カレンの召還術でも呼び寄せられない。つまり、彼は人間ではないんですよ」
「え?あ···、え?」
―――自分とウルリクは、海に引きずり込まれた時に”生きていた”。
自分が尾びれを傷つけられている間の彼のことは、わからない。
ただペテルダウノ王が「消した」と言っていたので―――死んだものと思っていた。
(あ、そっか···人間って、水の中じゃ息できないんだった···)
自分が当然水の中で息をできているのだから、そこに不可解さは感じなかった。
「じゃ、じゃあ彼は何なの?ウルリクは、人間って言ってた!何でそんな嘘つくの!?―――水の中で息ができるのなら、もしかして人魚!?あ、でも人魚だったら罰を受けることもなかったはず···!じゃあ···?」
「···あなたは、彼がどんな姿でも良いと仰っていましたね。本当に、よろしいんですか?」
「リオさん!何を知ってるの!?私はウルリクに会いたい!会いたいの!彼に会えるのなら、全てを差し出すわっ!」
自分は陸地にあがり、リオの服を掴んだ。
ウルリクが、恋しい。もし生きているのなら―――会いに来てくれないとしても―――会いたいのだ!彼が好きで好きで仕方がないのだから。
「···ミアさん、お手を···」
「え?」
カレンの小さな手が自分の手首を掴み、何かを触らせた。
ぬめっとした、何かに。
「―――ひっ···!」
つい自分は声をあげ、手を引っ込めた。苔のような何かだ。
「な、何!?何なの!?これ···何!?」
「ウルリクさんですよ···ミアさん」
「え!?何言ってるの!?何で···そんな嘘をつくのよ!?ウルリク!?これが···!?」
「はい、ウルリクさんはウオジャノーイなんです」
「ウオジャノーイ!?ウオジャノーイって···水の化け物!?」
ウオジャノーイとは、水の中に生きるモンスターだ。苔が全身に生えており、カエルのような顔をしている生き物だ。人間のように二足歩行で歩くことはできるが、その姿は気味が悪いと―――他の人魚達に聞いている。
「―――嘘よ!だって、彼は人間って···大体、喋らないじゃない!本当にウルリクなら、話してよ!」
「彼は話せないらしいですよ、ペテルダウノ王に声を消されたんですって」
「え―――」
「私は彼の言葉わかりませんので、カレンと彼がウオジャノーイ語の筆談をして、何とか会話が成立しました。彼は間違いなく、あなたの知っているウルリクさんです」
今まで人間だと思っていた彼が、突然水の化け物であるウオジャノーイと聞き、動揺しない訳がない。
(だから―――触れなかったの···?)
手を繋ぐことすらできなかったのは、正体を知られないためだったのか。
「う、ウルリク···?」
声は返ってこない。声を失ったというのは、本当なのか―――?
『愛しているよ、ミア』
ウルリクは、そう言ってくれた。彼の愛の言葉を、もう聞くことはできないのか?
「ミアさん――彼はずっとミアさんの側にいたんです」
「え···?」
「誰かがあなたに危害を加えないか、見守っていたんですって。あなたを愛しているからって···ミアさん」
カレンの声音は切なげで、何かを訴えかけているようだった。
『長い銀髪、真紅の鱗。こんなに綺麗な女性を見たことがないよ』
ウルリクは、自分にそういって話しかけてくれた。
(―――逆に、私は彼に言ったことがなかった。愛しているという言葉には応えたけれど、彼の容姿を―――気にもしなかった)
自分にとって、どうでも良いことだからだ。
ウルリクは、ウルリクだ。
自分を愛し、そして今も側にいて、自分を見守ってくれていた――。
「あ···わ、私···」
先ほど、自分は何と言った?
化け物と、せっかく初めて彼の手に触れたというのに、悲鳴をあげてしまった。――――何て、馬鹿者なのだろう!
「――ウルリク!」
ミアは、彼に抱き着いた。
陸地にあがり、ぬめりとしたその身体に確かに抱き着き、彼の身体のどこかに頬をあてた。
「ごめんなさい!ごめんなさい!ごめんなさい!私、あなたを化け物なんて言ってしまったわ!本当にごめんなさい!私こそ化け物よ!心優しいあなたを化け物扱いする私こそ―――私は、あなたを愛しているというのに!」
彼の身体に体温などなかった。水のように冷たい、湿った身体は、自分にとって心地よく感じられた。
まるで、海の藻の上で寝ているかのように―――自分にとっては、気持ちが良い。
「ごめんなさい!もう許してなどもらえない!?愛してくれない!?ウルリク!それでも私は、あなたのことを、心から···っ!!」
彼が何も反応してくれないことに不安を覚えた。
もう彼の愛は、自分の物ではないのだろうか。
自分を、許してはくれないのだろうか。
(もう···っ!)
自分の背中に、ぬめりとした手が触れた。
とても優しく―――自分を不安がらせないよう、苦しめないよう、自分を抱きしめてくれた。
「あ···」
―――これ、ウルリクだ。
自分と会話をし続け、愛を深め合った彼だ。彼の優しさが自分の心に沁みわたる。
言葉を交わさなくても、わかる。
「ありがとう!ずっと···ずっと一緒よ!愛してる···ウルリク···っ!!」
彼を愛していることを、もう二度と一瞬たりとも忘れない。
彼とずっと―――共にいるのだ。
☆ ☆ ☆
「······美談だねぇ。···くだらない。大体これ、我々は何の対価も得ないし···」
リオとカレンは、傷ついた赤い尾びれを持つミアと、苔が生えたカエル頭の男が抱き合う姿を、じっと見つめていた。
二人の瞳からは、涙が伝っていた。
ミアはウルリクの胸に頬を当て、愛していると囁く。そんな彼女を眺め、リオは溜息を吐く。
「···彼女の目が見えていないから、成立する恋だね」
「違いますよ、リオさん」
カレンはきっぱりと言い切る。
「彼等の愛は、美しいんです。····互いに信じあう、綺麗な愛は存在するんですよ。リオさん、認めましょう?」
「···いや、これは特殊な例でしょ。私は信じない」
「――あの、私は···絶対、リオさんに信じさせます。命ある者が、下らなくなんかないことを。元・人間として」
カレンはいつも自信なさげなくせして、そこだけは強情だ。
リオは内心胸糞悪い気分になりつつ、この場から去った。


