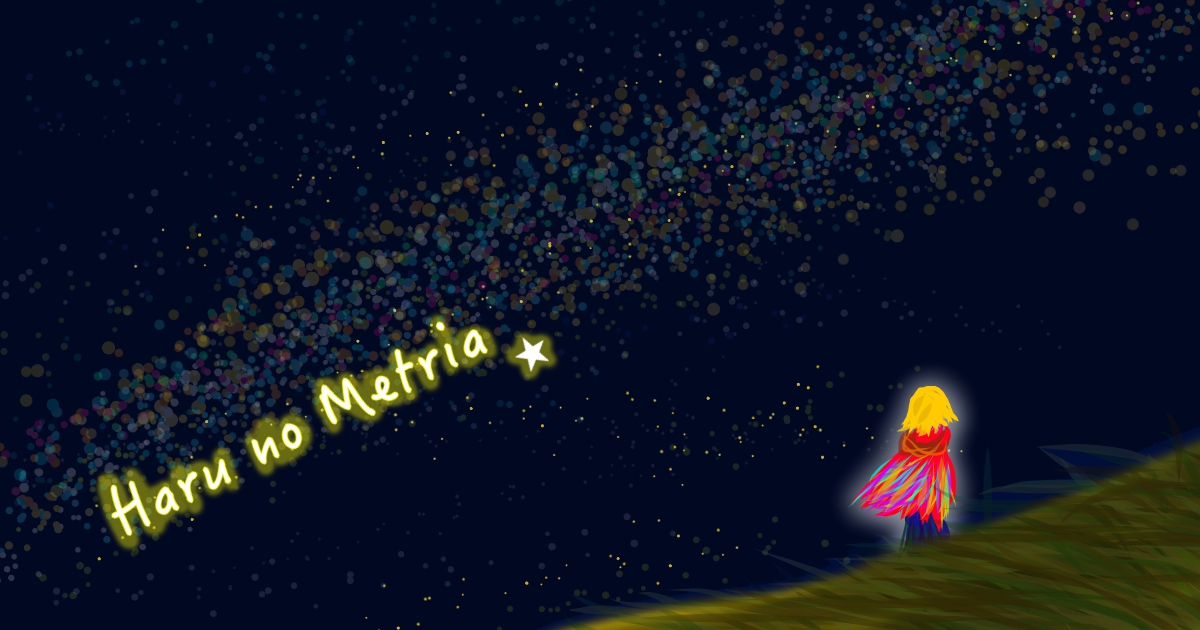終幕6
ああなるほどと、それを見てめいは納得する。つまりは。
「また随分な化け物になったものですね」
詳細までは分からないが、どうやら今起きた一連の流れはソシオが狙って起こした事だと理解しためいは、呆れたようにそう口にした。
それにソシオは黙したまま笑みを深める。
(さて、どうしましょうかね)
何かしらの方法で先を読むか誘導している可能性はあるものの、それ以外の能力的には先程と同様の評価のままでいいだろう。めいはそう判断しながらも、何が起きても対処出来るように警戒だけはしておく。
驚きこそしたものの、現段階ではそれでもめいにとってソシオは勝てない相手ではない。それでも負ける可能性は存在しているので、油断は出来ないのだが。
めいはソシオに視線を向けたまま、周囲にも意識を向ける。
先程までソシオの分体と戦っていたらしいジュライは、吹き飛ばされて意識を失っているようだ。満身創痍といった感じではあるが、傍らに居るプラタによって治療は済んでいるらしく、負傷は見当たらない。
もう一体のソシオの分体と戦っているシトリー達は、一進一退といったところ。シトリー達はソシオの分体にほとんど負傷を与えられていないが、その代りソシオの分体からの攻撃は全く命中していない。
回避もギリギリといった感じではないし、疲れた様子は全くみられないので、このまま放置していると永遠と戦っているのではないかと思ってしまうほど。
めい達の周囲には、ソシオが以前支配域の国境を守護する為に配置した人形達が緩やかに取り囲んでいる。ただ、警戒しているというよりは、観察しているだけのような気がした。
それと、何故か一人だけ天使族が混じっていた。そちらはジュライの傍でプラタと一緒にジュライの面倒を見ている。その天使族の影からは魔物の気配がするも、どうやら天使族を護る為に周囲を警戒しているだけのようだ。
とりあえず、周囲にめいの脅威になり得そうな存在は確認出来ない。念の為にめいは残っていたソシオの分体へと攻撃して壊しておく。プラタやシトリー達が攻撃しても即座に回復していた分体も、めいの攻撃で一瞬にして吹き飛ぶ。念の為に完全に消滅させておいた。
「また酷いことをするねー」
その様子に、見ていただけのソシオが軽い調子でそう告げる。相手が消えたので、シトリー達はソシオを警戒しながらもジュライの許へと移動した。
それに一切反応しないので、ソシオはめいへと意識を向けるだけで周囲についてはどうでもいいらしい。
めいはソシオに狙いを定めると、一瞬で距離を詰める。空中からでも速度が衰える様子はなく、瞬きする間にソシオの目の前にめいは現れる。
ソシオの目の前に移動しためいは、同時にソシオへと攻撃を行う。移動の勢いをも込めて繰り出したこぶしは、ソシオの鳩尾辺りに命中する。そうして接触したところで、めいは死の権能を行使した。
「くっ! 相変わらずそれは効くねぇ」
突き抜けていった破壊の力にソシオは一瞬顔を歪めるも、直ぐに楽しげな笑みを浮かべる。
「これで三つ・・・いえ、四つですか」
「ま、さっきのも結構効いたけれども、あれは数えなくてもいいんじゃないかな?」
「余裕ですね」
「余裕だからね」
めいの腕の長さ程の距離で見詰め合うソシオとめい。ソシオの余裕そうな笑みに、めいは肩を竦めて少し距離を取る。
「後何回殺せば死んでくれますか?」
「それぐらい把握しているんじゃないのかい? 沢山だよ、沢山」
「面倒なものです」
ため息を一つ零すと、めいはスッと目を細める。
「あまりにも面倒なので、少し纏めて吹き飛ばすとしましょう」
「おお、それは恐いね」
そう口では言いながらも、ケラケラと愉快そうに笑うソシオ。
戦闘狂とでも言えばいいのか、そんな様子のソシオにめいは呆れを感じるが、そんな状態でもソシオに油断は無いように思えたので、めいが気を緩める事はない。
めいはソシオに対して効果のある死の権能を行使して、ソシオの周囲の地面から死の力を込めた棘を伸ばしてソシオへと向かわせる。
現れた瞬間には伸びてきた棘に反応してみせたソシオは、身を捩って数本の棘を回避するが、あまりの棘の多さにそれぐらいでは全てを避けきるのは不可能で、ソシオの身体中を大量の棘が突き刺していく。
「がぁ」
喉も貫かれ満足に声も出せなくなったソシオは、全身を棘に貫かれてその場に縫い留められる。
棘の山の中に埋もれたソシオだが、どうやらそれでもまだ生きているようで、棘の山の中から低い呻き声が届く。
それを聞きながら、めいは死の力をソシオに流し続けて攻撃を継続させる。
(僅かに中らなかった部分がありますね。避けた辺りに何があるのやら)
ソシオへの攻撃を継続させながら、めいはソシオがわざわざ回避した部分について気に掛ける。今まで何度か攻撃してきたが、ソシオがまともに回避しようとしたのは初めての事であった。
今までの流れからそれがはったりという可能性もあるにはあるが、それでも気にする価値は十分にあるような気がした。
(それにしても、一体何度殺せば死ぬというのか)
めいは油断なく棘の山を見据えながら、呆れたようにそう思う。棘を全身に突き刺しているのもだが、万物に死を与える力も行使しているというのに、未だにソシオは健在であった。
(いくら別の理に書き換えている分だけ効きが悪いとはいえ、それでも既に何百何千と命を奪っているはずなんですがね・・・)
何処かしらに急所となる核でもあるのか、それとも本体は別に在るのか、もしくは無数に命を有しているのか。まだその辺りは判然としていない。調べてはいるが、確かな事はまだ何とも言えなかった。それでも、本体が別に在るというのはおそらく違うだろうとは考えているが・・・。
それからも、ソシオの全身から命を刈り取るように死の力を流し込み循環させていく。本来であればそれで終わりだろうが、上手くはいっていない。ソシオが本気になる前には終わらせたいところなのだが。
(ん?)
そうしてソシオを調べていると、めいは何かに気づいて眉を動かす。
(何か嫌な予感がしますね)
身体中を何かが這うかのようなぞわぞわとした感覚に、めいは何事かと原因を調べていく。
原因の調査を始めて程なくして、めいは内心で舌を打った。
(力を介してこちらに干渉しようとしてきますか。非常に厄介ですね)
ソシオが大人しく棘の山を築いていた理由は抜け出せないからではなく、その棘を流れるめいの力を伝って逆に侵食しようとしていたからであった。
それに気づいためいは力を流すのを止め、棘との繋がりを絶つ。その瞬間、ソシオが築いていた棘の山は内側から弾けるようにして崩壊する。
パリンという軽い音と共に棘の山が消える。棘の山の消失と共に中から出てきたソシオは、変わらぬ愉快げな笑みを浮かべていた。
「おや、気づくのが早かったね」
「あの程度では気づきますよ」
ソシオの軽い言葉に、めいは肩を竦めて返す。しかし、実際は危ういところであった。もう少し気づくのが遅れていれば、めいの敗北が確定してしまっていたかもしれない。実際、早期に浸食を絶ったというのに、力が少し喰われてしまっている。
(回復には少し時間が掛かりますね)
喰われた分の回復には数十秒程度は掛かるだろうが、それでもそれだけで何とかなる。問題は、僅かとはいえ力を喰われてしまった事だろう。
(あの力はもう通用しないかもしれませんね)
めいにとってそれは一つ手を封じられた程度ではあるのだが、新たな力を相手に与えてしまった事には違いない。そして、ソシオは手元の素材から新たな何かを生み出すのが得意であった。
とはいえ、めいは自身の力で傷つく事はない。多少手を加えられた程度であれば問題ないので、めいの力を基にして創られたモノであれば問題はないだろう。
(基が別の何かであればその限りではありませんが・・・)
力を解析して対策を立てられる。それだけであればどれだけ楽であったか。そんな事を考え、内心で苦虫を嚙み潰したような想いを抱く。ただし、表情には一切出さないが。
「そうかい。思ったよりも育ってくれていて、ぼくは嬉しいよ」
「貴方を喜ばす為に強くなった訳ではありませんがね」
呆れたようにそう返しつつも、めいは引き続きソシオについて調べていく。今でも変わらず勝てない相手ではないとは思うのだが、同時によく分からない不気味な存在にも思えてきてならなかった。
時が経つにつれて存在自体が変化しているようなそんな妙な感覚。そのせいで、めいは自分が相手をしているのが本当にソシオなのだろうかとさえ僅かに考えてしまうほど。
ソシオはニヤニヤと嫌らしい笑みを浮かべながら、全身に虹色に輝く光を纏う。
「さて、じゃあ次はこちらからの番かな?」
気楽な調子でそう言うとソシオは地を蹴り、一瞬でめいの眼前に腕を振りかぶった姿で現れる。
眼前に現れたソシオを見て、めいはそのこぶしを受けてはいけないような気がして、思いっきり後退した。
めいが立っていた場所の空を切るソシオのこぶし。それを少し離れたところから冷静に観察していためいは、ソシオが纏っている光が少し前よりも若干黒みを帯びているような気がした。
(まさか・・・いえ、早速混ぜてきたという事なのでしょう)
それを観察しためいは、ソシオの行った事を瞬時に理解して、思わず苦笑を漏らす。ソシオが新しい力を使うのが上手いのは知っていたが、それでも今し方手に入れた力を初手から使用してくるというのは理解に苦しむ。
もっとも、先程の様子をみる限り、驚く事に既にある程度完成しているようではあるが。
(あれは単純に特性を加えただけ、というのではないのでしょうね)
先程感じた嫌な感覚を思い出し、であれば自分の力に対して特別に効果があるのだろうとめいは推測する。つまりはソシオの攻撃はもう貰わない方がいいだろう。という事。
面倒なとは思うが、その程度であれば問題はないだろう。めいは本気で戦うのであれば、はじめから一撃必殺を信条に戦っているのだから、今までとそこまで大きく変わりはしない。後の問題は、めいの攻撃が通用するかどうかといったところだろうか。
そんな事を考えている間にも、ソシオはめいに襲い掛かってくる。
ソシオは徒手ではあるが、やや黒みを帯びた虹色の光を全身に纏っているので、触れるのも危険かもしれない。
めいはソシオの攻撃を踊るように回避しつつ、合間合間に様々な系統の魔法を放つ。
魔法がソシオに命中するも、効果は大してないのか反応はない。しかし、めいにとってはそんな事よりも、魔法がソシオに中った際の反応の方が重要であった。
(普通の魔法であれば、今まで通り霧散させられるだけで問題はなさそうですが、それに死の力を載せると一瞬で侵食されて砕かれていますね)
元々ソシオの虹色の光は、魔法を消し去る力に特化させたものであった。なので、通常の魔法が効果が無いのは今まで通りなのだが、それに先程まで使用していた死の権能を籠めた力を加えると、霧散どころか一瞬で魔法自体を侵食して破壊してしまう。
そして、めいは普段死の支配者として活動することが多いので、そこまで強力なモノではないが、その身に死の力を纏っている。現在もそうだが、その状態でソシオに触れようものなら、魔法同様に侵食されてしまうだろう。纏っている力自体はそれほど強くはないとはいえ、調べた結果その辺りは関係ないようであるし。
(これはしょうがないですね)
その結果が出た以上、このままの状態で戦うのは得策ではないと判断しためいは、死の支配者として戦うのを止める。オーガストに任された役割だっただけに、自身の技量不足に忸怩たる思いながらも、今は現実的に考えて、その役割を一旦横に措く事にした。
その代わりに表に出したのは、この世界の管理者としての顔。この世界で最も優秀な存在である管理者に相応しい万能の存在。
使用するのも死の権能から管理権限に変更。そうする事で、自身に設けていた制限が一部解除される。この世界の理から逸脱した存在であるソシオには、管理権限での攻撃で大きな効果は望めないが、それでも完全に防ぐことは不可能だろう。管理者というのはそこまで甘くはないのだから。
そんなめいの変化を感じ取ったのか、ソシオはより一層機嫌よさそうに笑みを浮かべる。
しかし、次の瞬間にはめいの攻撃により地面に顔面をめり込ませていた。
「?」
何が起きたのか分からず僅かに困惑したソシオだったが、直ぐに一瞬前に起きた出来事を思い返す。
それにより、一瞬でめいがソシオの背後に回ったかと思いきや、後頭部を思いっきり殴打されたのだという事を思い出した。そうやってソシオは地面に顔面から衝突したのだった。
それは、ソシオでさえこうして思い起こさなければ思い出せないほど一瞬の出来事であった。その事に思考が追い付き、ソシオは驚きと共に歓喜の笑みを浮かべる。
(これを取り込めばより高みに・・・)
そう思いながら顔を地面から抜く。ソシオの身体は異様に頑丈なので、めいの攻撃で多少頭部が破損したぐらいであった。それも既に治っている。
「・・・これで無事ですか。それもほぼ無傷。自信を無くしますね」
めいはそんな事を口にしながら地面から顔を抜いたソシオを蹴り上げ、空中でひたすらに殴り続けていく。
「やはり、こういう事をするには素手が一番だと思いませんか?」
空中で縫い留められているソシオは、次第に身体が破損していく。その崩れ方はおよそ生き物のそれではなく、石膏か何かのようにひびが入ってはボロボロと砕けている。
それから腕が砕け、脚が砕け、胴が砕けていくも、ソシオの笑みは失われない。そして遂に顔も砕けて全身が粉々になってしまった。
めいはその場から少し下がると、ソシオだったモノの破片に向けて真っ白な炎を放つ。
地面を嘗める白炎。それを眺めながら、めいは一切油断せずに周囲にも視線を向ける。あの程度でソシオが終わるとは到底思えなかった。
そして、めいのその予想は当たっていたらしく、白炎の中でゆらりと影が揺れる。
「しつこいですね。今ので終わっていればいいものを」
「ふふふ。あの程度で終わらせるなんて勿体ない」
些か不明瞭な声音ではあったが、それも致し方ない事だろう。何せ白炎の中で今でも破片が寄り集まって高速で修復している最中なのだから。
顔の半分は未だに空洞のままだし、腕も両方途中までしかない。脚も片方だけで、もう片方はまだ修復が始まっていなかった。
「どんどん化け物じみてきましたね」
そんな修復途中のソシオへと、めいは風の魔法を操り白炎の渦を形成してそれに閉じ込める。白炎の中で修復していたが、どうやら白炎も効果が無い訳ではないらしく、部位によっては修復直後に崩れていた。
そうして白炎の渦の中に閉じ込めながら、上空からは大気がソシオを押さえつける。その瞬間、白炎の中からガシャンという何かが壊れる音がめいの耳に届いた。
(さて、後どれだけ殺せばいいのでしょうか)
そんな音が届こうとも、めいにはソシオがまだ生きているのが解る。
あの状態からどうやって復活するのか気になるが、それでも加減は一切しない。管理者として戦うと決めた瞬間から、世界から異物を排除する事は徹底的に行う必要があった。
めいは攻撃の手を止める事なく、周囲の警戒も継続させる。
ジュライ達の方は、未だにジュライの意識が戻っていないという以外は問題なさそうだ。怪我の方は治っているようなので、魔力の使い過ぎか単純に疲労が濃いのだろう。
直に目を覚ますだろうし、そちらは気にする必要はないかと判断しためいは。白炎の渦の向こう側の様子を探る。
(まだ動いているようですが、このままであれば問題はないでしょう。しかし、本当にこのまま済むとも思えませんね)
少し見ない間に未知の存在へと変貌していたソシオに、めいは最大限警戒しながらそう思う。勝てる勝てないは別だとしても、理解出来るかどうかでいえば理解出来なくなっていた。
それだけ訳の分からない存在へと変化してしまっているソシオだが、少し前までそんな様子は無かったので、この短期間に一体何があったというのか。
(あれは多分壊れかけていたのでしょう。我が君への想いも如何ほど残っていたのやら)
ソシオの様子を思い出しためいは、そう推測する。おそらく変化を急ぎ過ぎたのだろうとも。
(許容出来る範囲以上を一度の変化で行おうとした。といったところでしょうかね。それだけ強大な何かを取り込んだという事でしょう)
それが何かは、ソシオの言動を思い返せば推測ぐらいは出来るだろう。しかし、その過程に意味はないかとめいは判断する。自身の許容量ぐらいは把握出来ていて当然だし、取り込むモノが問題がないかどうかを調べるのは基本であった。それを怠ったり焦った結果、先程のソシオのようになるのだから、あれは自業自得と言えた。
そして、それを冷静に判断出来るからこそ、めいは毎回自身の限界まで問題なく成長を行えている。もっとも、だからこそめいは、オーガストと自身の間に横たわる差というものを明確に理解出来てしまっているのだが。
(焦る気持ちは理解出来ますが、それで壊れていては意味がないでしょうに)
呆れとも叱責とも取れる事を内心で漏らしためいは白炎の渦を消すと、次に破片が散っている範囲の地面を強酸の沼に変える。
ジュウジュウと溶けていくソシオの破片を眺めながら、めいは世界中を調べていく。
(何処かで復活している様子は確認出来ませんね。世界の外に逃げたのか、はたまた本当にこれで終わりなのか)
何となく拍子抜けしたような気分になりながらも、めいは内心で首を捻る。
その間にも、破片はジュウジュウと音を立てて溶けていく。それを眺めていためいは余裕が出てきたのか、一体あれの材質は何なのかと疑問を抱いた。
とはいえ、もうほぼ溶けてしまっているので、今更調べるというのも難しい。それに、破片が僅かでもあればソシオが復活しそうなので、たとえ溶けていなくても調べる余裕まではないが。
それから程なくして、強酸の沼が全ての破片を溶かしきる。それを確認後、めいは地面を元に戻した。
(もう残りはありませんよね?)
めいはキョロキョロと周囲を見回してみるも、破片は僅かも残っていない。それに安堵したところで、改めてジュライの方に目を向けてみる。
(魔力の消耗もですが、それ以上に疲労が濃いようですね。最大限の魔法を立て続けに放ったのも影響しているのでしょう)
離れた場所からジュライの状態を調べてみためいは、意識が戻るまでもう少し掛かりそうだなと判断する。それと共に疑問を抱いた。
(しかし、何故こうも弱いのでしょうか?)
予想以上に弱かったジュライに、めいは首を傾げる。楽を出来たのはいいが、旧時代の力を一部抜き出して取り込んでいたという割には、ジュライの強さは不自然なまでに成長していない。
(かつて最強の一角を約束されていた存在としてはおかしな姿ですが)
気を失って無防備を晒しているその姿に、改めてその事を考えためいは眉根を寄せた。
(抜き出した力の行き先はあれで間違いなかったですし)
めいは封印している旧時代の理から一部を抜き出していた先もしっかりと確認していた。そのうえで今回の用意だったのだが、ふたを開けてみれば、めい一人でも十分だったほど。
理の異なる魔法の影響だろうかとも考えてみたが、あれは世界の理に対して影響があるだけで、設定の方までは関与していない。
(いや、そうとは限らない?)
しかし、そこでめいは、ジュライ達が魔法を行使する為に肉体の方も根幹を変えているという事柄を思い出す。
予想では大して影響は出ないと考えていたが、もしかしたらそうではなかったのかもしれない。そう思い、もう一度ジュライを調べてみる。そうすると、妙な結果が判明する。
(旧時代の理が・・・消えている?)
そう。本来在るべきはずのモノがどれだけ探してみてもそこには無かったのだ。上書きされたとしても痕跡ぐらいは残る。しかし、消えたという表現が正しいように、そこにはきれいさっぱりと何も無かった。
めいはジュライがそれを取り込んでいたのは確認済みなので、その結果は明らかにおかしい。そう思ったところで、ふと視線を感じためいはそちらに目を向けてみると、視線の先にはジュライの傍らからめいの方をジッと窺っているプラタの姿があった。
プラタの姿を確認しためいは、そこで全てが繋がったような気がして頭の中で今までの情報を整理していく。そうすると、一つの可能性が見えてくる。
(ああ、なるほど)
それに思い至り、めいは一人納得する。
(あの妖精が奪っていたのか)
そもそも、めいは確かに旧時代の理をジュライが取り込んでいたのを確認していた。なので、先程改めて調べるまではそれを前提に考えていた事もあり、その後について詳しくは調べていなかった。
なので、これはあくまでも推測でしかないのだが、めいは色々と考えた結果、ジュライから旧時代の理が消えていたのは、ジュライが旧時代の理を取り込んだ後に、何者かがジュライから旧時代の理を奪ったのだろうと推測する。
では誰がだが、ここで重要になってくるのが、痕跡もなく消失しているという部分だろう。それはつまり、取り込んでそう経たずに奪ったか、時間を掛けて引き剥がして奪ったかという事が考えられる。
ジュライは旧時代の理を何回にも分けて吸収していたので、それを悉く取り込んで直ぐに奪うとなると骨が折れるだろう。それにそんな事をする為には、よほど近くに居なければ難しい。
もう一つの時間を掛けて引き剥がすというのは、それだけ時間が掛かる作業の準備を済ませたら、後は放置していればいいという訳ではないので、こちらもかなりの手間が掛かる方法だ。こちらの方法もやはり、よほど近くに居なければ難しい作業である。
何者かがジュライの近くに潜伏していたという可能性も否定は出来ないが、プラタ達が護る場所で見つからずにそんな事が出来るのは、それこそめいぐらいのものだろう。
めい自身にそんな事をした記憶は無いので、他には誰にも出来ないという事になる。つまり、犯行はよほど近くに居られる者という事になる。それを踏まえて考えると、幾人か候補は上がるが、有力候補は一人しか居なかった。それは当然、プラタという事になる。
ジュライの近くに常に居て、それをおかしいと思われない唯一の存在。つまり、前提がジュライが旧時代の理を取り込んだ後に奪われた。であれば、プラタ以外には考えられなかった。
他にも、旧時代の理をジュライが取り込んでいる事に気がつける者で、尚且つそれを取り出せる者という条件も付くから、プラタ以外には考えられない。敢えて言うならばシトリーだろうが、そうなると立ち位置が少し遠い。
では、動機はと考えたところで、めいはプラタの種族を改めて思い出す。
(大分変異してきていますが、そういえば、あれはまだ妖精でしたね。いや、全く別の種に変わっていたとしても、結局は基が妖精である事に変わりはありませんが)
ソシオの元々の種族と同じ妖精種。それがプラタの種族だ。そして、妖精種にはある特徴があった。それは――。
妖精は世界の観測者として世界と距離を取り、世界を傍観してきた種族であるが故に、何かに対して興味を持つという事が極端に薄い種族であった。しかしその反面、何かに興味を持った時の執着がもの凄い種族でもあった。
その特徴が顕著に表れていたのがソシオ。彼女は興味を持った相手であるオーガストに段々と執着していき、その横に並ぼうとして、遂には種族の枠を超越し、かなりの強さを手に入れたのだった。
実は妖精には、もう一つ特徴が備わっている。それは強烈なまでの独占欲。強い執着から派生するそれは、世界と距離を置き、何物も得ることがなかった妖精ならではの反応なのかもしれない。
先程のソシオの場合だと、もしもソシオがオーガストよりも強かったと仮定すると、ソシオはおそらくオーガストを何処かの世界に閉じ込めてしまうだろう。そのうえで、その世界のオーガストと自分以外の存在を全て抹消し、オーガストには自分のみを見続けるように強要していたことだろう。それでいながら、もしもオーガストが抵抗するようならば、手足ぐらいは平然と切り落としていたとしてもおかしくはない。最悪、オーガストを殺して死体を持ち歩くぐらいはしたかもしれない。それぐらいに独占欲が強かった。
もっとも、実際はオーガストの方がソシオよりも遥かに強いので、そんな事態にはならなかったが。代わりに自分だけを見ていてもらう為にソシオが己を高めていた訳だ。
では、プラタの場合はどうなのかというと、ソシオに比べればどちらもかなり大人しかった。プラタはジュライよりも強かったというのに、ジュライには自由があったのだから。
(我が君があれから離れたというのに、あの妖精が離れなかったところで、その入れ込みように気がつくべきだったのかもしれませんが)
ジュライとプラタの出会いはそう決められていたからなのだが、その後にその設定はめいが全て封印してしまった。なので、オーガストがジュライから離れた辺りでは既にその設定の繋がりはかなり薄くなっていたはずなのだ。そして、現在は完全にその設定は消えている。
そうしてその意思を縛るものはなくなったというのに、プラタは変わらずジュライの傍に居続けていた。それはつまり、その段階で既にプラタはジュライに執着し始めていたという事。
現在はどこまでそれが進行しているかは不明だが、そんな相手から設定を奪うというのはどういう事か。それについてめいは思案した結果。
(外敵は全て自分で処理し、相手は籠の中で大事に保護する。といったところですかね? という事は、独占欲まで出ていそうですね・・・まぁ、近くに強烈なのが居たせいで気にも留めませんでしたが)
そう考えながら、めいは意識を集中してプラタを詳しく調べていく。