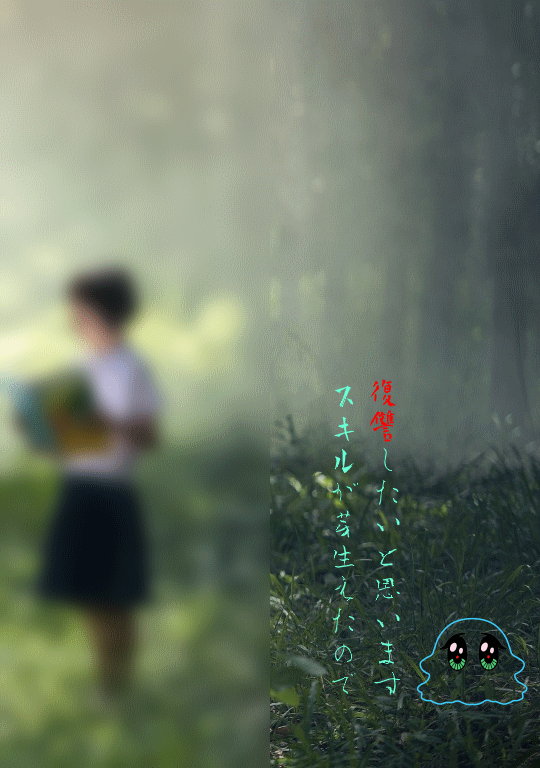第十話 待ち人
豪奢とは思えないが、奇麗に整えられた天幕の中で、同じく粗末ではないが質素な福に身を包んだ男が報告を聞いていた。
同年代の男を背後に従えている様子は、男がある一定の権力を持っている事を現している。
天幕での生活は長期化しているが、本人たちはまったく気にしていない。連れてきた者たちも、交代で帰国させている。すでに、包囲網は完成している。そのうえで、窓口を開けて待っている状況だ。
「ユリウス殿下。彼の方は、無事に国境を越えられました」
「そうか・・・。クリスにも・・・。必要ないか?」
「はい。別の者が、報告に向かいました」
「それで?」
ユリウス王太孫は、伝令の姿をした密偵から報告を聞いている。密偵は、彼の配下ではなく、彼の婚約者であるクリスティーネ・フォン・フォイルゲン辺境伯の配下だった者たちだ。現在は、フォイルゲン辺境伯から離れて、ウーレンフートに拠点を移している。商会の会員としての身分を持って活動を行っている。
「はい。切り捨てる方向に動いています」
頭を下げたまま、密偵は情報を開示する。すでに、報告は行っているのだが、ユリウスが密偵から直接話を聞きたいと言って、伝令のフリをして天幕に招いた。
「ははは。クリスの予想通りか?」
密偵から状況を聞いて、ユリウスは婚約者の推論が正しかったことを認めた。
ユリウスは、共和国がデュ・コロワ国を見捨てないと考えていた。共和国の食糧事情を考えれば、デュ・コロワ国を切り捨てるのは愚策だ。ダンジョン依存率が高い共和国で、ダンジョンからのドロップ率が下がっている情報を、共和国の首脳部は把握していない。持っている情報が違うのだから、違う結論になってしまうのはしょうがない。
クリスティーネは、共和国が持っていると思われる情報から”切り捨てる”と推論を出した。ユリウスは、自分が持っている情報から推理している。わずかな違いだが、これからの方向から考えれば、大きな違いになる。
「はい。デュ・コロワからの伝令が殺されました」
「状況は?」
「抑えています。お館様が作られた道具で、録画しています」
「そうか、俺は・・・。奴に借りを返そうと、また借りを作ってしまったのだな」
「ユリウス様。それは・・・」
「わかっている。しかし、借りだと思っていても、奴は貸しているとは思っていないのだろう?」
「ユリウス様。アルは」「ギード。わかっている。嫉妬とは違う。そうだな、俺の我儘だ・・・。傲慢だとわかっているが・・・」
伝令役を務めていた者が、頭を深々と下げてから天幕を出る。
ギードの反対側に居た男が、懐に入れていた道具の発動を止めた。
「ハンス?」
「もう、遮音結界は必要ないだろう?新しく改良された物でも、消耗はする。必要な時だけ使うようにしている」
ハンスの説明で、ユリウスは納得したのだが、ハンスの意図は違うところにある。
これ以上、機密につながるような話をユリウスにさせたくなかった。それに、実際に、起動している状況では中の音が外に漏れないのは当然だとして、外の音も遮断されてしまう。
アルノルトは、遮音結界の弱点をユリウスたちにも伝えてある。遮音結界は、音を遮断する結界だ。音は、空気の振動で伝わる。空気は遮断していないが、空気の波を遮断しているために、外側と内側に大きな壁があるような状態になっている。
内側の音が伝わらないのはメリットだが、外の音が伝わってこないのは、おおきなデメリットだ。特に、戦場で使う場合には”音”は情報の一つだ。
「そうか・・・。改良版か?」
「はい。あの・・・。街?には、刺激的な物が多くて・・・。クリスティーネ様から持っていくように言われました」
ダンジョンの周りにアルノルトが作った”村”だけど、本人以外は、”街”と呼称している。
正式な名前は、共和国の出方次第だ。名前を付けずに放置するのには、大きくなりすぎている。行商人は使わないルートだが、王国からの軍が移動しているのは、周知されている。
そのために、諸国の密偵の出入りが確認されている。
ダンジョン村の存在は知られていると考えて動いたほうがいいだろうと言うのが、ユリウスたちの共通認識だ。
「ははは。ウーレンフートと違ってか?」
「はい。領都と違って、本当に好き勝手に・・・。いえ、失礼しました」
ハンスの言葉は正しい。
ユリウスも、クリスティーネも同じことを考えた。
「いや、本当にそうなのだろう。ウーレンフートだけでも、手一杯なのに・・・。本当に、奴を自由にすると、後始末が・・・。違うな・・・。ギード。陛下に報告は?」
以前のウーレンフートは、ダンジョンの上に街が出来ていた。
ダンジョンのおかげで街が潤っているだけの場所だ。潤っているが、問題も多い場所だと認識されていた。
ウーレンフートは、各国の密偵が活動するのには適した場所だった。
雑多な者たちが多く存在しているダンジョンにアタックする者たちが多く過ごしているために、多くの人がウーレンフートに集まって、そしてダンジョンの中で命を散らしていた。そのために、ウーレンフートでは正確な人口が掴めない状況にあり、税の徴収が機能していなかった。それでも、街として考えれば、ダンジョンから産出した物資の売買から得られる”税”で潤っていた。
「してあります。殿下の好きなようにするように言われています。そろそろ、共和国の相手も面倒に思っていたようです」
「ははは。陛下らしい考えだ。他には?」
「宰相閣下から、なんなら全部をライムバッハ領にしてもよいと伝言をいただいております」
「フォイルゲン殿らしい言い方だ。他には?」
「これを預かっています」
ユリウスは、ハンスの従者から封書を受け取った。
宛名も差出人も書かれていないが、封蝋を見れば誰からの封書なのかわかる。
「仰々しいな」
ユリウスは、面倒そうな表情を崩さずに、封蝋を切った。封蝋を切るためのナイフではなく、アルノルトからプレゼントされた、アルノルトが作ったナイフを使った。普段使いするナイフとして重宝している。懐刀という言葉を、アルノルトから聞いてから、自分の懐刀はアルノルトだというつもりなのか、他にどんなナイフを渡されても変えるつもりはない。
ユリウスは、手紙を読み始める。
想像していた通り、王太子である父親からの手紙だ。
「・・・」
「ユリウス様?」
「あぁ・・・。おまえたちは、この内容を知っているのか?」
ハンスとギードは、お互いを見てから首を横に振る。
「クリスは知っていると思うか?」
ギードは首を横に振るだけに留めた。
「クリスティーネ様に知らせているのなら、封書の形にしないと思います」
「そうだな・・・」
ユリウスは、王太子からの手紙に目を落とす。
読み返しても、内容は変わらない。
ユリウスは、ハンスとギードを手招きして、持っていた手紙を渡した。
二人は、交互に渡された手紙に目を通した。
個人的な事が書かれていた手紙ではない部分だけだが、数枚にわたって書かれた内容は、二人の顔色を変えるには十分な威力を持っていた。
二人から戻された手紙を受け取ったユリウスは、魔法を発動して手紙を燃やした。
内容は頭の中に入っている。内容は残しておかないほうがよいと判断した。
「殿下?」
「大丈夫だ。いきなり、突撃命令は出さない」
「・・・」
「大丈夫だ。まだ、”疑い”の段階だ。デュ・コロワに証拠が”ない”ことを・・・」
「証拠が有ったら?」
「どうしたらいいと思う?」
ユリウスは、まっすぐに前だけを見て、冷え切った声で二人に問いかけた。
二人も、ユリウスが何を考えているのかわかる。王国の王太孫としては、絶対に出してはダメな命令だと把握している。しかし、二人はユリウスが出すと思われる命令を止めることはできない。自分たちが、その命令を望んでいるのだとわかっている。
手紙が燃え切ったタイミングで、外が騒がしくなる。
確認のために、従者が天幕を出た。